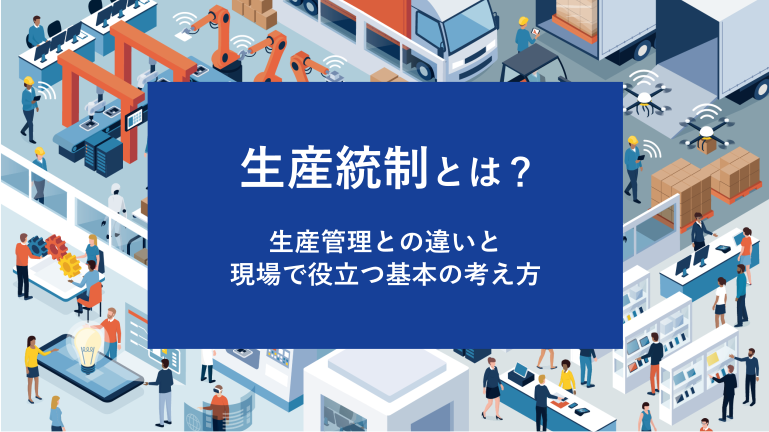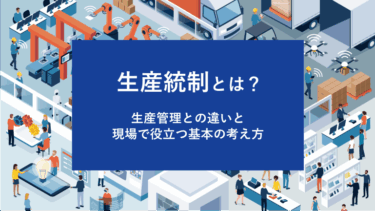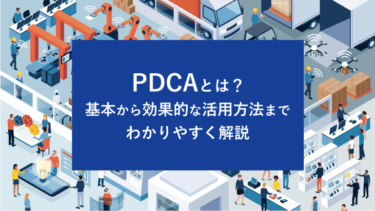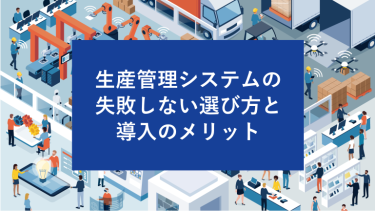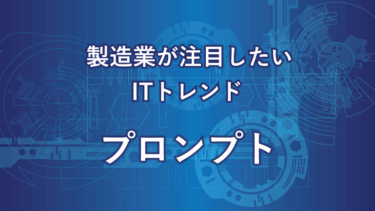製品を作る際、生産計画を基に進められるのが一般的です。生産の流れを計画通りに進めることで、効率的な生産を可能とします。
しかし、必ずしも計画通りに進むわけではなく、トラブルによって問題が発生することも多いです。問題を抱えたままでは計画通りに生産が行なえず、納品の遅れや品質の低下を招いてしまうでしょう。
生産統制は、そんな計画外となってしまった生産を正すための取り組みです。問題を解決することで、本来の計画通りに生産が進められるよう統制を行ないます。顧客の期待に応えるためにも、計画外となった時の取り組みについて知っておく必要があるでしょう。
生産統制とはどのような取り組みなのか。生産統制の仕組みや生産管理との違いなどについて紹介します。
生産統制とは何か?
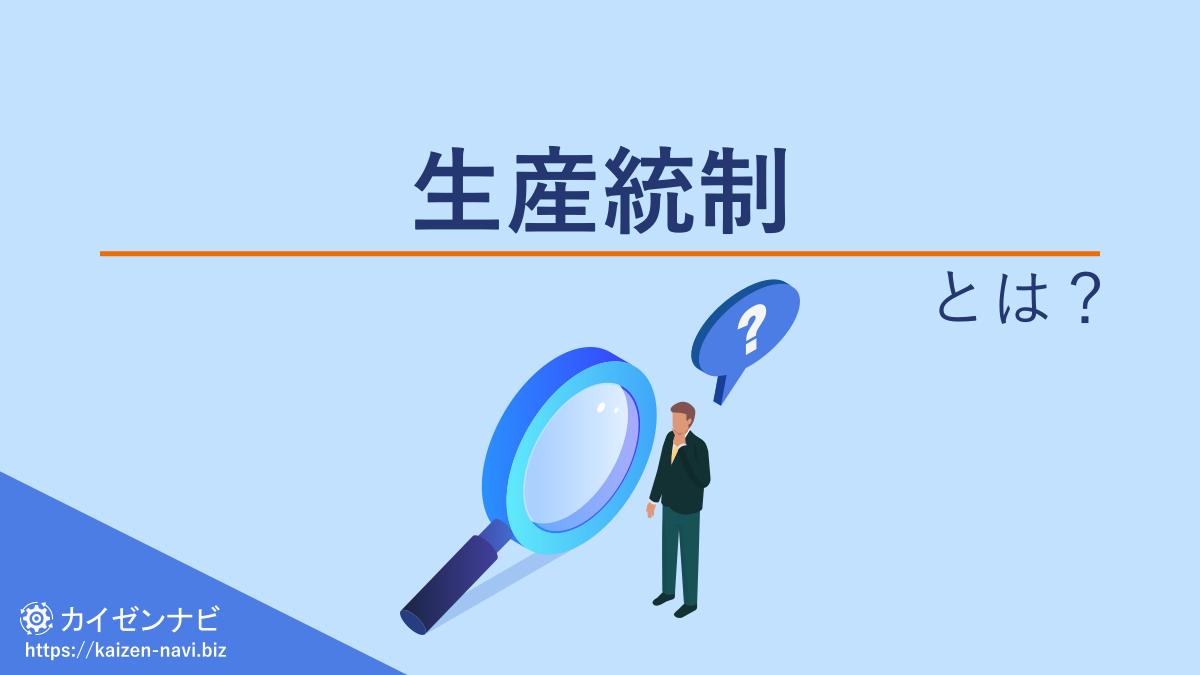
生産統制とは、生産計画通りに進められるよう、工程やスケジュールを管理(調整・修正)する取り組みのことです。生産状況を監視し、もし生産状況に問題が生じるようなら、問題を解決するため対策を講じます。
例えば、一日に製品を100個作るはずが、現状では50個しかできていませんでした。このままでは納期に間に合わないため、作業人数を増やし、生産数を上げるよう取り組みます。
ほかにも、不良品が多ければ機械を修理して品質を維持したり、ボトルネックが生じるようなら工程を見直したりなど、計画通りに進行できるよう生産を調整し統制を行ないます。
もちろん、計画通りに進めば生産統制は必要ありませんが、計画通りにならないことは多いです。影響が大きくならないよう、早めの対策が求められます。
生産統制の目的
生産統制を必要とする目的は、主に3つ挙げられます。
納期の順守
一つ目は、納期に間に合わせることです。納期の遅れは顧客からの信用を損ねる結果となるため、生産に遅れは生じないよう、生産統制を行ないます。
顧客からの信用は、企業の売上に影響します。いくら良い製品であっても、信用が無いと製品を選んでもらえません。近年はインターネットによって評判が広まりやすく、納期を守らないと、すぐに悪い評判が広まってしまうでしょう。
納期を守るためにも、生産状況を正しく管理する必要があります。
生産性の向上
二つ目は、生産数を向上させることです。生産のトラブルは生産数を落とす結果となるため、トラブルを解決することで生産数を向上させます。
生産数の低下は、納期を遅らせる原因にもなります。納期を順守するためにも、生産数の向上は必要です。
品質の維持・向上
三つ目は、品質の維持や向上をさせることです。正しく作業されないと品質が安定しないため、正しい作業となるよう生産状況を整えます。
また、生産の遅れは作業を雑にさせます。納期に間に合わせようと急ぐようになり、それによっても品質を低下させるでしょう。
製造業では、最も重要な要素として、「品質(Quality)」「コスト(Cost)」「納期(Delivery)」の3つ(QCD)を挙げています。この3つは信用や利益に大きく影響する要素であり、生産をするうえで常に意識すべき必要があります。
生産統制をすることは、納期の厳守や品質の維持はもちろん、正しい生産によってコストも抑えます。QCDの維持や向上を目指すうえで、生産統制は重要な取り組みといえるでしょう。
生産統制を構成する3つの要素
生産統制は、主に「進捗管理」「現品管理」「余力管理」の3要素によって構成されています。
進捗管理(進度管理)
進捗管理(進度管理)とは、計画通りに業務が進んでいるかを確認することです。生産計画と進捗を比較し、差異がないかを管理します。そして、もし計画と差異がある場合は、差異をなくすよう調整を行ないます。
進行状況に焦点を当てた要素であり、進捗に問題がないかを判断するうえで重要な要素といえるでしょう。
進捗管理によって生産速度が評価でき、それによって、生産ラインの増産や人数の増員といった対策を取ることができます。
現品管理(在庫管理)
現品管理(在庫管理)とは、現品の有無を確認することです。資材、仕掛品、完成品など、現品の状況や個数などを管理します。
物に焦点を当てた要素であり、生産に問題がないかを判断するうえで重要といえるでしょう。
現品管理によって在庫状況や不良品数などを評価でき、それによって、生産数の調整やメンテナンスといった対策を取ることができます。
余力管理(負荷管理・能力調整)
余力管理(負荷管理・能力調整)とは、リソースの余力を確認することです。人、モノ、資金など、生産に使えるリソースや使用したリソースなどを管理します。
労働力に焦点を当てた要素であり、労働負荷を判断するうえで重要といえるでしょう。
リソースは、ある程度余力を持たせることが大切です。余力が無いとトラブルが生じた際に対処が難しくなります。労働負荷も増してしまい、作業員への負担になってしまいます。
しかし、余裕があり過ぎるのも問題があります。余裕があることで、今度は労働力を遊ばせてしまうからです。生産する機会も減ってしまい、出費に対して利益が望めません。
労働負荷は多すぎても少なすぎてもダメであり、効率の良い生産にするためには、バランスの取れた配分が求められます。
生産管理と生産統制の違い
生産統制以外にも、生産管理と呼ばれる取り組みも存在します。
生産管理とは、生産業務を管理する取り組みのことです。生産計画から出荷まで生産に関する一連の流れを管理することで、QCDの維持や向上を目指します。
生産管理と生産統制の違いはどちらも生産をサポートするための取り組みですが、それぞれ管理する範囲が異なります。生産管理は生産そのものを管理するのに対して、生産統制は生産計画の流れをコントロールといったように、それぞれ役割は異なるのです。
例えば、生産管理が需要予測から計画、調達、出荷まで生産プロセス全体を設計・運営する「司令塔」であるのに対し、生産統制は計画が実行段階に移された後、現場レベルで日々その進捗を監視し、計画からの逸脱を修正する「現場指揮官」の役割を担います。
それぞれの関係性としては、生産管理の一部分が生産統制であり、生産管理に含まれる生産計画を成功させるために、生産統制が行なわれます。
生産管理と生産統制、どちらも生産をサポートすることから親密な関係にあります。効率よく生産を行なうためにも、互いに連携を取り合うことが重要です。
現場でよくある生産統制の課題
生産統制は、正しく生産を行なうために必要な取り組みです。生産統制によって生産状況が正されることで、QCDを守ることができます。
生産統制を正しく行なうためにも、以下のような課題を解決していくことが大切といえるでしょう。
進捗の遅れと納期の悪化
「気づいたら計画から大幅に遅れていた」「特定の工程でいつもボトルネックが発生し、結果的に納期に間に合わない」といったように、進捗に遅れが生じると納期の悪化を招きます。
納期の悪化は顧客からの信用を損ねる原因となるため、生産統制によって防がなければなりません。
主な取り組みとしては、作業員の増員や作業工程の調整などが挙げられます。課題の解決によって、作業効率の改善が目指せるでしょう。
過剰在庫・欠品の発生
「使わない部品や仕掛品が現場に溢れている」「急な計画変更で必要な部品が足りず、生産ラインが止まってしまう」といったように、現品数が把握できていないと、過剰在庫や欠品といった事態を招きます。
過剰在庫は保管スペースを圧迫し管理コストを増大させ、欠品は生産する機会や販売する機会を損ねる結果となります。出費を増やし利益を減らすことから、在庫状況も意識する必要があるでしょう。
主な取り組みとしては、倉庫の整理整頓や目録の作成など、在庫状況の見える化が挙げられます。現品管理が行なわれることで、必要なモノを必要な量だけ作れるようになります。
また、生産管理システムを導入すれば、在庫管理をリアルタイムで行なえます。より在庫状況が鮮明となり、生産計画の参考にできるでしょう。
ほかにも、トヨタ自動車では、詳細が記された帳票をライン間で共有する「カンバン方式」と呼ばれる方法を採用しています。情報共有を強化することが、過剰在庫や欠品を防ぐポイントとなるでしょう。
品質の不安定化
「急な増産で無理な生産をした結果、不良品が多発した」「作業者によって品質にバラつきが出てしまう」といったように、作業が統制されていないと、品質にバラつきが生じてしまいます。
品質も、納期と同様に顧客の信用に大きく影響します。QCDはどれも重要ではありますが、品質は特に意識すべき要素といえるでしょう。
主な取り組みとしては、作業員の増員や作業の標準化などが挙げられます。ほかにも、実施と改善を繰り返して精度を高めるPDCAサイクルの活用や、現場環境を整える5S活動の実施なども効果があります。
また、品質の安定化だけではなく、不良品の発見も重要な要素です。万が一不良品が発生しても、しっかりと発見できれば、不良品が出荷されるのを防ぐことができます。
センサーの導入や品質検査の訓練なども、合わせて実施していきましょう。
現場の疲弊とモチベーション低下
「頻繁な計画変更や残業指示に現場が振り回されている」「頑張っても評価されず、改善意欲が湧かない」といったように、精神的な負担も生産に影響を与えます。
現場の疲労とモチベーションの低下は、どちらも労災リスクを高めるものです。労災が発生すれば、生産を中断する必要が出てきます。作業効率も低下し、納期の悪化を招いてしまうでしょう。
主な取り組みとしては、ITシステムを使ったリアルタイムな伝達や表彰システムの導入などが挙げられます。伝達が早ければ対応に余裕が持てますし、目に見えた評価は「自分も頑張ろう」といった気持ちにさせます。
ほかにも、作業動線の改善や交代制勤務の導入など、負担を減らすための環境づくりも大切です。
データと現実の乖離
「システム上の在庫数と実際の在庫数が合わない」「日報の入力が手間で、正確な作業時間や進捗が把握できない」といったように、管理に問題があると、データと実際の状況が合わなくなります。
記録との乖離は、生産計画の破綻を意味します。生産計画はデータを基に立てられますので、そのデータに間違いがあるようだと、計画通りに生産ができないでしょう。納期が遅れるのはもちろん、現場が混乱することで品質の低下や現場の疲労など、さまざまな問題も誘発させてしまいます。
主な取り組みとしては、ITシステムを活用したデジタル管理の導入が挙げられます。生産全体を一元管理することで、現状に合った正しいデータを残せます。入力する手間がなくなることから、作業負担の軽減やヒューマンエラーの減少にもなるでしょう。
ほかにも、チェックシートで確認をしたり、作業を簡単にするためマニュアルを作成したりなど、アナログでできることもあります。
課題解決への戦略的アプローチ
現場が直面する課題を克服するには、体系的なアプローチが必要です。ここでは代表的な4つの解決策を紹介します。
PDCAサイクル
PDCAサイクルは、改善活動の基本フレームワークで、継続的な業務プロセスの進化を促します。
Plan-Do-Check-Actを繰り返す改善の基本。データに基づき体系的に問題解決を進め、継続的な進化を組織に根付かせます。
主に「品質の不安定化」「現場の疲弊と意欲低下」を解決することに用いられます。
ビジネスで改善を進めるうえでよく聞く「PDCAサイクル」。この記事では、PDCAサイクルの基本から、実際にどう活用できるかを詳しく説明します。また、この記事を読むことで、業務改善をどのように進めるかの具体的な方法が理解できるようにな[…]
5S活動
5S活動は、整理・整頓・清掃・清潔・しつけの5つからなる職場環境を整える活動で、全ての改善活動の「土台」を築きます。
安全で効率的な職場環境は、品質安定や在庫管理の精度向上に直結し、全ての改善活動の土台となります。
主に「品質の不安定化」「過剰在庫・欠品の発生」「現場の疲弊と意欲低下」を解決することに用いられます。
製造業でよく耳にする5S活動。現場環境を改善することで作業効率や生産性が向上することから、多くの企業が注目・取り入れています。 もちろん、5Sの考えは製造業だけではありません。医療業界、物流業、サービス業、小売業なども実施して[…]
カンバン方式
カンバン方式は、JIT(ジャストインタイム)を実現するための道具として「造りすぎのムダ」を徹底的に排除します。
後工程が「必要なモノを、必要な時に、必要なだけ」引き取るプル型生産。在庫を極小化し、問題点を強制的に顕在化させます。
主に「過剰在庫・欠品の発生」「進捗の遅れと納期悪化」を解決することに用いられます。
製造業において、適切な在庫管理を行うことはとても重要です。 欠品が発生すると販売機会を損失してしまい、逆に造りすぎると過剰在庫になってしまうため、バランス良く製品を製造していく必要があります。 自動車メーカー「トヨタ自動車」は[…]
生産管理システム
生産管理システムは、情報のデジタル化と一元管理し、データと現実の乖離を解消します。
情報を一元管理し、リアルタイムな可視化を実現するITツールとして、データと現実の乖離を解消し、迅速な意思決定を支援します。
主に「データと現実の乖離」「進捗の遅れと納期悪化」「過剰在庫・欠品の発生」を解決することに用いられます。
生産をサポートする生産管理システム。近年は工場のデジタル化が推進されており、生産管理システムを導入する企業も増えてきています。中には、生産管理システムの導入を、既に検討している企業もあるかもしれません。 ですが、生産管理システ[…]
まとめ:統制力を高めると現場が安定する
生産統制とは、生産通りに進められるよう、生産環境を調整することです。生産が遅れるようならスケジュールを調整し、品質が安定しないなら生産体制を見直すなど、それぞれに対策を行なうことでスムーズな生産を可能にします。
生産管理と混同されることも多いですが、生産統制は生産の流れを整えるための取り組みです。大まかにですが、生産管理における進捗管理や在庫管理の一部が、生産統制であると思っていいでしょう。
生産統制は、いわば生産における修正力です。計画にズレが生じても、修正力が強ければ現場は安定します。安定した生産ができるよう、しっかりとした生産統制を心がけてください。