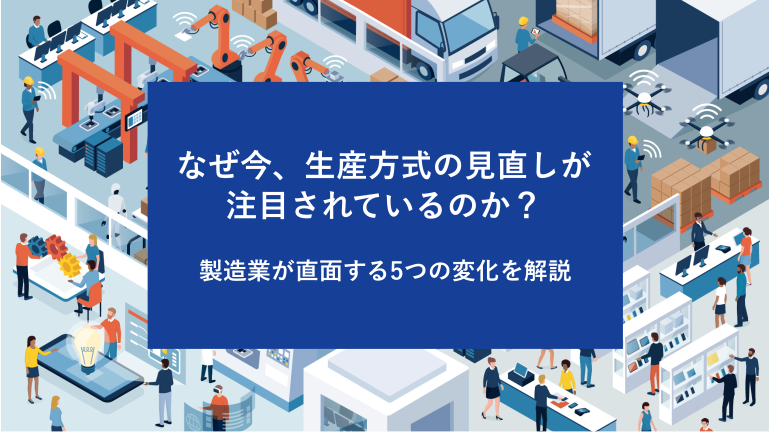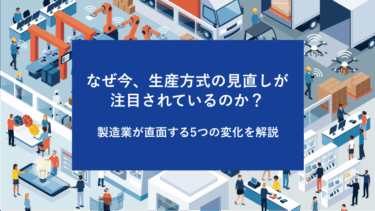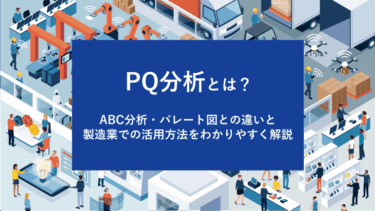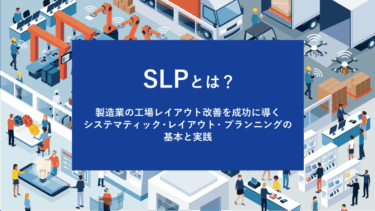製造業を取り巻く環境が大きく変化する中で、これまで主流だった「受注生産」や「見込生産」といった方式も、状況に応じた対応が求められる場面が増えています。
多くの企業では、従来の方式を基盤としながら、ハイブリッド型や柔軟な生産体制への移行を進めています。実際、製造業向けソリューション各社でも、見込生産・受注組立・個別受注など多様な形態をサポートしており、状況に応じて生産方式を組み合わせる動きが広がっています。
では、なぜ今、生産方式の見直しがこれほど注目されているのでしょうか。背景には、製造業全体が直面している5つの大きな変化があります。
この記事では、まずその必要性を整理し、次に変化の中身を具体的に見ていきます。
なぜ今「生産方式の見直し」が必要なのか
これまでの製造業は、「安定した需要を前提にした計画生産」が中心でした。しかし現在は、市場変化のスピードが速く、“予測通りに作れば売れる”という時代ではなくなっています。
顧客のニーズは細分化し、製品ライフサイクルは短期化。そこに原材料の調達難や海外拠点のリスクが重なり、生産現場では「計画どおりに回らない」ケースが増えています。
その結果、受注生産では納期対応に追われ、見込生産では在庫を抱えるという、どちらの方式にも課題が生じています。
このような状況を打開するには、生産方式そのものを柔軟に見直し、環境に合わせて最適化することが欠かせません。
生産方式の見直しは単なる改善活動ではなく、企業の競争力を左右する「経営戦略の一部」として位置づける必要があります。
製造業が直面する5つの変化
生産方式の見直しが注目されている背景には、単なる景気の波だけでなく、製造業全体の構造変化があります。市場の変動が激しく、顧客の要望も多様化する中で、従来の「受注生産」「見込生産」という区分では対応しきれない場面が増えています。
加えて、デジタル技術の進化やサプライチェーンリスク、ESG対応など、経営を取り巻く環境も大きく変化しました。こうした複数の要因が同時に進むことで、企業は「どのように生産方式を選択・組み合わせるか」という課題に直面しています。
ここでは、製造業が直面している5つの変化を整理し、それぞれが現場や生産管理にどのような影響を及ぼしているのかを見ていきましょう。
- 需要変動と市場の読みづらさ
- 顧客ニーズの多様化と短納期圧力
- DXによる生産管理の進化
- サプライチェーンリスクとBCP対応
- ESG・環境対応の観点
需要変動と市場の読みづらさ
近年、製造業では「需要が読めない」という悩みが常態化しています。
コロナ禍による消費変化、為替の乱高下、地政学リスクなど、需要を左右する要因が複雑化し、これまでの経験や勘に頼った予測では対応しきれなくなっています。
需要が読めなければ、見込生産では在庫が膨らみ、受注生産では納期が遅れる——。どちらの方式にも限界が見えています。
このような状況では、“どこまでを見込で作り、どこから受注で作るか”という判断基準を再構築することが重要です。
顧客ニーズの多様化と短納期圧力
顧客が求める製品のバリエーションが増え、「多品種少量生産」は多くの業界で当たり前になりました。
さらに、EC化やサプライチェーンの短縮により、「できるだけ早く欲しい」という短納期要望も増えています。
こうした中で、見込生産だけでは在庫リスクが高く、受注生産だけでは納期が間に合いません。
現場では、標準部品を見込で作り、最終組立を受注後に行なうなど、“部分的なハイブリッド生産”への移行が進んでいます。
つまり、顧客ニーズの多様化は、生産方式の柔軟化を求める大きな原動力になっているのです。
DXによる生産管理の進化
かつて「生産計画は経験と勘で立てるもの」だった時代から、今やデータに基づく判断へと変わりつつあります。
AIによる需要予測、IoTでの設備稼働データ収集、生産管理システム(MES・MRP・SCM)などの導入により、
現場と経営の情報をリアルタイムに結びつけることが可能になりました。
これにより、「見込」「受注」どちらの生産比率を高めるかをシミュレーションで検討できるようになり、従来の“勘と経験”に頼る計画から、“根拠のある最適計画”への転換が進んでいます。
もっとも、データの整備やシステム連携、人材のデジタルスキル育成など、DXを現場に定着させるには時間と継続的な取り組みが必要です。
DXは単なるIT導入ではなく、生産方式を再定義するための仕組みであり、データを活かした“柔軟な計画立案”を実現する基盤として位置づけられています。
サプライチェーンリスクとBCP対応
コロナ禍や国際情勢の影響により、世界的に物流の混乱や部品調達の遅延が発生しました。
これまで「必要なときに必要な分だけ作る」ことを前提にしていた企業も、部材が届かず生産ラインが止まるというリスクを実感したはずです。
こうした状況は、日本貿易振興機構(JETRO)が2022年に実施した調査によると、サプライチェーンの見直しを進める企業のうち、「国際輸送の混乱・輸送コストの高騰」を理由に挙げた割合は35.2%と最も多く、次いで「需要の増加」が32.5%、「移動制限・操業規制」が20.6%、「原料・部品不足」が19.2%が続くというデータにも表れています。
この結果からも、多くの製造業がグローバル物流の不安定さを背景に、調達・生産・在庫の分散や国内回帰などの対策を検討している実態がうかがえます。
BCP(事業継続計画)の観点からも、サプライチェーンの見直しは今や避けて通れないテーマとなっています。
国内回帰という言葉を知っていますか?新型コロナウイルスが蔓延する近年、様々な企業が国内回帰を実施しています。今までの生産状態では企業の赤字となるため、新しい生産状況が必要となってきています。 国内回帰とはどのような対策なのか。[…]
ESG・環境対応の観点
近年、企業には利益だけでなく、環境や社会への配慮が求められるようになっています。
過剰生産や在庫廃棄は、コスト面だけでなく環境負荷の観点からも問題視されます。そのため、「必要なものを、必要なときに、必要な分だけ生産する」ことが、ESG経営を実践するうえで欠かせない視点となっています。
また、モジュール化やリユース可能な部品設計など、環境負荷を抑えつつ生産効率を高める取り組みも増えています。
つまり、生産方式の見直しは、単なる生産効率化ではなく、持続可能なものづくりへの第一歩なのです。
まとめ:これからの製造業に必要な「柔軟な生産設計」
これまで見てきたように、製造業を取り巻く環境は大きく変化しています。需要の不安定化、顧客の多様化、デジタル化、サプライチェーンの再構築、そして環境対応。
こうした変化の中で、「受注生産」と「見込生産」という二つの枠組みだけでは、もはや十分に対応できません。
これからの時代に求められるのは、環境の変化に応じて生産方式を柔軟に切り替えられる設計力です。たとえば、需要が安定している製品群は見込生産で効率化し、変動の大きい製品は受注生産に切り替える。一部の中間部品だけを見込で生産し、最終組立は受注後に行なうといったハイブリッドな考え方も有効です。
このような柔軟な生産設計を実現するためには、現場だけでなく、経営・調達・営業を含めた全社的な連携が欠かせません。
さらに、データを活用した需要予測や生産計画の精度向上も重要です。システムを導入して“現場の勘”と“データの裏付け”を組み合わせることで、変化に強い生産体制を築くことができます。
生産方式の見直しは、一度きりの取り組みではなく、継続的に改善を重ねていくプロセスです。市場の変化を敏感に捉えながら、自社のリソースや顧客ニーズに合った最適な方式を模索していくことが、これからの競争力につながります。