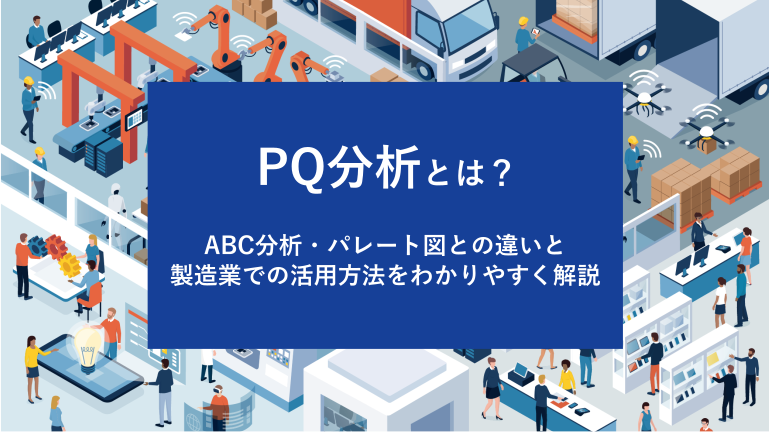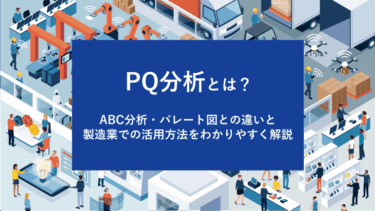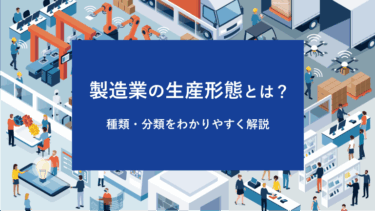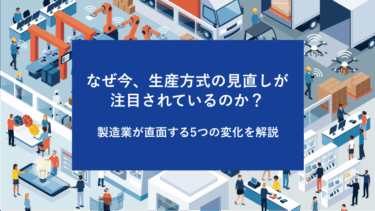利益を上げるためには、売れる製品=重点製品を見極めて前面に押し出すことが重要です。
しかし、重点製品を売り出すためには、どの製品が重点製品なのかを見極める必要があります。
PQ分析は、そんな重点製品を見極めるためのフレームワークです。重点製品を特定することで、生産計画や販売戦略を決めることができるようになります。
PQ分析とはどのようなフレームワークなのか。使い方やABC分析との違いなど、PQ分析の活用方法について紹介します。
PQ分析とは?基本構造と目的
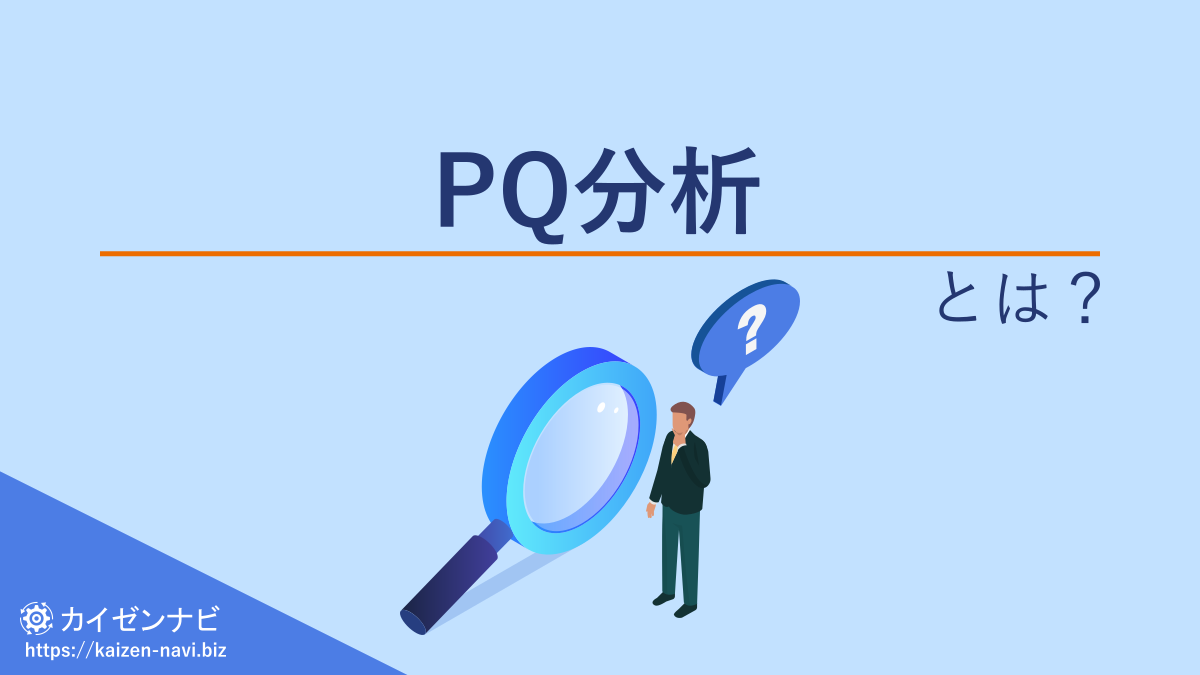
PQ分析とは、重点製品を見つけるためのフレームワークのことです。重点製品とは影響の大きい主力製品のことであり、改善を行なう際、優先的に対策がとられます。
PQ分析では、生産品目と生産量の2軸で分析します。それぞれのデータを棒グラフでまとめたものをPQ図と呼び、PQ図を基に重点製品を見極めるのです。
効果的な対策を行なうためには、影響力の大きい製品に対して行なうことが効率的です。生産管理や販売戦略の見直しを行なう上で、重点製品の見極めはとても重要となってきます。
PとQの意味
PとQは、それぞれ生産品目(Product)と生産量(Quantity)を示します。生産品目を横軸に、生産量を縦軸に配置し、生産数が多い順に並べ替えることで影響の多い生産品目を特定するわけです。
また、Pを事故の種類、Qを発生件数に置き換えれば、最も問題となっている事故の種類も把握できるでしょう。
元々の項目は生産品目と生産量ですが、品目と量を置き換えることで、さまざまな分析に活用できます。
PQ分析の目的
PQ分析を行なう目的は、影響が高い種目を見分けるためです。生産品目が多いと、どの製品に手を加えれば良いのかわかりません。より効果的な改善を行なうためにも、PQ分析で最も影響力のある品目を見分ける必要があります。
また、影響力が高い種目がわかれば優先順位も決めやすいです。影響力の高い種目から実施することで、効率的に改善が行なえます。
ほかにも、生産量の多さから生産方式を見直したり、客観的なデータを用いて会議や説明に活かしたりなど、見やすくまとめることで情報の共有がしやすくなるでしょう。
PQ分析のプロセスと流れ
PQ分析はどのように行なえばいいのか。実際に行なう際のプロセスを紹介します。
- 分析対象製品のデータ収集
- データの整理と並べ替え
- PQグラフの作成
- 生産方式の決定
- レイアウトの見直し
- 結果の評価とモニタリング
分析対象製品のデータ収集
まずは、必要なデータの収集です。生産品目と生産量を、それぞれ表でまとめてください。
その際、売上高などの別の項目もまとめておくと、後で別の視点から分析ができます。
事故の種類や件数など別の項目で行なう場合は、それぞれに合わせたデータを用意してください。
データの整理と並べ替え
データが集まったらデータを整理します。生産量が多い順に並べ替えてください。
Excelには降順で並べ替える機能もあり、データを整理しやすいです。データをまとめる際は、Excelを活用するのがおすすめです。
また、累積構成比を求めてみると、生産量が多い上位20%の製品が、全体の生産量の約80%を占めることが多いです(パレート分析)。端的に言えば売れ筋製品であり、企業にとっての重点製品だといえるでしょう。
PQグラフを作成して視覚的に確認
データを整理し終わったら、PQグラフを作成し視認しやすくします。比較しやすいよう棒グラフで作成してください。
Excelには、複数の項目をまとめてグラフ化する機能もあります。簡単にグラフ化ができますので、ぜひ利用しましょう。
パレート分析からパレート図も作成する場合は、完成したPQグラフの上に、合わせて記載すると良いです。
また、PQグラフを大きく3つのグループに分けて考えることもできます。生産量が「多いグループ(累積構成比が70%未満)」「平均的なグループ(累積構成比が70%以上90%未満)」「少ないグループ(累積構成比が90%以上)」の3つです。
それぞれを「重点製品(Aグループ)」「標準製品(Bグループ)」「非重点製品(Cグループ)」として評価することができ、ABC分析を基に今後の生産方式を決められます。
生産方式の決定
生産方式とは、生産の手順のことです。流れ作業を行なうライン生産方式や注文に合わせて生産を開始する個別生産方式など、生産需要に合わせて生産方式を決めていきます。
例えば、重点製品であるAグループは、少品種多量生産の方式を目指します。販売する機会を逃さないためにも、充分な在庫を用意する必要があるでしょう。
逆に、非重点製品であるCグループは、多品種少量生産の方式を目指します。Cグループは目玉製品ではないため、在庫をたくさん用意する必要はありません。むしろ、今よりも売るために、オーダーメイドなどの新しい付加価値を持たせる必要があります。
効率的な生産方式は、生産のムダを削減できコスト削減につながります。より企業の利益につなげるためにも、需要に合わせた生産方式の決定が大切です。
レイアウトの見直しと改善
生産方式が決定したら、方式に合わせて設備や工程をレイアウトしていきます。
例えば、少品種多量生産を目指すAグループは、流れ作業によるライン生産が適しています。連続生産によって継続的に作り続けることで、安定して在庫を用意できるでしょう。生産数が多いことから、設備を常に稼働させます。そのため、製品別にレイアウトすることが望ましいです。
中間に位置するBグループは、ロット生産などのまとめて生産する方式が適しています。規定量を決めて生産することで、過剰在庫となる心配はありません。規定量を決めた生産はスケジュール調整がしやすく、ほかの生産と設備を共有しやすいです。そのため、同じ設備を使う同士でグループ別にレイアウトすることが望ましいといえます。
多品種少量生産を目指すCグループは、付加価値を持たせやすい個別生産が適しています。生産数が少ないことで柔軟に対応しやすく、顧客のニーズに細かく応えられます。顧客ニーズによって使う設備も変わってくるため、機能別にレイアウトすることが望ましいといえるでしょう。
ほかにも、工程のやり方によってレイアウトを決めたり、作業者の人数によってレイアウトを決めたりなどの方法もあります。
チームや部署で話し合い、最も良いと思うレイアウトを選んでみてください。
結果の評価とモニタリング
最後に、新しくレイアウトした結果を評価します。変更前と比較して、結果が出ていれば、施策は成功です。他の設備やラインも変更し、改善結果を工場全体に広めましょう。
逆に、結果が出なければ、施策の失敗となります。なぜうまくいかないのかをチームで話し合い、新しい対策を実施してください。
また、モニタリングをした結果、新たに問題が見つかることもあります。そのような場合も、結果をまとめ対策を行ないます。
改善策は、一度行なえば完成とはいきません。時代に合わせて顧客ニーズが変化するため、時代に合わせて生産方式も変えていく必要があります。定期的にPQ分析やABC分析を行ない、その都度、適したレイアウトを選んでいきましょう。
類似する分析手法
PQ分析のほかにも、似たような分析手法があります。どれも「全体の中の重要少数を見つける分析」であるため個別で使うこともできますが、PQ分析と合わせて使うと、より結果の分析がしやすいです。
PQ分析を行なう際は、以下の分析手法も合わせて行なってみてください。
ABC分析
ABC分析は、種目の構成比をABCで3分割し管理するフレームワークです。「重点分析」とも呼ばれ、最も重要度の高いAグループに対して管理や対策を行ないます。
それぞれの分け方は、累積比率によって決まります。累積比率をそれぞれの種目で検出し、70%未満の場合はAグループ、70%以上90%未満の場合はBグループ、90%以上の場合はCグループに分類します。
グループごとに分けて考えることで、個別に種目を評価するよりも対策が取りやすくなるでしょう。
PQ分析と合わせて使われることが多く、ABC分析の結果から、今後の対応を決めていきます。
パレート図
パレート図は、棒グラフと折れ線グラフを組み合わせた分析図のことです。累積比率を棒グラフで記載することにより、直感的に重点製品が分かるようになります。
折れ線グラフが急激に右上がりになるほど、重点製品が集中しているといえるでしょう。
パレート図も、ABC分析と同様にPQ分析と合わせて分析が可能です。PQ図の上に書き足すことが多く、連携して分析がされます。
また、パレート図は品質改善を目的とする「QC7つ道具」の一つであり、課題の解決に使用されることも多いです。「不良品の発生原因」などを調べる際にも、パレート図を活用してみてください。
製造業での活用シーン
PQ分析をどのように活用すれば良いのか。それぞれのシーンで考えてみましょう。
生産管理
生産管理の場面では、生産スケジュールの調整に役立ちます。PQ分析によって重点製品が判明するため、重点製品を中心とした生産スケジュールを組むことができます。
単純に、売れる製品をたくさん作れば利益となります。主力製品は優先的に生産するべきでしょう。
利益向上を目指すためにも、主力製品の把握と生産スケジュールの調整はとても大切です。
在庫管理
在庫管理では、在庫切れ防止に役立ちます。Aグループ製品は売れ行きがよく、在庫も不足しがちです。PQ分析によってAグループ製品を事前に把握しておけば、生産数を増やして在庫切れを防ぐことができます。
逆に、Cグループ製品を把握することで過剰在庫を防ぐことも可能です。PQ分析によって、製品ごとに適切な在庫管理ができるようになります。
改善活動
改善活動では、Cグループ製品の改善に役立ちます。Cグループ製品は生産数が少ない、つまりは売れ行きが悪い製品です。Cグループ製品の売り方や作り方を見直すことで、Cグループ製品の利益を高めることができます。
場合によっては、利益が出ないことから生産が中止になることもあるでしょう。利益を上げるためには、統廃合の判断も必要です。
もちろん、レイアウトの見直しや改善にも役立ちます。それぞれに合った生産方式にすることで、生産効率を高めることができます。
原価管理
原価管理では、コスト削減に役立ちます。影響力の大きいAグループから改善を行なうことで、より効果的にコスト削減ができるでしょう。
生産のレイアウト変更も、人件費や電気代の節約になります。
利益率分析と連携すれば、より利益を高めることも可能です。ムダのない生産によって「儲かる構成」を作ることができます。
まとめ:PQ分析で重点管理を効率化
PQ分析とは、重点製品を判別するための方法です。生産品目と生産量をまとめ、生産量が多い順に並び変えることで、どの製品が重点製品なのかを見極めることができます。
重点製品がわかれば、重点製品を中心とした販売戦略が可能です。より売れる商品を生産・販売することで、企業の利益にできるでしょう。
PQ分析やABC分析を活用し、より効率的で戦略的な生産管理・重点管理を実現していきましょう。