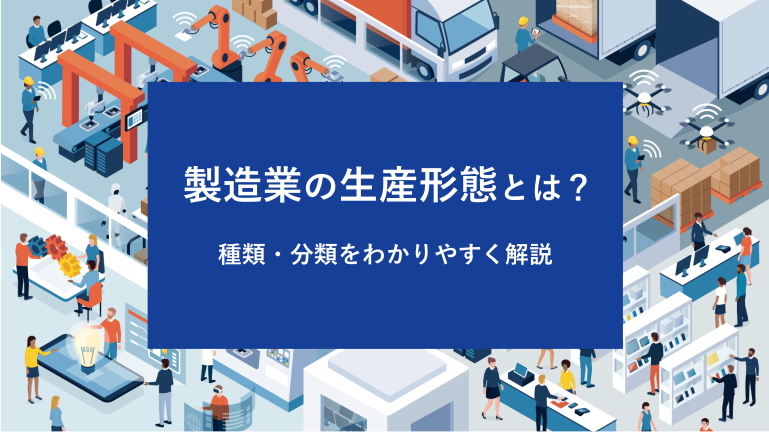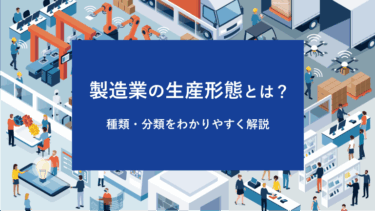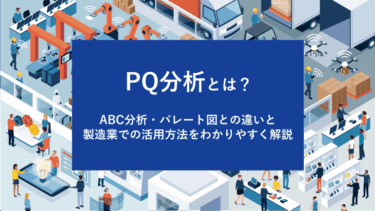製品を生産する方法には「受注生産」「ライン生産」など、さまざまな形態があります。
どの形態でも生産自体は可能ですが、方式によって作業効率やコスト、柔軟性は大きく変わります。効率的な生産を実現するには、それぞれの生産形態の特徴を理解しておくことが重要です。
生産形態にはどのような分類があるのか。分類やそれぞれの特徴を紹介します。
生産形態とは?
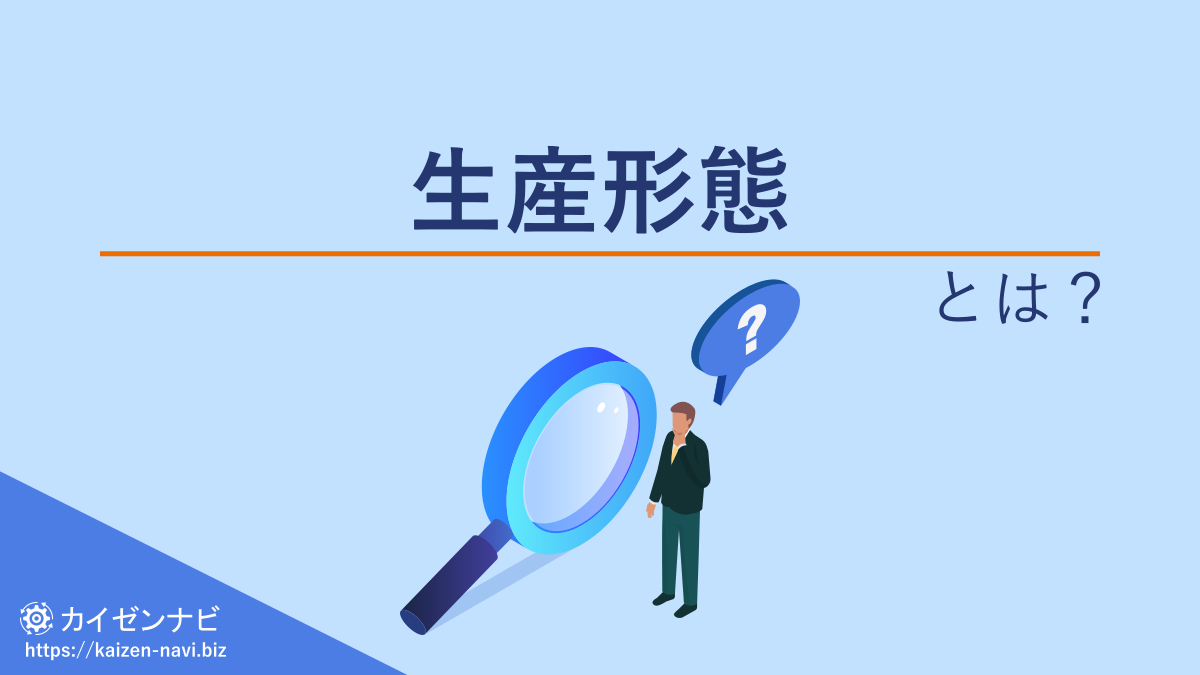
生産形態とは、生産のスタイルを指します。同じ製品を作るにしても、人数や設備の配置などによって生産のやりやすさなどが異なります。効率的に生産するには、目的や状況に応じて形態を選ぶ必要があります。
例えば、一つ10万円もするような製品を販売するとします。たくさん利益を出すためにはたくさん作る必要がありますが、金額が高いことから売れ残るのが心配です。
そのような売れ残る心配がある場合は、製品を先に作ってから売る(見込生産)のではなく、注文を確定してから生産を始める(受注生産)と良いです。注文に紐づけて生産するため、完成品在庫のリスクを大幅に低減できます。
以上のように、生産時期を変えるだけで不良在庫となる可能性は大きく変わってきます。ほかにも、加工設備や作業員の配置を変えるだけで作業効率が変わるなど、生産のやり方は一つだけではありません。
単一の生産方法にこだわるだけでは、場合によって損をしてしまいます。損をせず利益にするためにも、生産形態の特徴を理解し、正しく選択できるようにしてください。
生産時期による分類
生産時期による分類とは、生産を行なうタイミングで判断する分類です。受注をしてから生産をするのか、それとも生産をしてから販売するのかによって分類ができます。
- 受注生産:注文を受けてから、注文数に合わせて生産をする
- 見込生産:データを基に需要を予測して生産をする
などの分類があります。
受注生産は、注文を受けた後に生産を始める形態です。製品在庫を持たないことが特徴であり、不良在庫を抱える心配がありません。顧客ごとに仕様を変えることも可能であり、特別感のある製品を提供できます。
見込生産は、需要予測にもとづき在庫として先行生産する戦略で、結果として量産に採用されることが多い方式です。市場や過去のデータを基に生産数を決めて生産を行ないます。先に製品を作っているため、必要な時にすぐ販売できるのが特徴です。充分な量を用意しておけば、多くの人に製品を提供できます。
一般的には、高額な一点ものを生産する場合は受注生産、安価な消耗品などを生産する場合は見込生産が適しています。
生産方式による分類
生産方式による分類とは、生産のやり方で判断する分類です。職人が最後まで手掛けるのか、それとも大人数による流れ作業を行なうのかによって分類ができます。
- 個別生産:職人が始めから最後まで手がけて生産をする
- バッチ生産:ロットごとに区切って流れ作業を行なう
- 連続生産:原料や加工品を流し続け継続的に生産をする
などの分類があります。
個別生産は、始めから最後まで一つの製品を手がける生産形態です。一つの製品を最後まで手がけるため、柔軟に顧客の要望に応えられます。小規模な生産になることで、一点ものの対応に向いています。
バッチ生産(ロット生産)は、製品をロット単位で生産する生産形態です。一定の数量をまとめて生産し、完了してから次の生産に移行します。さまざまな製品を規定量生産するのに向いており、必要な量をまとめて生産できます。
連続生産は、原料の投入から完成までを継続的に続ける生産形態です。バッチ生産のように一定数で区切るのではなく、就業時間中は常に動かし生産を続けます。製造を流れ作業とすることで、安定した大量生産が可能です。
典型的な傾向として、一点ものは個別生産、まとまった量が必要な場合はバッチ生産、需要が高い場合は連続生産が選ばれます。
設備レイアウトによる分類
設備レイアウトによる分類とは、加工機の配置で判断する分類です。似た動作の機械をまとめて置くか、それとも工程の動線に合わせて置くかによって分類ができます。
- ジョブショップ型:似た機能を持つ機械や設備をまとめて配置する
- フローショップ型:生産工程の流れに合わせて配置する
ジョブショップ型は、同じ種類の作業を行う機械をまとめて配置し、各注文が個別に異なる工程順序をたどることを前提とした方式です。
フローショップ型は、生産工程の順序が一定で、各製品が同じ流れをたどる方式で、機械を工程順に直列配置します。
よく見られる使い分けとして、多品種少量生産ではジョブショップ型、少品種多量生産ではフローショップ型が選ばれることが多いです。
作業者と工程による分類
作業者と工程による分類とは、担当する工程範囲で判断する分類です。少人数で複数の工程を担当するか、それとも大人数で少ない工程を担当するかによって分類ができます。
- セル生産方式:一人または少人数で多工程を担当する
- ライン生産方式:工程を分担し流れ作業で生産を進める
- ダイナミックセル生産:セル生産とライン生産を合わせた形態であり、セル単位でライン生産を行なう
セル生産方式は、少人数のグループで作業を分担し、グループ内で完結させる形態です。少人数での生産は融通が聞きやすく、顧客ニーズに対して柔軟に対応がしやすいです。
ライン生産方式は、大人数で作業をする生産形態です。各作業員が担当する作業を細かく分担し、流れ作業で担当作業を行なっていきます。作業範囲が狭いため、少し教えるだけで即戦力にできるのが特徴です。流れ作業ができることから大量生産とも相性が良く、安定した大量生産が可能です。
ダイナミックセル生産は、セル単位でライン生産を行なう生産形態です。グループで工程作業を行ない、完成したら次のグループに生産を引き渡します。セル生産とライン生産の特性を兼ね備えており、効率よく量産できます。
また、ダイナミックセル生産は部分的な変更もしやすいです。車の生産をする際、ボディの生産を担当するセルだけを新しくすることで、ほかの仕様を変えずにリニューアルできます。大部分の仕様を変更せずリニューアルできるため、現場の混乱を最小限にできるでしょう。
用途別に見ると、多品種少量生産にはセル生産方式、少品種多量生産にはライン生産方式、柔軟な製品展開にはダイナミックセル生産が向いています。
品種と生産量による分類
品種と生産量による分類とは、品種と生産量のバランスで判断する分類です。多品種を少量ずつ生産をするか、それとも小品種を大量生産するかによって分類ができます。
- 多品種少量生産:たくさんの品種を少しずつ生産をする
- 中品種中量生産:品種と生産数のバランスを取って生産をする
- 少品種多量生産:少しの品種をたくさん生産をする
多品種少量生産は、さまざまな製品を少量ずつ生産する生産形態です。近年は顧客ニーズの変化が激しく、同じ製品ばかりでは対応しきれなくなっています。さまざまなニーズに応えるため、近年望まれている生産形態といえるでしょう。
中品種中量生産は、品種と生産数のバランスを意識した生産形態です。多品種少量生産と少品種多量生産の間となる形態であり、それぞれのメリットとデメリットを併せ持ちます。
少品種多量生産は、決まった製品を大量に生産する生産形態です。同じ製品を作り続けるため効率的に生産がしやすく、生産のコストを抑えることができます。
ケース別に考えると、新商品や特注品は多品種少量生産、定番商品は少品種多量生産が適しています。
工程への指示による分類
工程への指示による分類とは、工程間をつなぐ指示のやり方で判断する分類です。前工程が主導となって生産数を決めるのか、それとも後工程から指示によって生産数を決めるのかで分類ができます。
- Push型(プッシュ型):計画に基づき前倒しで工程を投入する
- Push/Pull型:PushとPull型の両立を目指した生産方法
- Pull型(プル型):需要に応じて後工程が前工程に引き取る
Push型は、事前に作って置いた在庫の中から後工程に渡す生産形態です。需要予測に基づいて生産を行ない、在庫としてストックしておきます。在庫が既にあるため、生産計画が急に変更しても対応がしやすいです。
Push/Pull型は、Push型とPull型を組み合わせて柔軟性を高めた生産形態です。例えば、家電メーカーでは標準部品をPush型で計画的に在庫し、モデルごとに異なる部品はPull型で需要に合わせて供給します。これにより、リードタイムを短縮しながら、市場の変動にも対応できます。
Pull型は、後工程からの指示によって生産を決める生産形態です。後工程から「加工品Aが5つ必要」との指示がされたら、加工品Aを5つだけ生産をして後工程に渡します。決められた量だけを生産するため、過剰在庫となる心配がなくコストを抑えることができます。
一般的な選択基準として、大量・定常需要にはPush型が採られやすく、需要変動対応や在庫削減にはPull型が有効とされます。
生産形態と生産管理システムの関係
生産形態には、さまざまな形態が存在しています。「生産時期による分類」や「生産方式による分類」といった生産についてのやり方だけではなく、「設備レイアウトによる分類」といった環境で分けることも可能です。生産をする際は、目的に合わせて生産形態を選ぶと、効率的に生産を行なうことができます。
しかし、生産形態は分類が多く、目的に合わせて選ぶのは難しいです。 生産形態ごとに必要な管理機能も違うため、複数の形態を採用することで現場を混乱させてしまうでしょう。
そのため、生産形態を使い分ける場合は生産管理システムを導入するのがおすすめです。生産状況などを一元管理することで、現場が混乱するのを防ぐことができます。生産計画も管理されるため、効率よく生産が進められるでしょう。
また、システムの導入が課題解決につながるケースもあります。工場の見える化によるボトルネックの発見や各号機の稼働率の比較など、システムで管理するからこそわかる問題点も多いです。問題点がわかれば対応もしやすく、生産率が大きく向上します。
こうした多様な生産形態を効率的に管理するためには、DX推進の一環として生産管理システムの導入が求められています。近年はDXへの推進が世界的に行なわれており、日本の工場も例外ではありません。グローバル化による市場変動に対応するために、生産管理システムの導入が求められます。
まとめ:生産形態を理解することが現場改善とDXの第一歩
生産形態とは、生産を行なうための方法や仕組みを指します。受注生産やライン生産など、どの形態にもメリットとデメリットがあり、製品や市場環境によって最適解は異なります。
重要なのは「自社の製品・顧客ニーズに合った形態を選択すること」です。生産形態を見直すことで、在庫削減や生産効率の改善といった課題解決につながるケースも少なくありません。
さらに、生産管理システムを導入することで、複数の生産形態を組み合わせた運用もスムーズに行えます。生産状況の見える化や計画の最適化が進み、DX推進にも直結します。
変化の激しい市場環境に対応するためにも、固定観念にとらわれず、自社に最適な生産形態を検討してみてください。