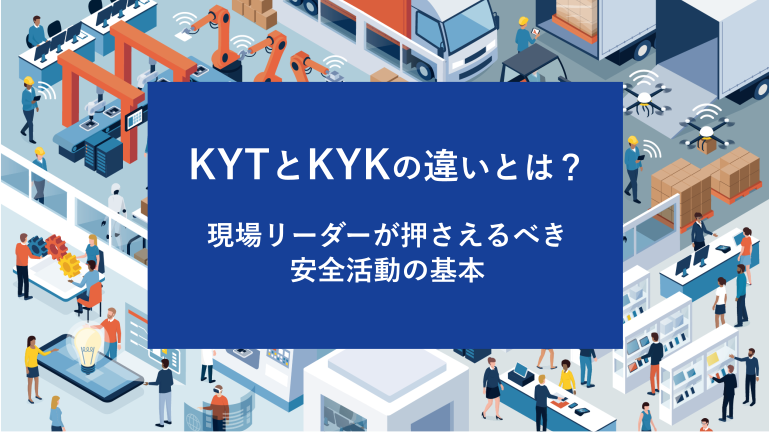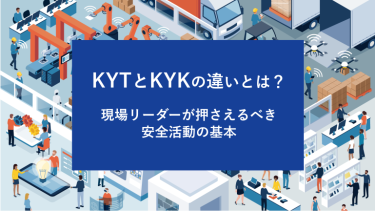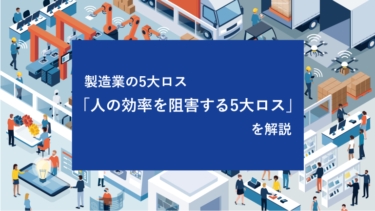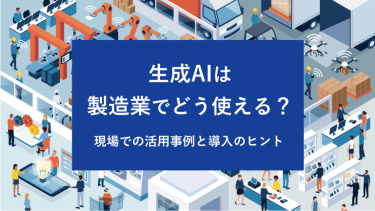作業員の安全を守る安全管理。労災の予防や処置を目的とした管理のことであり、安全に作業ができるよう、現場や職場環境を整えます。
安全基準は、働くうえで重要となる要素です。『きつい・汚い・危険』の3Kという言葉の中に、「危険」があるように、安全かどうかは、従業員のモチベーションに大きく影響を与えるでしょう。
そんな安全管理の一環として、KYTとKYKが存在します。どちらも作業員の安全を目的としたものではありますが、それぞれ内容や目的は違ってきます。安全管理を正しく行なうためにも、KYTとKYKの違いについて知っておく必要があります。
KYTとKYKは何が違うのか。現場リーダーの心得など、KY活動について紹介します。
KYT(危険予知訓練)とは?
KYTとは、危険予知トレーニングのことです。「危険(K)」「予知(Y)」「トレーニング(T)」の頭文字をとって、KYTと呼ばれます。
KYTの主な目的は、危険予知能力や問題解決力を高めることです。事前に研究室や事務所で現場の様子を確認してもらい、その状況から危険を予測し指摘し合うことで、働き方や解決策を立案します。
KYTの実施により、事故の回避や事故が生じた際の対処法が身につきます。勉強と同じで、あらかじめ対処方法がわかっていれば、焦ることなく対応できるでしょう。
また、初めて見るトラブルであっても、似たような事例を知っていれば、自分で考え行動することが可能です。訓練によってトラブルに慣れることで、落ち着いて行動ができるわけです。
危険は、防ごうと思っても完全に防げるものではありません。だからこそ、事前に訓練をし、回避や焦らず行動ができるようにしておく必要があります。
KYK(危険予知活動)とは?
KYTと似た言葉にKYKと呼ばれるものもあります。KYKとは危険予知活動のことです。「危険(K)」「予知(Y)」「活動(K)」の頭文字をとって、KYKと呼ばれます。
KYKの目的は、作業中に生じる危険を回避することです。危険や注意すべき箇所を作業前に確認をし、危険を自覚したうえで作業を始めるようにします。
KYKの実施により、事故になるのを未然に防げます。危険とわかっていれば注意して作業をしますので、リスク管理能力が高まるといえるでしょう。作業に慣れてしまった人も、改めて危険を確認をすることで、集中して作業をするようになります。
ヒューマンエラーをする原因の一つに「作業の慣れ」があります。作業に慣れていることで作業がおざなりとなり、その結果、ミスをしてしまうのです。
慣れによるミスを防ぐためにも、KYKによって気を引き締める必要があります。
KYTとKYKの違いを理解すべき理由
KYTとKYKは、どちらも危険を予知し対策をするための活動です。そのため、どちらも最終的な目標は同じといえるでしょう。
しかし、KYTはトレーニング、KYKは危険の確認といった明確な違いがあります。KYTは訓練によって危険を予防するのに対して、KYKは行動前に活動することで危険なことをしないための最終ブレーキを確認するわけです。
最終目標はどちらも同じですが、活動内容は異なります。当然、内容が異なれば運用方法も変わってくるでしょう。同じような活動に思えますが、実施内容は別物です。
活動を混同してしまうと、内容や目的が疎かになり、どちらも形骸化する恐れがあります。形骸化すると「なぜ必要なのか」が伝わらずに、活動の効果が得られません。
事故発生率の低下や若手の安全意識向上効果を期待するためにも、正しく使い分け、危険に対して取り組む必要があります。
KYTとKYKの実施タイミングの違い
KYTとKYKは、どちらも実施するタイミングが異なります。KYTは事前に行なうのに対して、KYKは作業の直前です。
訓練は事前に行なわないと意味がありませんし、確認事項は直前の方が意識しやすく効果が高いです。
実施タイミングが異なることからも、KYTとKYKは区別して行なう必要があるでしょう。
KYTとKYKの実施形式の違い
KYTとKYKは、実施形式も異なります。
KYTは、問題点をチームで話し合って進めていきます。写真やイラストなどで状況を把握したあと、チーム全体で危険因子や対策を話し合い、目標設定をすることで危険回避を図ります。
一方で、KYKは個人主体で進めます。危険や重要な個所を指差し確認で把握し、危険を意識してから作業を進めるのです。チームで行なう場合も、リーダーが主体となって確認し、それに続く形で作業員たちが簡易確認を行なっていきます。
チームと個人の違いがあることからも、KYTとKYKは別の活動といえるでしょう。
KYTとKYKのそれぞれのメリットと注意点
KYTとKYKが別物であることから、実施による効果も変わってきます。それぞれのメリットや注意点も確認をしてみてください。
KYTのメリットと注意点
KYTを行なうメリットは、危険予知能力が高まることです。現場の様子を基にリスク管理を行なうことで、「どのような危険があるか」や「どのように対応すればいいのか」などがわかるようになります。危険への意識もチームで共有されるため、自分が気が付かなかった危険も、新たに知ることができるでしょう。
また、作業への意識も改善されます。危険は身近にあることに気が付くことで、ほかの状況でも危険に気がつけるようになります。作業員一人ひとりが危機管理できるようにもなり、リーダーの負担が軽くなることで、チーム全体の作業効率を高めることにもつながるのです。
注意点としては、活動に時間がかかることです。話し合いを中心に進めていきますので、すぐに結果は出ません。短時間で終わらせようとすると、話し合いも浅くなり、充分な効果は期待できないでしょう。
ほかにも、慣れてくると形骸化しやすいです。時間がかかることから効率よく進めようとしてしまい、パターンに当てはめることで変化に乏しくなります。
もちろん、定型的な方法もダメなわけではありませんが、考えることを放棄してしまうため、危機管理能力が育ちません。考える力を育てるためにも、メンバーの交代や条件付けなど、活動に変化を加えると良いでしょう。
KYKのメリットと注意点
KYKを行なうメリットは、すぐにリスク回避ができることです。直前だからこそ頭に残りやすく、効果的にリスク管理が行なえます。指差し確認程度なら簡単に行なえることから、習慣化もしやすいといえるでしょう。
また、ヒューマンエラー対策にもなります。活動によって手順の再確認にもなり、集中力が高まることでミスをしにくくなるのです。
注意点としては、流れ作業になりやすいことです。指差し確認も、慣れてしまうと流れで作業しがちです。意識していないと頭に残りにくく、確認していても危険を見逃してしまいます。
流れ作業にしないためにも、ダブルチェックを取り入れたり休憩を挟んだりなど、集中できるようにしましょう。
KYTを実施するリーダーの心得
KYTを実施する際、リーダー(司会)は進行に努めてください。作業員たちに任せっきりにしてしまうと、話し合いがまとまりません。中にはディスカッションが初めてな人もおり、どのように進めればいいのかわからない場合もあるでしょう。
テーマやシートなどを用意し、あらかじめ訓練計画を立てておくのはもちろん、間延びしそうなら討議時間を区切るなど、スムーズに進められるよう工夫をしてみてください。
また、リーダー自身もあらかじめ勉強しておくことが大切です。事前に考えを持っていれば、話し合いに付け足す形で、チームを育てることができます。テーマにしたい重要なポイントがある場合は、チームが気が付くよう、さりげなく誘導もしましょう。
作業者だけに目を向けるのではなく、環境や状況など、さまざまな角度から考えてみてください。
最後に、明るく楽しく進めることを意識します。強制的に嫌々活動をやらせても、活動内容は身につきません。
KYTはチームワークを高める効果も期待できますので、積極的に発言できるような、気楽な雰囲気も作っていきましょう。
KYTを実施するリーダーの心得
- あらかじめ計画を立てて、間延びしないよう進める
- 内容が脱線したり急ぎ過ぎている場合は、流れを修正する
- 自分でも勉強し、話し合いのポイントを決めておく
- 明るく、元気に、楽しく活動を行なう
まとめ:KYTとKYKの違いを整理
KYTとKYKの違いは、予習か確認かの違いです。KYTは事前に勉強会を開いて危機管理能力を育てるのに対して、KYKは直前に最終確認をして気を引き締めます。
また、実施タイミングや実施形式も異なり、同じKYを持つ活動であっても別の活動といえるでしょう。
| 比較項目 | KYT(危険予知訓練) | KYK(危険予知活動) |
| フルネーム | 危険予知訓練/危険予知トレーニング | 危険予知活動 |
| 実施タイミング | 作業前の打ち合わせなど | 作業直前 |
| 実施形式 | グループディスカッション中心 | 個人 or チームで簡易確認 |
| メリット | 危険意識の共有・教育効果 | 習慣化しやすい・即効性 |
| 注意点 | 形骸化しやすい・時間がかかる | 流れ作業化しやすい |
とはいえ、どちらも作業員の安全を守るための活動であることには変わりありません。安全な作業は、従業員のモチベーションが保たれるだけではなく、生産性も向上します。さらには、安全性の高さから離職率も低下し、人材確保にもつながっていきます。
労災がない安全な現場にするためにも、KYTとKYKを含めたKY活動を徹底してみてください。