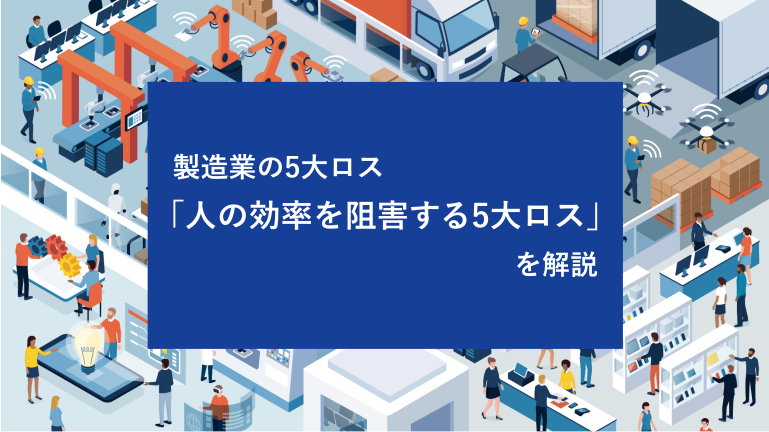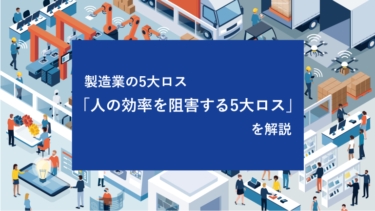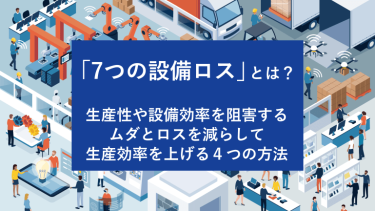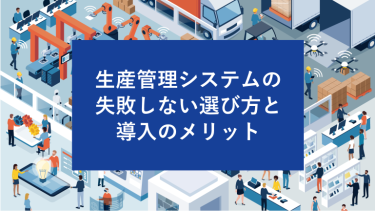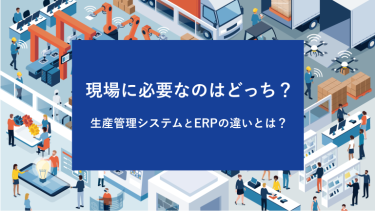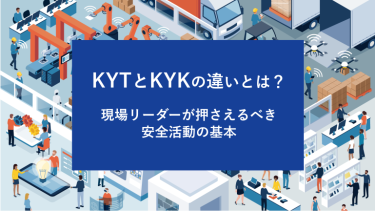企業の利益を損なう生産ロス。ロスの発生により、時間、資材、人材など、さまざまな生産コストを余計に消費することから、生産ロスの減少は製造における課題の一つとして挙げられています。
中でも、作業員の行動を阻害する要素のことを「人の効率を阻害するロス」と呼び、大きく5つに分けて考えることができます。作業効率や生産効率の向上を目指すためには、人の効率を阻害する5大ロスについて知っておく必要があるでしょう。
人の効率を阻害する5大ロスとはどのような生産ロスを指すのか。ロスを減らし生産効率を向上させる方法などと合わせて紹介します。
製造業における人の効率を阻害する5大ロスとは?
人の効率を阻害する5大ロスとは、ムダな行動によって時間や資材を消費させ、生産性の低下やコスト増大を招くロスのことです。「管理ロス」「動作ロス」「編成ロス」「自動化置換ロス」「測定調整ロス」の5項目が挙げられ、生産効率を低下させます。
生産効率が低下すれば、時間内に作れる製品が少なくなり、利益低下を招きます。さらに、納品も遅れることから、顧客からの信用も損ねてしまうでしょう。
ほかにも、ムダな作業は作業員の負担となり、作業員の不満や疲れを溜めてしまいます。
自社の利益向上だけではなく、作業員の負担を解消し気持ち良く働いてもらうためにも、ムダな行動は削減する必要があります。
人の効率を阻害する5大ロス
それぞれのロスがどのように影響するのか。以下の内容を確認してみてください。
管理ロス
管理ロスは、指示の段階で発生するロスのことです。「今日の配置を決めるために、作業員に待機してもらっている」「材料が到着するため、その場で待機している」といったように、作業員への指示ができていないことで発生します。
指示待ち状態でも、給料は発生します。成果が出ていないのに給料だけ支払うのは、管理者としては給料のムダといえるでしょう。別の指示ができていれば別の成果が得られていたと考えれば、人材や時間のムダにしています。
近年は、少子化の影響によって人材不足が懸念されています。せっかくの人材を遊ばせておくことがないよう、効率的な管理体制が求められるでしょう。
動作ロス
動作ロスは、作業中に発生するロスのことです。「製品を運ぶのに遠回りが必要」「道具が見つからず探す手間がかかる」といったように、動作が効率化されていないことで発生します。
動作に時間がかかると、その分、製造に時間がかかります。生産効率は低下し、利益を損ねる結果となるでしょう。
また、ムダな動作が多いことで作業員への負担も増加します。場合によっては、疲労や注意散漫から労災になる可能性もあります。
スムーズに作業を進めるためにも、作業動作を見直し、作業効率を高めることが大切です。
編成ロス
編成ロスは、ライン作業中に発生するロスのことです。「前工程が遅れて製品がこない」「人数が足りず作業が間に合っていない」といったように、一連の流れに問題があることで発生します。
待ち時間や作業の遅れがあれば、それだけ生産速度が遅くなります。生産数が低下するだけではなく、納品にも間に合わなくなるでしょう。
生産の流れをよどみなくするためにも、編成や配置を見直す必要があります。
自動化置換ロス
自動化置換ロスは、アナログ作業によって発生するロスのことです。「データを手入力する」「材料の運び入れを人力で行なう」といったように、作業をデジタル化せずに、アナログ作業をすることで発生します。
当然ですが、アナログよりもデジタルで作業をする方が効率的です。アナログでデータ入力をするよりも、デジタル技術によってデータが自動入力される方が、何倍も早く作業を完了します。デジタル技術でできることをアナログですることは、時間や人材のムダ使いといえるでしょう。
また、デジタルならヒューマンエラーの心配もなく、作業の信用性も高まります。作業員の負担も軽減できるなど、デジタル化によるメリットは多いです。
もちろん、導入による費用問題などもありますが、作業の効率化を目指すなら、デジタル化への移行がとても重要となります。
測定調整ロス
測定調整ロスは、過度な測定や調整によって発生するロスです。「同じ検査を3回行なう」「トリプルチェックを行なう」といったように、回数や頻度が多すぎることで発生します。
もちろん、検査や調整を複数回行なうのは正しいです。作業ミスや品質の低下を防ぐためには、念密な測定や調整を必要とします。しかし、回数が多いと、それだけ測定や調整に時間を取られてしまいます。その結果、品質は良いけど納期に間に合わない結果となるでしょう。
製造業においてQCD(品質、コスト、納期)が重要とされていますが、それぞれに相関関係があることから、バランスよく行なうことが大切と考えられています。
効率の良い生産を行なうためにも、測定や調整だけに時間をかけず、バランスよく工程を決める必要があります。
生産効率を阻害する16大ロス
製造の現場では、「人の効率を阻害する5大ロス」以外にも、ロスとなる要素がほかにもあります。生産効率を向上させるためにも、ほかのロスについても確認をしておいてください。
原単位の効率を阻害する3大ロス
原単位の効率を阻害するロスとは、コストの消費が大きくなる要素のことです。原単位とは生産をする際に必要となる原材料や時間などのことであり、効率を阻害することで余計に消費してしまいます。
原単位の効率化を阻害するロスには、以下の3つが挙げられます。
- 歩留まりロス
- エネルギーロス
- 型・治具ロス
歩留まりロスとは、加工時に発生するロスのことです。加工をする際にバリなどの不要な部分を切り取りますが、作業が雑だと余計に削ってしまい、資材をムダに捨ててしまいます。
エネルギーロスとは、設備を動かした際に発生するロスのことです。ムダに生産をして機械を長く稼働させることで、電気代や燃料代を余計に消費してしまいます。
型・治具ロスとは、治具の修理や制作した際に発生するロスのことです。ムダに修理や制作を繰り返すことで、金銭がたくさん消費されます。
原単位の効率を阻害するロスは、主に資金を浪費させます。企業の利益を増やすためにも、コストの出費を減らす必要があるでしょう。
設備効率を阻害する7つのロス
設備効率を阻害するロスとは、設備や機械の稼働を止めてしまう要素のことです。
設備効率を阻害するロスには、以下の7つが挙げられます。
- 故障ロス
- 段取り・調整ロス
- 刃具交換ロス
- 立上がりロス
- チョコ停・空転ロス
- 速度低下ロス
- 不良・手直しロス
故障ロスとは、設備や機械の故障時に発生するロスのことです。設備や機械が動かないことで生産ができず、時間をムダにしてしまいます。
段取り・調整ロスとは、段取りを進める際に発生するロスのことです。ロットの切り替えなどの段取りが遅くなることで、生産の流れを止めてしまいます。
刃具交換ロスとは、治具の交換時に発生するロスのことです。治具の交換やメンテナンスが遅くなることで、生産の流れを止めてしまいます。
立上がりロスとは、生産開始時に発生するロスのことです。機械の立ち上げに手間取り生産開始が遅れることで、時間をムダにしてしまいます。
チョコ停・空転ロスとは、小停止の積み重ねによって発生するロスのことです。たとえ数秒の停止であっても、回数が多いと大停止と変わらない時間、機械を止めてしまいます。
速度低下ロスとは、製造時に発生するロスのことです。機械の調子が悪いことで製造が遅くなり、生産を遅らせてしまいます。
不良・手直しロスとは、不良品が生じた際に発生するロスのことです。設備の調整や不良品の廃棄などの対応が必要となりますが、その対応によって、本来の生産業務を遅らせてしまいます。
設備効率を阻害するロスは、主に時間を浪費させます。生産の時間がなくなることで、生産効率を低下させます。また、生産が止まることによる作業員の手待ちや、機械の不調による品質低下といった問題も発生するでしょう。
生産数を増やすためにも、生産の流れを止めないようにする必要があります。
生産ロスとは、製造の際に生じる損失のことです。商品がムダになるのはもちろん、生産に使われた、資材、時間、人材、電気などがムダとなり、製造において避けるべきことの一つとして扱われています。 生産ロスはどのような場面で発生するのか[…]
シャットダウンロス
設備や機械をシャットダウンさせることも、ロスの発生につながります。機械を止めている際は生産も止まりますので、生産効率が低下するといえるでしょう。
立上がりロスと似たようなロスであり、生産効率を高めるためにも、メンテナンスなどを効率的に行ない、シャットダウン時間を短くすることが大切です。
また、シャットダウンロスも設備に関係することから、設備効率を阻害するロスに含めることもあります。
一方で、シャットダウンロスは意図的に止める、設備効率を阻害するは非意図的に止まることから別のロスとして考える場合もあり、評価する人によって意見が分かれます。
ロスを減らして生産効率を向上させる方法
生産ロスを減らすためにも、以下のことを意識して行なってみてください。
現状把握と原因の明確化
生産ロスを減らすためには、現状を正確に把握することが大切です。ロスの規模やロスが発生する場所、そもそも、ロスが発生していることを理解していないと、改善案を立案できません。
生産数やトラブルの原因などを確認して、ムダな行動や要素がないかを検討してみてください。
また、原因を明確にする際は、多角的に評価をすることも大切です。「新QC7つ道具」などの問題解決フレームワークを活用して、チーム全体で原因究明を目指してみてください。
5S活動の徹底
5S活動を徹底する方法もあります。5S活動とは「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ」からなる意識改革のことであり、実施することで現場が綺麗になり作業がしやすくなります。
たとえば、整頓をして物を探しやすくすれば、動作ロスを減らすことが可能です。普段から綺麗に清掃をしておけば、朝の清掃時間を短くでき、立上がりロスを減らすこともできるでしょう。
簡単なことだからすぐに実施がしやすく、低コストで生産ロス対策が始められます。
- 整理:不要なモノを処分し綺麗にすること
- 整頓:モノを片付け見やすく使いやすくすること
- 清掃:汚れを綺麗にし不備を改善すること
- 清潔:整理、整頓、清掃を続けていくこと
- しつけ:誰もが5Sを続けられるよう教えること
製造業でよく耳にする5S活動。現場環境を改善することで作業効率や生産性が向上することから、多くの企業が注目・取り入れています。 もちろん、5Sの考えは製造業だけではありません。医療業界、物流業、サービス業、小売業なども実施して[…]
TPM活動を取り入れる
TPM活動(Total Productive Maintenance)とは、生産現場全体で生産保全を行なう活動のことです。特定の人や部門だけで取り組むのではなく、生産に関わるすべての人や部門が協力して対策に取り組みます。
管理部門によって在庫不足を減らしたり、研究部門によって壊れにくく交換しやすい治具が提供されたりなど、他部門との協力によって生産効率がより高まります。
また、衛生部門による5Sの推進や営業部門によるマネジメントなど、普段は生産と関わらない部門も、活動によって生産に影響を与えます。
製造部門だけで取り組むのではなく、最終的には企業全体で対策に取り組むよう目指してください。
生産管理システムの導入
生産管理システムを導入することで、製造現場をまとめて管理できます。デジタル化によって自動化置換ロスが解消されるだけではなく、スケジュールや在庫管理をすることで、管理ロスや編成ロス対策にもなるでしょう。
ほかにも、機械の稼働状況を見える化することで、故障ロスやチョコ停・空転ロス対策にもなります。過去の生産数と比較することで速度低下ロスに気が付くなど、見えにくいロスも発見しやすいです。
生産管理システムの導入による効果は大きく、さまざまな形で生産ロスの削減を目指せます。
生産をサポートする生産管理システム。近年は工場のデジタル化が推進されており、生産管理システムを導入する企業も増えてきています。中には、生産管理システムの導入を、既に検討している企業もあるかもしれません。 ですが、生産管理システ[…]
まとめ:5大ロスを削減し、製造現場の生産性を向上させよう
製造現場では、さまざまな形で人の効率を阻害するロスが発生します。特に多いのが指示待ちによる人材や時間のロスであり、作業員が暇してしまうのは、管理者目線でもったいないといえるでしょう。
生産性を高めるためには、スムーズに作業を進められることが大切です。そのためにも、ムダな動作を減らし、効率よく作業できるよう改善する必要があります。
5S活動の徹底や生産管理システムの導入などを行ない、効率的で作業しやすい環境の構築を目指してみてください。