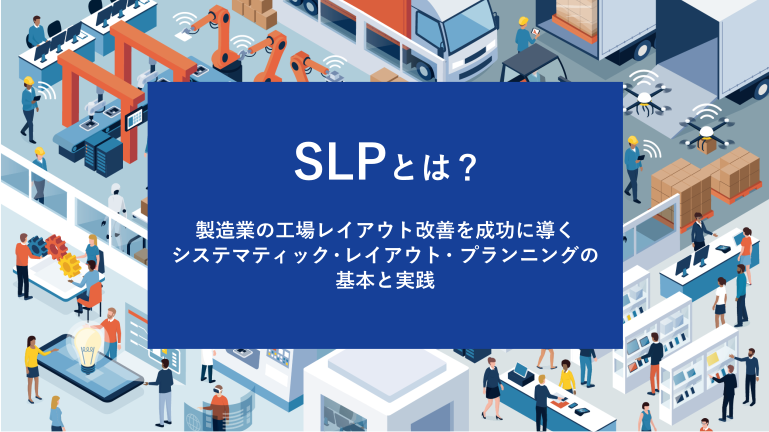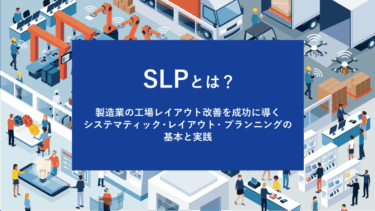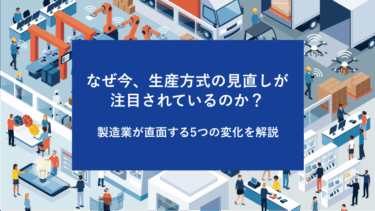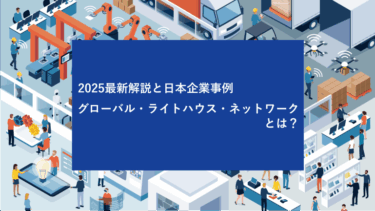工場のレイアウトは、作業効率の向上を目指すうえで重要な要素の一つです。配置によって作業しやすさが大きく変わり、生産性を高める切っ掛けとなります。また、行動のムダが無くなれば作業の負担も減り、労働者にとって働きやすい環境にもなるでしょう。
SLPは、そんな工場のレイアウトを決める際におすすめのフレームワークです。さまざまな要素を加味することで、効率の良いレイアウトが決められます。
工場に限らず、オフィスや倉庫など他の現場でも、配置換えは気軽にできるものではありません。配置換えで失敗しないためにも、綿密な計画と準備が必要です。
工場のレイアウト決めはどのように行なえばいいのか。SLPの基本や実践のコツなどについて紹介します。
SLP(システマティック・レイアウト・プランニング)とは?
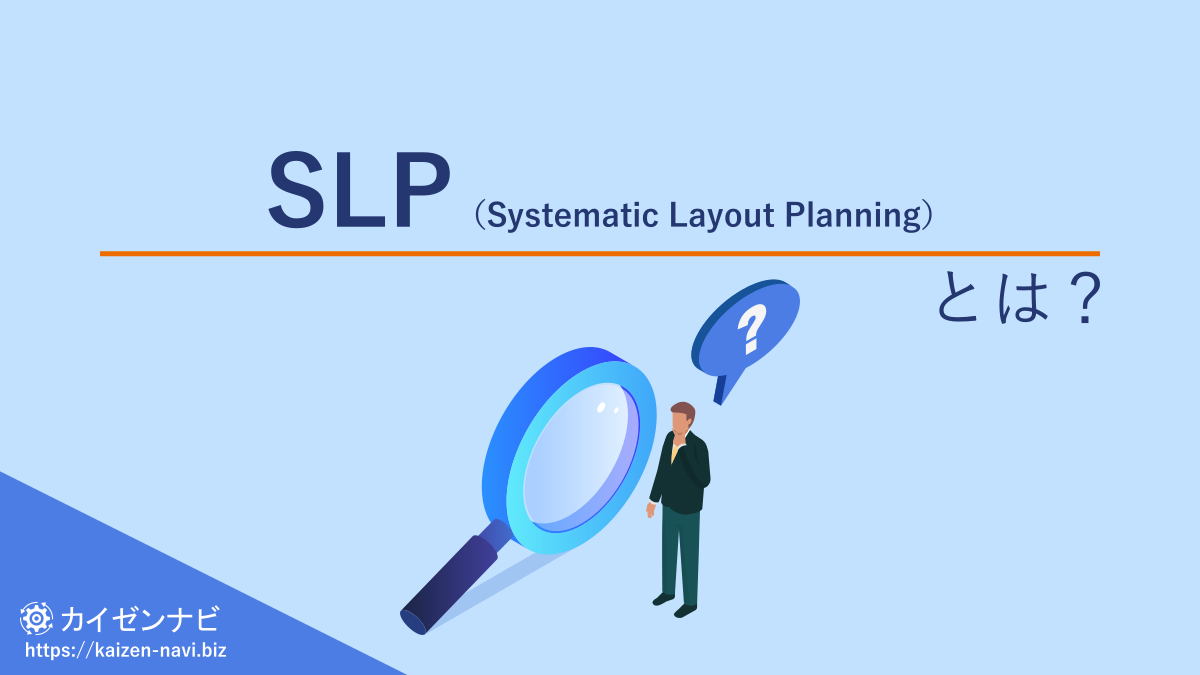
SLP(Systematic Layout Planning)とは、工場のレイアウトを決める体系的な手順のことです。1961年にアメリカのリチャード・ミューサーが提唱した手法であり、生産計画や物流計画などを基にしながら、設備や工具の配置を決めていきます。
工場のレイアウトは、ただ配置をすればいいわけではありません。設備や工具の配置によって、大きく作業効率が変わってくるからです。作業時間に影響があるのはもちろん、コストや事故の件数などにも影響するため、工場に合わせたレイアウトを検討する必要があります。
また、工場のような大きな施設だと、レイアウトの変更も一苦労です。簡単に変更ができないからこそ、レイアウト決めが重要になってきます。
生産をスムーズに行なうためにも、レイアウトの段階から意識することが大切です。
SLPの4つのステップ
SLPは、4つの段階を経て行なわれます。ステップに合わせて確認をしてみましょう。
データ収集・生産予測・PQ分析
まず始めに、データ収集から行ないます。生産項目、生産数、それぞれの生産コストなど、生産に関係するデータを用意してください。集まったデータを基にレイアウトを考慮するため、データが多いほど効率的なレイアウトを決めやすくなります。
また、将来的に増産や減産をする可能性もあります。配置を改めて変更するのは大変ですので、生産予測も考慮しておくといいでしょう。
データを集めたら、PQ分析も行ないます。PQ分析は生産項目と生産数から重点製品を調べるための手法であり、PQ分析によって「どの製品を優先すべきか」がわかります。
主力製品を生産の中心にするためにも、PQ分析は大切です。
工程・モノの流れ分析および関連性分析
製品の分析ができたら、次は工程や物流の流れを分析します。生産ラインを可視化することで、実際の流れをイメージしながら配置ができます。
チームで情報の共有もしやすくなりますので、全体の流れをまとめてみてください。
流れを整理する方法として、RELチャートとFrom-Toチャートがあります。RELチャートはモノの関連性を可視化するチャートであり、From-Toチャートは流れを整理するためのチャートです。
工程が多いほど流れを追いにくくなりますので、それぞれのフレームワークを用いて整理してみてください。
レイアウト案の作成(複数案展開)
製品と工程について整理できたら、データを基にレイアウトを決めていきます。「重点製品の生産は流れを一直線にして生産をしやすくする」「似た機能の設備はまとめてわかりやすくする」など、利便性と生産性の両方を踏まえて決めてみてください。
また、レイアウト案は複数用意するといいです。「コストを抑えた案」「動線を意識した案」「増設がしやすい案」など、特徴を変えた案も考慮してみましょう。
レイアウト案が完成したら、ほかの人に評価してもらいます。視点が変わることで、新しい発見が見つかるかもしれません。特に、実際に使用する現場の意見は大切です。現場に即した実用的なレイアウトにするためにも、必ず相談するようにしてください。
最適案の選定・実施・モニタリング
レイアウト案がまとまったら、次は最適案を決めていきます。どの案が最も自社工場に適しているかをチーム全体で決めてみてください。場合によっては、別の案のレイアウトも取り入れ、一つのレイアウトにまとめていきましょう。
レイアウトが決まったら、実際に取り入れてみます。いきなり全部を変更すると現場が混乱してしまいますので、「まずは一号機周りから」といったように段階を踏んで行なっていきます。
また、導入したら終わりではなく、導入した結果を評価します。もし、レイアウトに問題があるようなら、評価をまとめて修正をしてください。
時代が変われば、技術や作るものも変わってきます。定期的にレイアウトを見直し、時代や顧客ニーズに合わせたレイアウトを目指していきましょう。
SLPを活用するメリット
SLPを活用するメリットとしては、効果的な配置ができる点にあります。「重点製品を中心としたレイアウトにすることで重点製品の生産数を上げられる」といったように、データを用いることで客観的に評価ができます。
ほかにも、作業動線を短くすることによる作業効率の向上やコスト削減、設備をまとめることで新人でも配置が覚えやすくなる、作業環境を変えることによる品質の向上や安全性の向上など、レイアウト変更による効果はいろいろあります。
直感に頼った配置では、レイアウトによる効果はあまり期待できません。労働環境をより良くするためには、客観的に評価することが大切です。
また、SLPを活用することで、工場内を俯瞰視点で見ることもできます。From-Toチャートなどによって流れが可視化され、全体の流れを把握できるでしょう。俯瞰視点だからこそ気が付く要素も多く、新しい気が付きによって、より良い改善を目指せます。
SLPを実践する際の注意点・コツ
SLPを成功させるコツとして、以下のような点を意識してみてください。
データ収集と工程分析の精度を確保する
SLPを成功させるためには、データ収集がとても大切です。SLPはデータを基にレイアウトを決めるため、データの不足や不確定なデータが多いと正しい分析ができなくなります。
不確かな分析からは、正確な判断は得られません。誤った分析結果に基づくと、適切なレイアウト設計が難しくなります。間違った結果を参考にしたレイアウトによって、効率の低下やコストの増大などが生じる可能性もあります。
SLPの精度を高めるためにも、信用のおける最新のデータを用意するようにしてください。
部門横断の体制と現場巻き込みを徹底する
SLPを実施する際は、必ず製造現場も巻き込むようにしてください。実際に作業をするのは現場の人たちであり、現場の意見がとても重要になってきます。
たとえ理論上は効率が良くても、実際に作業をしてみると不具合が生じることはよくあります。現場を正しく知るためには、現場の意見が必要不可欠です。
また、ほかの部門とのつながりがある場合は、関係する部門との連携も必要です。ほかの部門との流れも意識することで、よりスムーズな生産が可能となります。
より良いレイアウトを目指すためにも、さまざまな意見を取り入れましょう。
現在だけに最適化せず、将来変化に耐える柔軟性を設計に組み込む
レイアウトを決める際は、将来性も意識してください。今を基準に設計してしまうと、スペースの余裕が無くなり増設が難しくなります。
今は予定がなくとも、将来的にどうなるかはわかりません。近年は市場や技術の変化が激しい時代であり、将来的に生産ラインを変更することもあるでしょう。
将来に備えて、レイアウトにある程度余裕を持たせることが大切です。
安全性・作業環境を犠牲にしない効率追求
レイアウトを決める際は、安全性も意識してください。効率を求め過ぎると、安全性を無視してしまうことがよくあります。
たとえ生産効率が良くても、労災が発生してしまえば生産は止まってしまいます。不良品の発生や補償金の支払いなども生じてしまい、レイアウトしたことが企業への負担となってしまうでしょう。
また、危険な職場には人が寄り付きません。離職率も高まり、人手不足が加速します。
効率だけを求める職場は、将来的に自分たちの首を絞める結果となります。従業員のモチベーションを高めるためにも、従業員のことも考えた労働環境にすることが大切です。
投資対効果(ROI)を明確にして現実的な計画に落とし込む
SLPを導入する際は、投資対効果を意識してください。いくら効率的かつ安全性の高いレイアウトが決まっても、導入コストが膨大だと実現は難しいです。
レイアウトを意識するあまり、企業の負担となってしまっては配置換えをした意味がありません。初期コストを抑えるのはもちろん、将来的にコストを回収できるよう慎重に検討しましょう。
デジタルツールを活用したSLPの進化
SLPを実施する際は、デジタルツールを活用するとより効果的に作業ができます。どのようなデジタルツールが使えるのか確認してみましょう。
シミュレーションツールによるレイアウト検証
シミュレーションツールを使えば、実際に配置換えをする前にレイアウトの確認が可能です。現実世界での配置換えはとても大変ですが、デジタル世界でなら配置換えも容易であり、さまざまなレイアウト検証が行なえます。
3Dモデルを作れるシミュレーションツールなら、よりリアルに現場をイメージできます。正確な情報共有が可能となることで、配置換え後のトラブルが少なくなるでしょう。
配置換え後に「こんなはずでは」とならないよう、まずはデジタル世界でシミュレーションをすることをおすすめします。
デジタルツイン/仮想工場によるSLPの高度化
デジタルツインとは、デジタル世界に現実世界を投影するデジタル技術のことです。現実世界をデジタル世界に再現することで、現実世界では難しい検証も、デジタル世界でシミュレーションできるようになります。
レイアウトのシミュレーションをするのはもちろん、全体の流れを把握しSLPの分析に活かす意味でも、デジタルツインの活用は効果的です。
SLPとDX・AIの融合
工場のDX化により、SLPの実施も進化しつつあります。DXとはデジタル技術を用いてビジネスモデルの変革を目指す取り組みであり、SLPの実施にもIoTやAIといったデジタル技術が取り入れられています。
例えば、上記で紹介したデジタルツインのリアルタイム化です。IoTで得た情報をAIが処理することで、リアルタイムに工場内の様子を再現することができます。全体の流れを把握できるようになり、より正確な生産管理が行えるでしょう。
また、AIを活用すれば、ビッグデータを基にしたレイアウト設計も可能となります。ビッグデータに含まれる生産データや作業データをAIが収集・分析することで、より緻密な配置ができるのです。設備の耐用年数や市場データから予測し、改修や増築を前提としたレイアウト設計もできるでしょう。
SLPの作業効率を向上させるためにも、ぜひデジタルツールの活用を考慮してみてください。
まとめ:SLPで“ムダのない工場づくり”を実現しよう
SLPとは、効率的に工場のレイアウトを決める手段のことです。収集したデータを基に工場レイアウトを決めることで、生産効率の高い配置を実現できます。
工場のレイアウト決めは、生産性に大きく影響をします。使いやすい並びにすれば作業の手間が減りますし、ムダを省くことでコスト削減にもなるからです。ほかにも、従業員の負担が減ることで、モチベーションを高めることにもつながるでしょう。
作業効率を向上させる方法は、工程を改善することだけではありません。作業をしやすいよう環境を整えることも重要になってきます。
作業を効率よく進めるためにも、SLPを用いてムダのない工場づくりを目指してみてください。