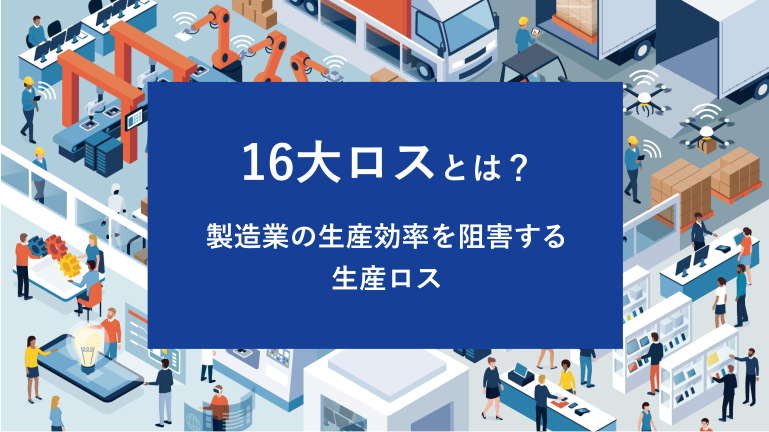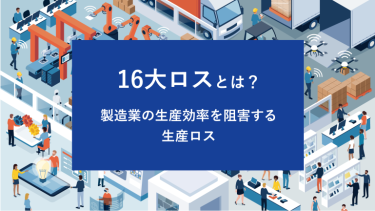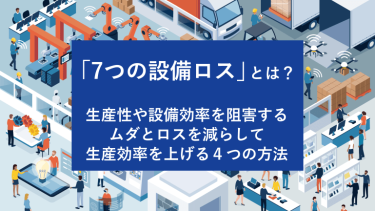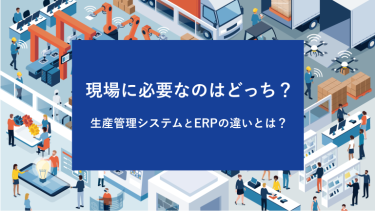製造現場において、生産ロスは解決すべき課題の一つです。生産ロスはコストを増大させるだけではなく、生産効率を下げることで利益の低下を招いてしまいます。
また、ロスの種類によっては、品質の低下や納期の遅れも誘発させてしまいます。企業の信頼を損ねないためにも、生産ロスは最小限に抑える必要があるでしょう。
生産ロスはどのように対応すれば良いのか。16大ロスについて紹介します。
生産ロスとは?

生産ロスとは、製造した際に生じる損失のことです。時間、資材、人材、光熱費など、不要な要素があったことで、リソースを余計に費やしてしまいます。
もちろん、製品が不良品の場合は、製品自体もロスとなります。たとえ製品自体に問題がなくても、過剰在庫であればムダになってしまうでしょう。
生産ロスが生じると、生産コストが余計にかかってしまいます。そのため、利益効率を高めるためには、生産ロスを把握し減らしていくことが大切です。
16大ロスとは?
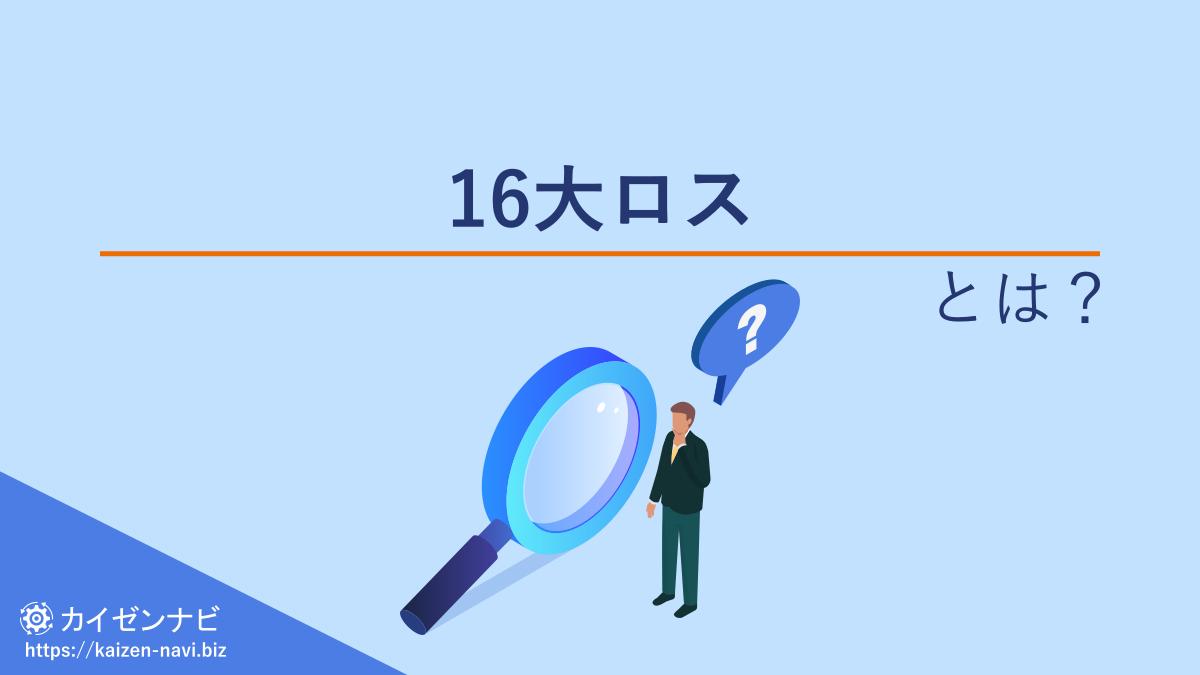
16大ロスとは、生産の効率化を阻害する16種類のロスのことです。大まかな分類として、「操業度を阻害するシャットダウンロス」「原単位の効率化を阻害するロス」「人の作業を阻害するロス」「設備効率を阻害するロス」に分けることができ、それぞれの分類ごとに、複数のロスが隠れています。
ロスは、ただ闇雲に探しても見つかりません。多くの場合、ロスを含んだやり方が定着しており、当たり前と思うことで、ロスを見落としてしまいます。
ロスを探す際は、今までの定義を見直し、それぞれの観点でムダを探す必要があります。そのためにも、どのようなロスが考えられるのか。また、何を阻害するロスなのかを知っておく必要があるでしょう。
16大ロスの分類
16大ロスは、それぞれ以下のように分類できます。それぞれ関係するロスと合わせて確認をしてみてください。
操業度を阻害するシャットダウンロス
シャットダウンロスは、メンテナンス時に生じるロスのことです。清掃や点検、部品交換など、準備作業中は生産ができないことから、製造する機会のロスとなります。
とはいえ、安全に作業するためにはメンテナンスが必要です。清掃や点検を行うことで、作業効率の向上や品質管理にもつながります。
機会のロスではありますが、生産をするうえで必要なロスでもあるわけです。そのことから、ほかのロスとは別に扱われることも多いです。
原単位の効率化を阻害する3大ロス
原単位とは、生産をする際に必要となる原材料や時間などのことです。原単位が小さいほど、生産のリソースが少なく、効率よく生産ができていることを意味します。
原単位の効率化を阻害するロスには、以下の3つが挙げられます。
- 歩留まりロス
- エネルギーロス
- 型・治具ロス
歩留まりロスは、使用した資材の重量と製品重量に差が生じた際に起きるロスです。加工する際にバリなどを削りますが、削る量が多いと、それだけ資材を捨ててしまっています。
エネルギーロスは、電気や燃料を余計に使用した際に生じるロスです。ムダな生産が多いとエネルギー消費が多くなり、電気代などが余計にかかってしまいます。
型・治具ロスは、不要な治具を作成した際に生じるロスです。使わない治具の制作や酷使することで修理が必要になると、その分の時間と費用がかかってしまいます。
コストの削減は、利益向上につながります。企業の利益を増やすためにも、ロスを削減する必要があるでしょう。
人の作業を阻害する5大ロス
人の作業を阻害するロスには、以下の5つが挙げられます。
- 管理ロス
- 動作ロス
- 編成ロス
- 自動化置換ロス
- 測定調整ロス
管理ロスとは、指示待ちや修理待ちした場合に発生するロスです。作業がないことで、人材をムダに持て余してしまいます。
動作ロスとは、作業にムダがある場合に発生するロスです。移動や道具探しなどで時間がかかると、作業効率が悪くなります。
編成ロスとは、ラインの流れが悪い場合に発生するロスです。人員配置やスケジュールに問題があると、ボトルネックなどのトラブルが発生し、生産を遅らせてしまいます。
自動化置換ロスとは、アナログ作業に時間がかかる場合に発生するロスです。データの入力や集計など、デジタル化できていないことで、作業に時間がかかってしまいます。
測定調整ロスとは、過剰に検査や測定を繰り返した場合に発生するロスです。慎重なのは大切ですが、回数が多いと工程が増えてしまい、生産性が落ちてしまいます。
効率よく作業が行えるようになれば、生産性が向上します。。より多くの製品を仕上げ、納期に間に合わせるためにも、ロスを削減する必要があるでしょう。
設備効率を阻害する7つのロス
設備効率を阻害するロスには、以下の7つが挙げられます。
- 故障ロス
- 段取り・調整ロス
- 刃具交換ロス
- 立上がりロス
- チョコ停・空転ロス
- 速度低下ロス
- 不良・手直しロス
故障ロスとは、設備が故障することによって発生するロスです。修理費用がかかるだけではなく、修理中は設備が使えないことで、生産を止めてしまいます。
段取り・調整ロスとは、製品の切り替えが遅いことで発生するロスです。ラインを切り替える際には指示書の確認や設定の変更などが必要ですが、切り替え中は生産を止めてしまいます。
刃具交換ロスとは、治具の交換が遅いことで発生するロスです。設定の変更や摩耗した際は新しい治具に交換する必要があり、交換中は生産を止めてしまいます。
立上がりロスとは、生産開始が遅いことで発生するロスです。立ち上がりが遅いと生産が始められず、生産数を落とす結果となります。
チョコ停・空転ロスとは、ちょっとした停止が積み重なって発生するロスです。たとえわずかな停止であっても、回数が増えれば大きな停止と同じになり、生産数を落としてしまいます。
速度低下ロスとは、本来よりも生産が遅いことで発生するロスです。設備の不調などによって生産スピードが落ちてしまい、生産数を落としてしまいます。
不良・手直しロスとは、不良品の対応をすることで発生するロスです。設備の修理や検査のやり直しなど、作業が増えることでリソースを割いてしまいます。
設備に問題があると、修理費用がかかります。生産ができないことで、手待ち時間も発生してしまうでしょう。生産数を落とす原因になることからロスを削減する必要があります。
また、シャットダウンも設備に関係することから、「シャットダウンロス」も加え、8大ロスとする場合もあります。
ただ、7大ロスは設備自体の問題、シャットダウンロスは人が操作することから、別として考えることも多いです。
生産ロスとは、製造の際に生じる損失のことです。商品がムダになるのはもちろん、生産に使われた、資材、時間、人材、電気などがムダとなり、製造において避けるべきことの一つとして扱われています。 生産ロスはどのような場面で発生するのか[…]
生産ロスの見つけ方
生産ロスは、以下の流れに沿って探すと、効率よく見つけることができます。実際に探す際の参考にしてみてください。
生産ロスの定義を見直す
まずは、生産ロス定義から見直してみると良いです。どのようなことが生産ロスなのかがわからないと、効果的に削減できません。場合によっては、効率を重視するあまり、安全性や信用を損ねる結果にもなります。
16大ロスを参考に、どのようなことがロスといえるのかを確認しておきましょう。
また、全体から一度に探すのではなく、それぞれの分類ごとに探すと良いです。全体を見て評価すると、見るべき部分が多いことから見逃しやすくなります。それぞれを分けて考えてみてください。
生産性を下げるムダな作業を洗い出す
ロスの定義ができたら、実際にロスを探してみます。実際の流れをイメージしながら、ムダと思った部分を洗い出してください。
とはいえ、初めてだと評価するのが難しいと思います。設備効率を阻害するロスは7種類もあり、それぞれで評価するのは大変です。
そのため、慣れないうちは「やり直す」「迷う」「モノを探す」「手待ち」の4項目で評価すると良いです。ロスといえる要素は16種類ありますが、突き詰めると4つの要素にまとめられます。
「やり直す」とは、同じ作業を繰り返すことです。「作業が重複している」「確認回数が多い」「動線の行き来が多い」など、同じことを繰り返していることでムダが生じます。
「迷う」とは、判断に時間がかかることです。「手順が多い」「確認のために上司を探す必要がある」「連絡手段が決まっていない」など、定まっていないことで時間がかかりムダが生じます。
「モノを探す」とは、見つからないことです。「モノが多い」「分類されていない」「行方がわからない」など、準備に手間取り時間がかかることでムダが生じます。
「手待ち」とは、暇ができていることです。「準備が遅い」「使用に順番待ちがある」「ラインに詰まりがある」など、待ち時間があることでムダが生じます。
もちろん、4要素では細かく洗い出すのは難しいですが、4要素だけでも大部分を洗い出すことができるでしょう。ロス探しに慣れてきたら、16大ロスを基準に探してみてください。
目で見て見えない生産ロスも把握する
目に見えるロスだけではなく、目に見えないロスを意識することも大切です。見えない生産ロスとは、ロスが発生しているが気が付かないロスのことであり、主に歩留まりロス、チョコ停止、速度低下ロスなどが挙げられます。
管理ロスや故障ロスは、ロスが生じているのが一目でわかります。作業員が手待ちをしていることから、人材がもったいないとすぐに気が付くはずです。
しかし、歩留まりロスや速度低下ロスといったロスは、測定や比較をして初めてわかるロスです。一目でわからないことで、ロスが発生していても気が付かないでしょう。
実際に目で見て評価するのも大切ですが、見えないロスもあることを忘れてはいけません。ロス対策をする際は、生産数や生産スピードなど、さまざまな情報を見える化し、そのうえで評価することが大切です。
まとめ:削減できる生産ロスを見極めて生産効率アップを目指す
16大ロスとは、生産におけるロスの分類のことです。「シャットダウン中に発生するロス」「コストの使い過ぎで発生するロス」「人が原因で発生するロス」「設備が原因で発生するロス」によって、コストの増大や作業効率の低下といったムダが生じてしまいます。
生産効率向上や利益向上を目指すためには、削減できる生産ロスを見極め、一つずつ対応していくことが大切です。
また、ムダを削減する方法としてデジタル化も有効です。リアルタイムに生産を管理することで、生産のムダを迅速に見つけられます。システムサポートによって、従来のアナログ作業が大幅に短縮されるでしょう。
生産ロスへの活用だけではなく、工程管理や製造の自動化も実施できます。情報化社会といわれる近年、多くの企業が工場のDXを目指しています。より効率的な生産を目指すためにも、デジタル技術の導入を検討してみてください。