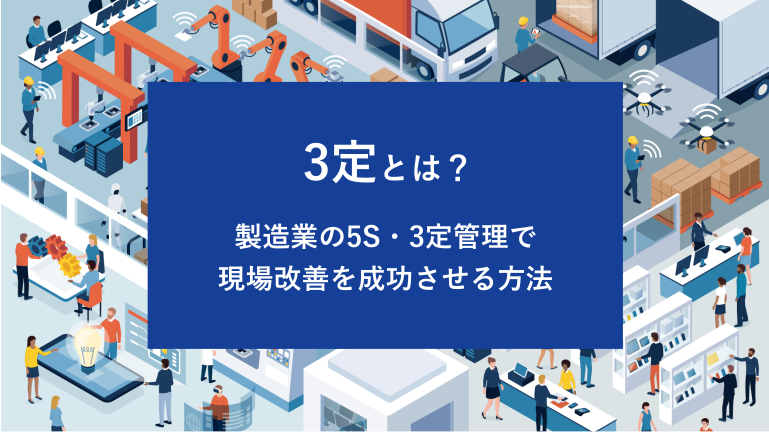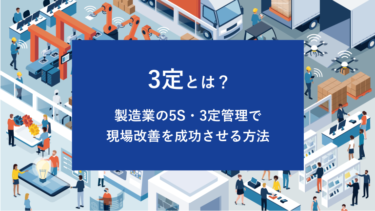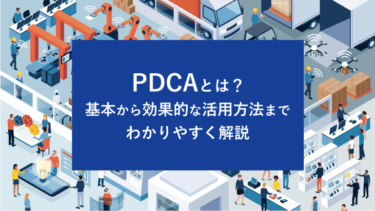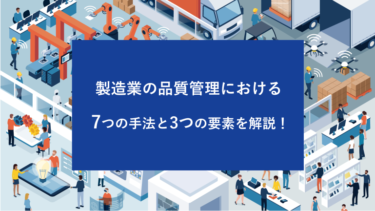製造業において、整理整頓はとても重要な要素です。働きやすい環境づくりは作業効率の向上につながり、ひいては生産性の向上につながります。利益向上を目指すうえで、整理整頓は欠かせない取り組みといえるでしょう。
3定は、そんな整理整頓を行なうために必要となる要素のことです。意識して取り組むことで、使いやすくわかりやすい整頓ができます。
3定とはどのような要素なのか。5Sを必要とする意味や3定の導入方法など、現場改善を成功させる方法について紹介します。
3定(定位・定品・定量)とは?
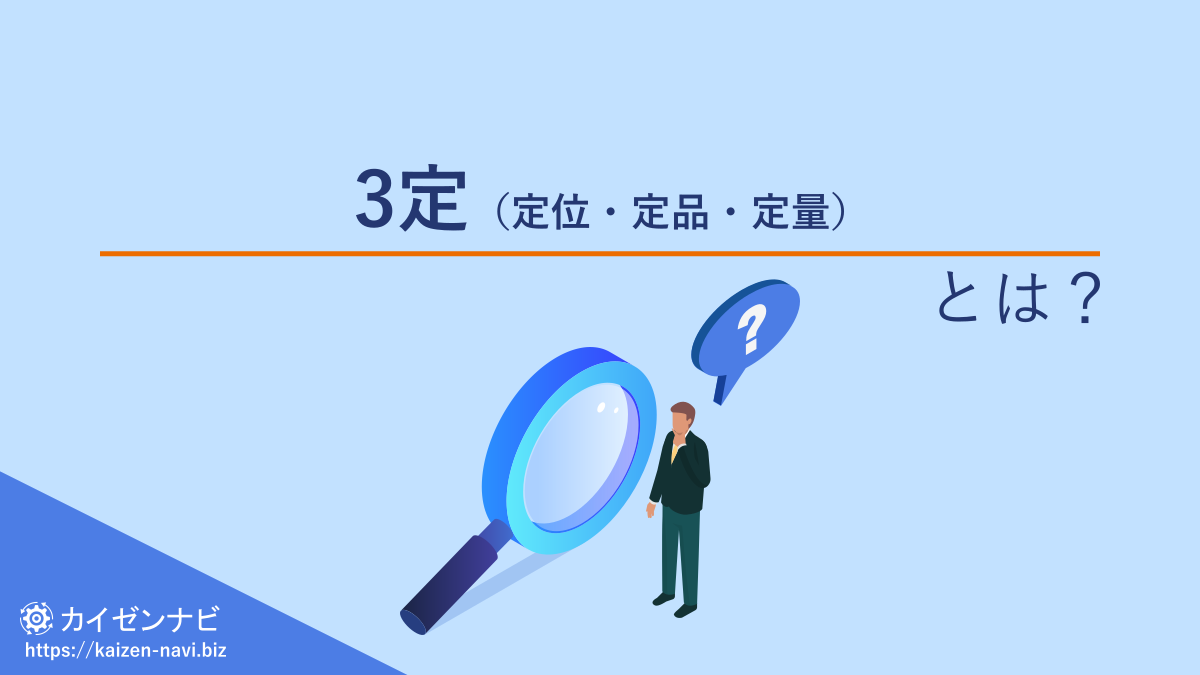
3定とは、整頓の基本となる3つの定石のことです。「定位」「定品」「定量」を意識することで、わかりやすく実用的な整頓が行なえます。
必要なときに必要な物をすぐに取り出せる状態にするためにも、それぞれの定石について知っておきましょう。
定位(ていい)とは
定位とは、物の置き場所を決めることです。あらかじめ定位置を決めておくことで、必要なときに必要な物がすぐに見つかります。
必要な物がすぐに見つかれば、探す時間を削減できます。できた時間を作業に費やすことで、生産性の向上につながるでしょう。
定位で大切なことは、わかりやすくすることです。いくら場所が決まっていても、見つけにくいと意味がありません。どこにあるのか一目でわかるよう表示することが重要といえます。
ほかにも、頻繁に使う物の場合は、アクセスのしやすさも考慮すると良いです。
定品(ていひん)とは
定品とは、置く物を決めることです。「棚の1段目には工具」「棚の2段目には部品」といったように決めておくことで、迷うことなく片付けられます。
定位と同じように、あらかじめ決まっていれば物を探すのが楽になります。探す時間が短くなることで、作業効率も向上するでしょう。
定品で大切なことは、置く物に合わせて決めることです。使用頻度が高い物は取りやすい位置に、重い物は安全のために下に置くなど、物に合わせて決めてください。
また、一目で全体が把握できることも大切です。ラベルなどで表示してあれば、箱の中を確認しなくてもすぐに物が見つかります。
定量(ていりょう)とは
定量とは、収納する量を決めることです。「レンチは3本」「ボルトは50個」といったように決めておくことで、物の管理がしやすくなります。
また、定量によって在庫の過不足を防ぐこともできます。在庫が多いと保管場所の圧迫、在庫が少ないと作業の中断となるため、在庫管理はとても重要です。
ほかにも、個数を把握することでムダな生産や発注を防ぐこともでき、コスト削減にもつながるでしょう。
定量で大切なことは、必要数を確認することです。量が多すぎるとスペースを圧迫し、整頓しても汚く見えます。基本的には必要数だけを置いて、残りは別の場所で管理すると綺麗に整頓できます。
3定の目的
3定の目的は、ただ綺麗に整頓をするためではありません。3定を意識する理由には、以下のような目的があります。
ムリ・ムダ・ムラの削除
3定を実施する目的は、ムリ・ムダ・ムラを削減するためです。ムリ・ムダ・ムラとは業務効率を低下させる3要素のことであり、作業効率の向上を目指す際に課題の一つとして挙げられています。
ムリとは、業務負荷が能力よりも大きい状態のことです。能力以上のことをすることで労災などのリスクが高まりますが、整頓によって作業が効率化されていれば、業務負荷を減らすことができます。
ムダとは、過剰によってコストが増大してしまうことです。管理ができていないと作り過ぎによる過剰在庫の心配がありますが、整頓によって個数管理がされていれば、過剰在庫となる心配がありません。
ムラとは、作業や成果に差が生じることです。準備に時間がかかることで作業時間にムラが生じますが、整頓によって定位置がわかっていれば、同じように準備し作業が始められます。
ムリ・ムダ・ムラを減らすことは、労働環境の改善や利益拡大にもつながっていきます。企業の成長を目指すうえで、3定の実施は欠かせない取り組みといえるでしょう。
作業の効率化とミスの防止
作業の効率化や作業ミスを防ぐことも、3定を実施する目的の一つです。使いやすいよう管理をすることで、どこにあるのか探す手間を省けます。部品の取り間違いなども防ぐことができ、作業ミスを減らすこともできるでしょう。
また、作業ミスの防止は安全性の向上にもなります。労働環境を改善する意味でも、3定による整理整頓は効果的です。
現場の整理整頓の徹底
3定の実施により、継続的な整理整頓が可能です。作業員全員が3定を意識し、自然と取り組むことで、整理整頓された現場環境を守ることができます。
整理整頓は、作業しやすい現場環境を作るために大切なことです。作業効率を高めるだけではなく、安全で綺麗な現場は作業員のモチベーションも高めてくれるでしょう。
また、3定は整頓の方法がわからない人の指標にもなります。大人でも整頓が苦手な人は多く、そのような人でも3定を基に管理をすれば、使いやすくわかりやすい整頓ができます。
製造業における現場改善の重要性
製造業において、現場改善が重要とされる理由には、企業の利益拡大が関係します。現場改善によって作業効率が向上し、生産性も向上することで、販売数を増やすことができるからです。
また、ムラのない生産は品質を安定させ、顧客からの信頼を得ることにもなります。信頼されることで注文も増え、利益拡大につながっていくでしょう。
ほかにも、安全性が向上することで、作業員のモチベーションも高まります。意欲的に仕事に取り組むことで生産性が高まるのはもちろん、良い現場で働くことは離職率を下げることにもつながるのです。
以上のように、現場改善によってさまざまな効果を生み出します。利益追求や企業成長をするうえで、現場改善は欠かせない取り組みといえます。
3定と5Sの関係
5Sとは、職場環境の改善や維持を目的とした取り組みのことです。「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ」の5要素から構成され、実施によって、快適な環境を作ることができます。
- 整理:物を片付けること。不要な物をわけて処分をする
- 整頓:整えて管理すること。使いやすいよう配置を決めて片付ける
- 清掃:整備すること。ゴミや汚れを掃除し、破損の修繕をする
- 清潔:環境を整えること。整理、整頓、清掃された状況を維持する
- しつけ:やり方を指導すること。誰でも5Sが続けられるようにする
3定をする目的は整頓することであり、つまりは、3定は5Sを実施するための取り組みといえます。3定を意識することで、5Sの整頓を効率よく実施できるでしょう。
製造業でよく耳にする5S活動。現場環境を改善することで作業効率や生産性が向上することから、多くの企業が注目・取り入れています。 もちろん、5Sの考えは製造業だけではありません。医療業界、物流業、サービス業、小売業なども実施して[…]
3定と5Sを組み合わせるメリット
3定と5Sは、どちらも現場環境の改善を目的とした取り組みです。そのため、3定と5Sをそれぞれ単独で実施するのではなく、合わせて実施するとより効果的となります。
もちろん、3定だけでも効果がありますが、不要な物が多いと整頓はままなりません。使わない物は整理する必要があります。
ほかにも、ラベルが見やすいよう清掃をしたり、現状を維持するため指導をしたりなど、3定と5Sは親密な関係にあるといえます。
より効果的に現場改善を目指す場合は、3定だけではなく、5Sも意識して取り組むことが大切です。
3定管理の導入ステップ
3定の取り組み方がわからない人は、以下の手順を参考にしてみてください。
- 現場の現状把握
- 3定のルールを設定
- 3定の運用と継続
現場の現状把握
まず始めに、現場の現状把握を行ないます。現状がわかっていないと、どのように整頓をすればいいのかわかりません。現場で現状把握をしたあと、見取り図を基に置き場所を決めます。
また、置き場所が散らかっている場合は、整理や清掃をして、置き場所のスペース確保をします。必要ならテープなどでスペースを区切り、専用の置き場所であることをわかりやすくしましょう。
3定のルールを設定
現状把握と置き場所を決めたら、3定のルールを決めていきます。「1段目の棚は工具」「2段目の棚は部品」といったように、基本的な枠組みを定めてください。
ほかにも、「持ち出した際には立札をかけて知らせる」「持ち手を手前側に向ける」「使ったら補充をする」など、使いやすくわかりやすいルールも決めておきましょう。
ルールを決めるポイントは、実用的であることです。実際に使ってみて、便利と思うようなルールを決めてください。実際に利用する作業員の意見を取り入れると、実用的な整頓ができます。
また、継続のしやすさも大切です。わかりやすいようルールを決めても、面倒ではルールは守られません。手順が多いと、作業効率の改善にもならないでしょう。ルールが維持できるよう、簡単であることも意識してみてください。
3定の運用と継続
ルールが決まったら、実際に運用をしてみます。そして、問題なく維持ができ、作業効率が向上されているようなら3定管理は完了です。より作業効率を高めるよう、ほかの場所も整頓をしてみてください。
もし、問題があったりルールが継続されない場合は、ルールを見直す必要があります。どのような問題があるのか、なぜルールが維持できないのかなどをまとめ、新しくルールを定めましょう。
3定管理と5Sでの現場改善を成功させるポイント
3定や5Sがうまくいかない場合は、以下のポイントを意識してみてください。
- 見える化を意識した誰でも分かるルール作り
- 現場の作業員を巻き込んで協力してもらう
- 5Sとセットで取り組む
- 定期的な点検・改善で形骸化を防ぐ
- PDCAで改善サイクルを回して柔軟にルールを見直す
見える化を意識した誰でも分かるルール作り
一つ目は、見える化を意識したルール作りです。見える化とは状況を把握し共有できる取り組みであり、見える化を意識することで、誰もが3定や5Sを必要とする意味がわかります。
必要とする意味がわかれば、進んで3定や5Sを意識するようにもなるでしょう。
また、物理的な意味でも見える化は大切です。ラベルや立札で明記することで、誰が見ても一目で物の配置がわかります。遠くから見てもわかるよう、文字の大きさや色も工夫をすると、より効果的です。
現場の作業員を巻き込んで協力してもらう
二つ目は、現場の作業員にも協力を仰ぐことです。整頓の目的は使いやすいよう整えることであり、実際に利用する作業員の意見がとても重要になります。
ルールを定める際はもちろん、実施したあとも、現場作業員からフィードバックすることで、より良い現場改善を目指すことができます。
また、実際の自分の目で確認することも大切です。文面だけでは、正しく現場を把握できません。実際に見て使ってみることで、使いやすい整頓やルール決めができるでしょう。
5Sとセットで取り組む
三つ目は、5Sも考慮しながら定めることです。3定と5Sは親密な関係にあり、合わせて行なうことで、より改善効果が高まります。
3定だけを意識して取り組むのではなく、始めから5Sを前提として取り組んでみてください。
定期的な点検・改善で形骸化を防ぐ
四つ目は、定期的な点検や改善も行なうことです。ルールは長く続くと形骸化しやすいため、定期的に見直す必要があります。
ルールが形骸化すると、3定をする目的が破綻してしまいます。表面だけをなぞるようでは、3定の効果は期待できません。中には、目的がわからないことで自己流に改修してしまう人も出てくるでしょう。その結果、ルールを守らないことで現場環境が悪化し、作業効率を低下させてしまいます。
ルール通り正しく行なわれているかを確認することも、管理をするうえで重要なことです。
また、設備や作る物が変われば、管理方法も変わってきます。状況に合わせて管理方法やルールを改善することも、現場改善には必要といえます。
PDCAで改善サイクルを回して柔軟にルールを見直す
五つ目は、PDCAサイクルを回し継続的にルールを見直すことです。設備や作る物によって現場環境は変わるため、ルールも柔軟に変更する必要があります。
PDCAサイクルとは、「計画」「実行」「評価」「改善」を1サイクルとした取り組みのことです。改善をしたら実行に移し評価するといったように、サイクルを繰り返すことで、前のサイクルよりも、さらに内容を良くすることができます。
一度定めたルールが、必ずしも正しいとは限りません。実際に使ってみての評価もありますし、工場の機械化によって現場環境が変わることもあります。形骸化をさせない意味でも見直しが必要であり、そのための手段として、PDCAサイクルがおすすめです。
ビジネスで改善を進めるうえでよく聞く「PDCAサイクル」。この記事では、PDCAサイクルの基本から、実際にどう活用できるかを詳しく説明します。また、この記事を読むことで、業務改善をどのように進めるかの具体的な方法が理解できるようにな[…]
まとめ:3定は「整頓」を徹底し、現場を効率化する手法
3定とは、整頓の基本となる3つの要素のことです。「定位」「定品」「定量」を意識することで、効率的な整頓を可能にします。
3定の実施は、現場を改善し作業効率の向上させます。ムダやムラなどが改善されることによる、コスト削減も期待できるでしょう。
利益向上を目指すためにも、3定を意識した整理整頓を心がけてみてください。
また、生産管理システムを導入することで、在庫管理が楽になります。ICタグやRFタグも活用すれば、製品や工具の行方を追跡することも可能です。さらなる作業効率の向上につながりますので、ぜひシステムの導入も検討してみてください。