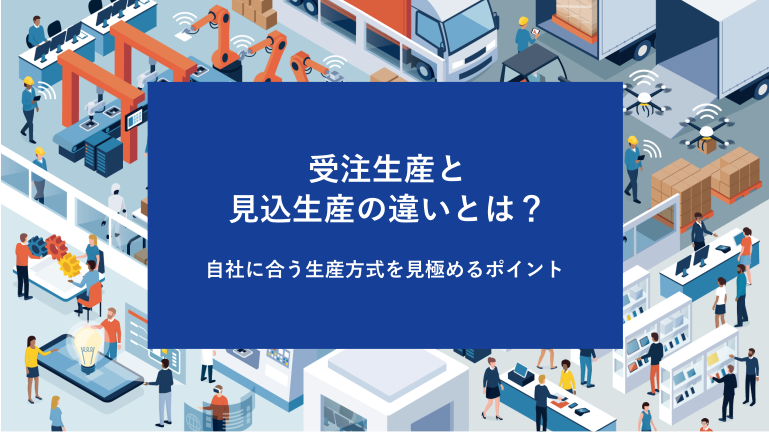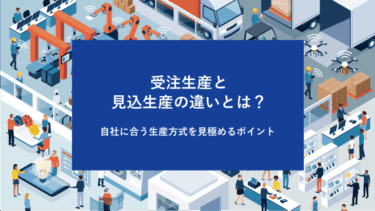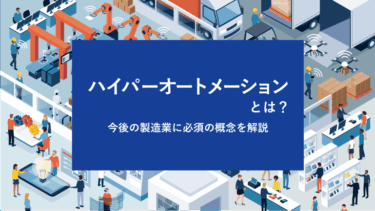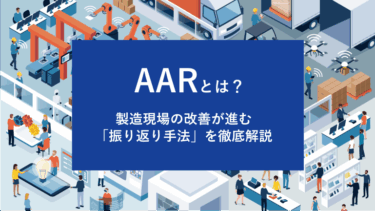製造業では「受注生産(Make to Order)」と「見込生産(Make to Stock)」という2つの生産方式が広く使われています。
しかし、「自社にはどちらが適しているのか」「切り替える必要があるのか」など、現場で明確に判断できているケースは意外と少ないかもしれません。
本記事では、両者の違いや特徴を分かりやすく整理し、それぞれのメリット・デメリット、活用シーンを比較したうえで、自社に合った生産方式を見極めるための考え方をご紹介します。
※本記事は、特定の方式を推奨するものではなく、「違いを理解し、自社に合った最適な設計を行う」ための判断軸を提供することを目的としています。
「受注生産」と「見込生産」とは?

生産方式を見直すうえで、まずは「受注生産(Make to Order)」と「見込生産(Make to Stock)」の違いを正しく理解することが重要です。
両者は、生産の開始タイミングや在庫の考え方、対応する製品の特性などに大きな違いがあり、メリット・デメリットも異なります。
ここでは、それぞれの方式の基本的な考え方と特徴を整理し、自社の現状と照らし合わせるうえでの基礎知識を確認しておきましょう。
受注生産とは? ― 顧客注文後に作る無駄のない生産方式
受注生産(Make to Order)は、顧客から注文を受けてから生産を開始する方式です。製品の仕様が顧客ごとに異なるケースが多く、柔軟な対応が求められるBtoB製品やカスタム品、部品製造などでよく採用されています。
主な特徴:
- 注文確定後に生産を始めるため、過剰在庫や作りすぎのリスクが低い
- 顧客ごとの要望に応じた個別対応や仕様変更がしやすい
- 一方で、短納期対応や高精度な工程管理が求められるため、計画と現場の連携が重要
適した製品の例:特注機械、産業装置、試作部品、顧客ごとにカスタマイズが必要な製品 など
受注生産は、無駄の少ない効率的な方式である一方、受注が集中した場合のリソース確保や、納期管理の複雑さといった運用上の課題にも注意が必要です。
見込生産とは? ― 需要予測で先回りするスピード重視型
見込生産(Make to Stock)は、過去の販売実績や市場データなどに基づいて、あらかじめ製品を生産しておく方式です。主に需要の変動が少ない標準品や、リピート率の高い製品に適しています。
主な特徴:
- 在庫をあらかじめ用意しておけるため、短納期の顧客要望に応えやすい
- 同じ製品をまとめて生産することで、スケールメリットや生産コストの削減が期待できる
- 一方で、需要予測が外れた場合には在庫過多や欠品といったリスクが発生する可能性もある
適した製品の例:標準部品、汎用製品、家電、消耗品など、仕様が変わらず大量に流通する製品
見込生産は、スピード対応やコスト効率の面で強みがありますが、需要の変化に弱く、在庫管理や計画精度が生産性に直結するという点に注意が必要です。
受注生産と見込生産の違いを比較表で整理
ここまで紹介してきた「受注生産」と「見込生産」には、それぞれ明確な特徴と適した運用シーンがあります。
以下の比較表では、両者の違いを主な観点ごとに整理しました。
自社の現状と照らし合わせながら、どちらの方式がより適しているかを考えるヒントとしてご活用ください。
このように、どちらの方式にも一長一短があり、自社の製品特性や市場環境に応じた選択が重要になります。
| 比較項目 | 受注生産 | 見込生産 |
|---|---|---|
| 生産開始のタイミング | 注文確定後に生産開始 | 需要予測に基づいて先行生産 |
| 在庫リスク | 低い(必要な分だけ生産) | 高い(予測が外れた場合は余剰在庫に) |
| 納期対応 | 比較的長くなる傾向 | 短納期対応がしやすい |
| 柔軟性 | 高い(顧客ごとの個別対応が可能) | 低い(標準化・仕様固定が前提) |
| 管理の難易度 | 高い(工程ごとの調整が都度必要) | 中程度(計画通りなら安定しやすい) |
| 適した製品 | 特注品、多品種少量、都度仕様変更品 | 標準品、大量生産品、リピート性の高い製品 |
どちらの方式にも一長一短があり、製品の性質・顧客の要望・需要の安定性といった要素を総合的に見て判断することが重要です。
なぜ今「生産方式の見直し」が注目されているのか
受注生産と見込生産、それぞれにメリットと課題があることは理解していても、「これまでのやり方を変えるのは難しい」と感じている現場も多いのではないでしょうか。
しかし近年、在庫の過不足や納期トラブル、計画変更の頻発といった問題が顕在化し、従来の生産方式では対応しきれないケースが増えています。
さらに、コロナ禍以降の需要変動やサプライチェーンの不安定化を受け、これまでの「見込中心の生産計画」には限界があるとの認識が広がりつつあります。
こうした背景から、今あらためて「自社に合った生産方式とは何か?」を見直す企業が増えており、柔軟かつ現実的な生産体制の再設計が求められています。
在庫過多・納期遅延など、現場で増える課題
多くの製造現場で今、「在庫はあるのに必要な部品が足りない」といったチグハグな在庫状況が課題となっています。これは、営業部門による需要予測と、実際の受注内容が乖離することによって、在庫過多と欠品が同時に発生していることが主な原因です。
このような状況が続くと、生産計画の変更や納期調整、急な残業対応が頻発し、現場の負担が増大します。加えて、仕入れや製造の各工程で調整が必要となり、工程全体の効率低下にもつながりかねません。
こうした問題は、「見込生産」の構造的な弱点でもあり、需要の読み違いがそのまま現場の混乱に直結するというリスクが浮き彫りになっています。
市場変化で見込生産頼みが限界に
かつては、安定した需要と販売サイクルに基づいて先行生産する「見込生産」が、多くの製造業にとって最適な手法とされていました。しかし近年では、顧客ニーズの多様化やカスタマイズ要求の増加、短納期志向の強まりにより、その前提が大きく変化しています。
さらに、コロナ禍以降の急激な需要変動や、原材料・部品供給の不安定化など、予測が立てづらい時代に突入したことで、「売れる前に作っておく」戦略がかえってリスクとなる場面が増えました。その結果、在庫を抱えても売れない・必要なものは不足するといった非効率が顕在化し、見込生産一辺倒の運用には限界があるとする企業も少なくありません。こうした背景から、最近では受注生産型への移行や受注と見込みを柔軟に組み合わせた「ハイブリッド型」への見直しを進める企業が増えています。
現場目線で見る、2つの生産方式のメリット・デメリット
「受注生産」と「見込生産」は、それぞれに合理性のある生産方式ですが、理論上のメリットと、実際の現場で感じる課題にはギャップがあることも少なくありません。
たとえば、見込生産では「短納期対応がしやすい」とされる一方で、需要のズレによる在庫の山と欠品の同時発生に悩まされる現場も多くあります。
また、受注生産に移行することで在庫リスクは減るものの、納期のプレッシャーや調整業務の煩雑化といった新たな課題が浮かび上がることもあります。
ここでは、現場でよく耳にする典型的な課題や、導入によって得られる効果を、それぞれの方式ごとに整理していきます。
見込生産が抱える典型的な課題
見込生産は、一定の安定性と効率性を持つ一方で、予測と現実のズレによって生じる不具合が現場の悩みの種となることが少なくありません。
とくに、以下のような課題は多くの現場で共通して見られます。
- 需要変動による在庫過多・欠品の同時発生
→ 売れ筋予測が外れると、必要な部品が足りない一方で、不要な在庫だけが積み上がってしまいます。 - 計画変更による工程混乱
→ 市場や営業の状況に応じて生産計画を頻繁に変更せざるを得ず、現場が翻弄されやすくなります。 - 営業と現場の情報ギャップによる負担増
→ 予測を立てる部門と実行する現場との間で認識のズレが起き、結果的に無理な対応や残業が常態化しがちです。
とくに生産管理担当者にとっては、「予測通りにいかない現実」と日々向き合わなければならないことが大きなストレス要因になります。
一見安定して見える見込生産ですが、外的変化に対して脆さを抱えていることを忘れてはなりません。
受注生産に切り替えることで得られる効果
見込生産の課題を踏まえ、受注生産への移行を検討する企業も増えています。
適切に運用できれば、以下のような現場にとっての具体的な効果が期待できます。
- 不要な在庫を削減し、倉庫スペースや管理コストを軽減
→ 注文を受けてから生産するため、「売れ残り」を最小限に抑えることが可能です。 - 顧客仕様に柔軟に対応でき、満足度向上にもつながる
→ 個別対応が前提となるため、カスタマイズや仕様変更にも対応しやすくなります。 - DXツールを活用すれば、生産の可視化と工程効率化が可能に
→ 設計・製造・購買の各部門がリアルタイムで連携しやすくなり、全体最適が実現しやすくなります。
受注生産を導入することで、「作りすぎ」「作り直し」といったムダが減り、結果として品質の安定や現場負担の軽減にもつながります。
ただし、すべてを受注生産に切り替えると納期対応が難しくなる恐れがあるため、「どの工程までを見込みで行い、どこから受注対応に切り替えるか」をあらかじめ明確に設計しておくことが成功のポイントです。
受注生産の落とし穴と注意点
受注生産には多くのメリットがありますが、すべての企業や現場にとって万能な解決策とは限りません。
運用を誤ると、かえって現場の負荷が高まるケースもあります。以下のような落とし穴に注意が必要です。
- 受注が集中したときに生産リソースが不足する
→ 納期遅延のリスクが高まり、計画的なリードタイム管理がより重要になります。 - 工程間の連携精度が求められる
→ 各工程の遅れが全体に波及しやすく、ちょっとしたズレが大きな納期影響につながる恐れがあります。 - 設計・購買・営業の情報共有体制が不可欠
→ 顧客要求の反映や仕様確定が遅れると、すぐに生産に着手できず、全体の納期が圧迫されます。
また、個別対応が前提となるため、現場での調整業務が煩雑になりやすいのも受注生産の特徴です。
こうしたリスクに対応するためには、システムやデータ連携を前提とした生産体制の構築が不可欠です。
情報のリアルタイム共有や部門間の連携強化によって、受注生産のメリットを最大限に活かすことが可能になります。
どちらが自社に合う?判断のための3つのチェックポイント
受注生産と見込生産のどちらを選ぶべきかは、「一般論」ではなく、自社の製品特性や顧客ニーズ、業務の現実に即して判断する必要があります。
最適な生産方式は、業種や製品によって異なり、「どちらか一方に決めること」よりも、現状を正しく理解し、柔軟に使い分けることが重要です。
ここでは、自社に合った生産方式を見極めるために確認すべき、3つの視点(チェックポイント)をご紹介します。
一つずつ照らし合わせながら、自社に最適なバランスを考えてみましょう。
製品特性 ― 標準化度・カスタム性を確認
まず確認したいのは、自社製品がどれだけ標準化されているかという点です。
あらかじめ仕様が決まっていて、同じ形状や構成で繰り返し生産される製品であれば、見込生産に適しています。
一方で、顧客の要望に応じて都度設計変更が発生するようなカスタム製品や一点物の場合は、見込生産では対応が難しく、受注生産の方が現実的です。
例として、次のような分類が考えられます:
- 見込生産が適する製品の例:標準品、ユニット化された製品、定番の消耗部品など
- 受注生産が適する製品の例:特注機械、仕様変更が多い装置、一点物の試作など
製品ごとに標準化度が異なる場合は、部品単位・工程単位での切り分けを検討することも有効です。
需要の安定性 ― 変動幅を数値で把握
次に確認すべきは、製品の需要がどれくらい安定しているかです。
「最近は売れている気がする」といった感覚ではなく、売上や受注データの変動幅を数値で確認することが重要です。
たとえば、月ごとの受注数量や出荷実績の推移から、過去半年〜1年分の**変動率(変動の幅や頻度)**を把握すると、予測の精度を定量的に評価できます。
- 需要が安定している製品:見込生産でも在庫リスクを抑えやすい
- 需要の変動が大きい製品:見込生産では余剰在庫や欠品のリスクが高まりやすい
このように、データに基づいて判断することで、計画精度や在庫管理の改善につながります。
変動が大きい製品については、受注生産やハイブリッド型への切り替えを検討する価値があります。
リードタイム要求 ― 顧客が求めるスピードを評価
最後に重要となるのが、顧客がどれだけ短納期を求めているかという点です。
納期の余裕がある製品であれば、注文後に生産を始める受注生産でも十分に対応可能です。
しかし、「できるだけ早く納品してほしい」「注文後すぐにほしい」といった声が多い場合、完全な受注生産では対応が難しくなることもあります。
このようなケースでは、たとえば一部の部品や中間工程までを事前に生産(見込み)しておき、組立や最終仕様は受注後に対応するといったハイブリッド型の運用が有効です。
納期に対する顧客の期待水準を正しく把握し、どこまでを先に用意し、どこからを受注対応にするかを戦略的に見極めることが、安定供給と柔軟対応の両立につながります。
ハイブリッド型(受注点方式)という選択肢も
受注生産と見込生産は対照的な方式ですが、必ずしもどちらか一方に絞る必要はありません。
両者のメリットを組み合わせた「ハイブリッド型(受注点方式)」という選択肢も、有効な運用手法の一つです。
ハイブリッド型では、たとえば以下のような分業が可能です:
- 部品や中間品までは見込で生産して在庫化しておく
- 最終組立や仕様確定工程は、顧客の注文を受けてから対応する
この方法により、短納期対応の柔軟さを維持しつつ、在庫リスクを最小限に抑えることができます。
たとえば、家電や産業機械などの分野では、標準化された基盤やユニットは事前に生産し、筐体や機能のカスタマイズは受注後に対応する、といった運用が実際に行われています。
製品や工程の特性に応じて、「どこまでを見込生産にするか」を設計することが、現実的で無理のない生産方式の鍵になります。
成功企業に学ぶ生産方式改善のポイント
生産方式の見直しに成功している企業では、共通して「在庫管理の最適化」「リードタイム短縮」「現場の見える化」の3点を重点施策として実践しています。
これらを継続的に改善することで、受注変動への柔軟性や生産計画の精度が大きく向上しています。
さらに特徴的なのは、改善が現場リーダーを中心としたボトムアップ型で進められている点です。
現場を最も理解している担当者が主体となり、課題の抽出から改善策の立案・実行までをリードすることで、実効性の高い取り組みが実現しています。
まとめ|違いを理解すれば“最適な生産方式”が見えてくる
「受注生産」と「見込生産」の違いを正しく理解することは、単なる知識ではなく、自社の生産体制を根本から見直すための第一歩です。
両者の特徴・メリット・注意点を把握することで、自社に必要な改善ポイントがより鮮明になります。
生産方式を検討する際は、次の3点を整理することが重要です。
- 製品特性:標準化度・カスタマイズの必要性
- 需要の安定性:販売・受注データの変動幅
- 顧客のリードタイム要求:短納期の必要性と優先度
これらを踏まえ、
「どの工程を見込みで進め、どこから受注対応に切り替えるか」を明確に設計することで、在庫過多や欠品、納期遅延といった課題を無理なく改善できます。
ポイントは、受注生産か見込生産かの“二択”ではなく、
自社の実情に合わせて最適なバランスを設計することです。
生産方式の理解は、生産改革の出発点。
自社にとって最も合理的で柔軟な運用を構築することで、現場の負荷軽減と競争力向上につながります。