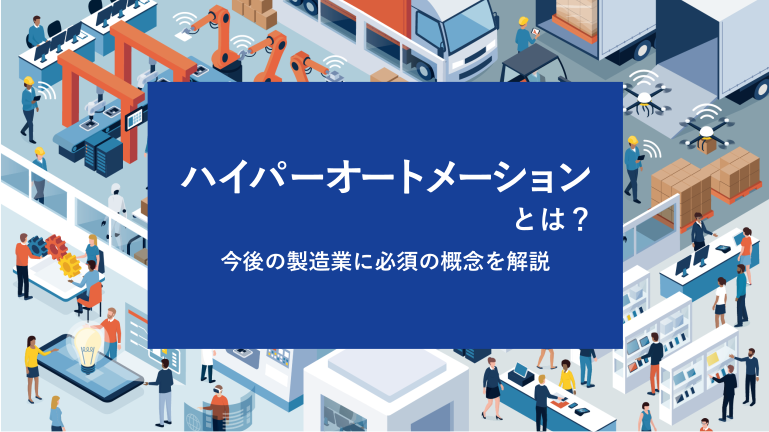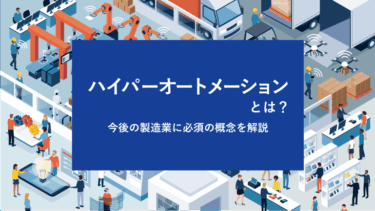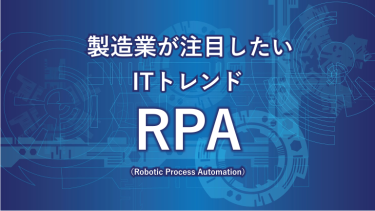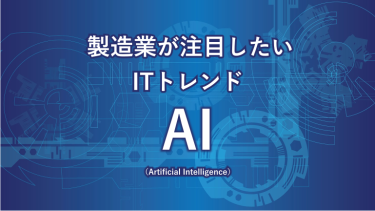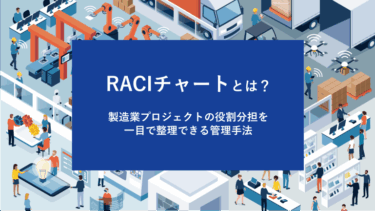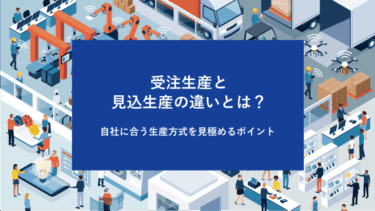近年は、デジタル技術によってさまざまなことが自動化しつつあります。身近なものだとスマートホームや自動運転などが挙げられ、人の労力がどんどん不要になっています。
ハイパーオートメーションは、デジタル化が進む現代において、より高度な自動化を実現する新しい働き方のアプローチです。業務全体を自動化することで、人手不足を始めとしたさまざまな課題解決が期待できます。
工場のデジタル化が進められる製造業ではハイパーオートメーションの導入が競争力の重要要素として加速しており、適用領域を段階的に拡大する動きが広がっています。時代に合わせた生産を行なうためにも、ぜひハイパーオートメーションについて知っておきましょう。
ハイパーオートメーションとは何か
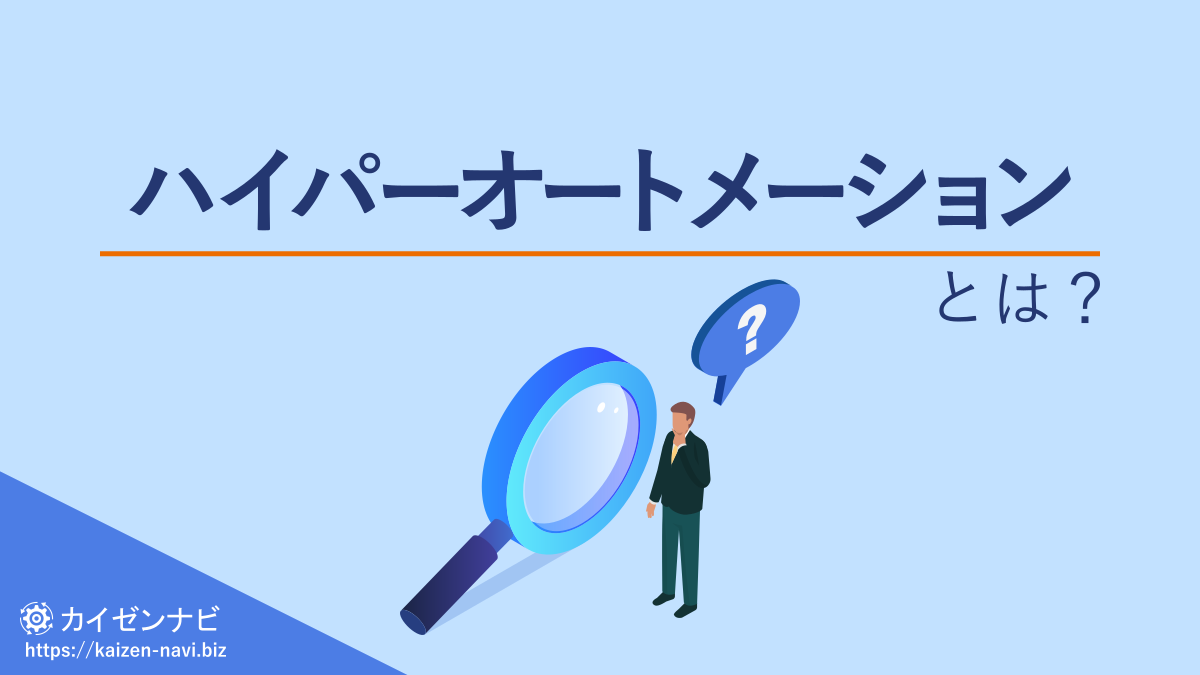
ハイパーオートメーションとは、複数のデジタル技術を組み合わせ、作業プロセスを自動化させる仕組みのことです。簡単に説明すると「人が指示をしなくても、AIが自分で判断し代わりに作業をしてくれる」仕組みといえます。
データ入力や情報整理といったデジタル業務に加え、作業用ロボットの導入によってアナログ作業の自動化も可能です。トラブル対応や不良品の識別といった判断が必要な作業にも対応ができ、人の監督下でAIが判断・実行を補助し、例外や最終承認は人が担う体制により、広範な工程での自動化が進みます。
自動化によって従来の業務が大きく変わることから、さまざまな業界や企業で注目されています。
RPAとハイパーオートメーションの違い
RPA(Robotic Process Automation)とは、業務をデジタルロボット(ソフトウェア)が代わりに行なう自動化技術のことです。データ入力、リストの整理、メールの送信、データの収集などデジタルで行なう仕事はいろいろありますが、それら業務を人の代わりに作業してくれます。
ハイパーオートメーションとの主な違いは、判断業務への対応の違いです。RPAは判断業務ができず決められたプロセスをこなすだけですが、ハイパーオートメーションは自分で判断し業務を続けて作業をすることができます。
例えば、各号機から生産データを収集するとします。RPAだと次の業務へ移行する判断ができないためデータを収集して終わりですが、ハイパーオートメーションの場合だと終わったのを判断してデータの分析も行ないます。さらに、分析が終わればその結果をまとめてレポートにするなど、AIが自分で判断し一連の流れとして行なってくれます。
RPAはハイパーオートメーションを構成する技術の一つであり、RPAで自動化した業務を別の技術でつなぎ合わせることで、プロセス全体を自動化することができます。
なぜ今、企業がハイパーオートメーションを求めるのか
ハイパーオートメーションが求められる理由には、以下のようなことが挙げられています。
人手不足
一つ目は、人手不足が問題となっているからです。近年は少子高齢化が深刻化しており、それに伴い労働人口も減少しています。働き手がいないことで業務が成り立たず、業務縮小や廃業をする企業も少なくありません。
そのことから、新しい働き手としてAIが注目されています。AIによって業務が自動化されれば、少ない人数でも業務を回すことが可能です。
少人数でも仕事ができるよう、ハイパーオートメーションによる業務の自動化が求められています。
RPA単体の限界
二つ目は、RPAだけではできることが限られているからです。RPAも業務を自動化しますが、できる範囲は限定的であり、カバーできない業務が多く存在します。
より多くの業務を自動化するためにも、RPAを含めたハイパーオートメーションによる仕組みが必要とされています。
生成AIでの判断業務の自動化も現実に
三つ目は、生成AIが進化し、できる業務が広がったからです。人間中心(HITL)での運用が前提ではありますが、従来のAIでは判断が必要な業務は難しかった判断業務も、AIが進化したことで対応できる領域が広がっています。
一方で、高リスクの意思決定や例外処理は人間の監督(Human-in-the-Loop, HITL)を前提とするのが実務上のベストプラクティスです。たとえば、品質異常の自動検知はAIが行ない、是正処置の選択・承認は担当者がゲートで確認する、といった二段構えの設計が有効です。
また、モデルの誤検知/見逃し、データドリフト、バイアスといったリスクに備え、監査可能なログ、再学習プロセス、性能モニタリング(精度・再現率・アラート適合率)を継続運用に組み込みます。これにより、生産性向上と安全性・コンプライアンスを両立できます。
判断業務もAIによって自動化できるようになったことから、新しい業務への導入が検討されています。
経営側の「全社効率化」プレッシャー
四つ目は、経営側から期待されているからです。自動化が実現すれば効率よく生産が行なえ、結果としてコスト削減や生産数の向上につながります。
企業の利益を増やすためにも、経営側がハイパーオートメーションを求め、生産側に導入を指示しています。
どんな業務が対象になるのか
ハイパーオートメーションが導入されることで、業務がどのように変化するのか。それぞれの業務ごとに考えてみましょう。
バックオフィス領域
バックオフィス(事務)では、各書類業務を自動化できます。業務内容には請求処理、受注処理、支払処理などがありますが、それらのデジタル業務がすべて自動化されます。
さらに、業務を続けて行なうことも可能です。顧客からの依頼を受注処理し、その内容を契約管理します。製造部門に発注・在庫データの転記をした後、営業部門へ請求処理を行なうといったように、一連の流れでプロセスを実行できます。
書類仕事は、細かい仕事が多いことからヒューマンエラーも起こりがちです。正確性を高める意味でも、ハイパーオートメーションによる自動化はバックオフィス領域で必要といえるでしょう。
製造現場
製造現場では、生産データの管理を自動化できます。業務内容には検査データ入力、在庫データ更新、生産計画調整などがありますが、それらのデジタル業務がすべて自動化されます。
また、管理だけではなく作業も自動化できます。品質検査の自動化や資材の自動発注、さらには稼働データを基にした予兆保全など、製造現場には自動化できる業務がたくさんあります。
近年は、製造の現場でも人手不足が問題視されています。生産性が低下するだけではなく、属人化や労災のリスクも高まることから、自動化を望む現場は多いです。
企業の利益向上だけではなく、作業員の負担を軽減する意味でも、ハイパーオートメーションが必要といえるでしょう。
DX推進部門
DX推進部門では、プロセスの進捗管理を自動化できます。KPI収集やレポート作成、データ統合(ETL:Extract, Transform, Load)をしたうえで予測を立てるなど、効率よくDXへの移行が進められます。
近年は、世界的にDXへの移行が推奨されており、製造業界でもDXが求められています。時代に合わせた生産を行なうためにも、DXへの移行は必須といえるでしょう。
とはいえ、DX化にはさまざまな課題もあり、簡単に移行できるわけではありません。DXへの移行を失敗しないためにも、先駆けとしてハイパーオートメーションの活用が求められています。
導入のメリット・デメリット
ハイパーオートメーションを導入するにあたって、メリット・デメリットを理解しておくことも大切です。
ハイパーオートメーションには、以下のようなメリット・デメリットがあります。
ハイパーオートメーションのメリット
ハイパーオートメーションの導入により、業務の効率化が期待できます。AIが自律的に判断して業務を進めるため、人の介入は最小限で済みます。作業が減ることで大幅な工数削減が実現します。
また、AIが生産管理することで品質の均一化もできます。スキルの違いやヒューマンエラーによる品質のばらけがなくなり、安定した生産が行なえるでしょう。
ほかにも、誰が作業しても同じようにできることから、属人化解消にもつながります。効率化されたプロセスは、業務の標準化がしやすくなります。
組織全体での最適化が可能であり、その結果、生産数や利益を向上させられます。
ハイパーオートメーションのデメリット
ハイパーオートメーションには、導入が大変であるデメリットもあります。ハイパーオートメーションには複数のデジタル技術が用いられますが、その導入にはコストがかかります。初期費用として、数百万円〜数千万円かかる場合も珍しくはありません。
また、デジタル技術を用いることから、サイバー攻撃をされるリスクもあります。情報漏えいやマルウェアの被害を防ぐためにも、充分なセキュリティ対策をとる必要があるでしょう。
ほかにも、ツールが乱立することで現場が混乱しやすいです。現場が変化することを作業員が拒否する可能性も高く、導入したからといってスムーズに移行できるわけではありません。
以上のように、導入に関しての課題が多く存在します。導入予算を準備するのはもちろん、初期設計を整えたりデジタル人材を育てたりなど、導入を進めるためにはしっかりとした準備が必要です。
ハイパーオートメーションに用いられる技術・ツール例
ハイパーオートメーションは、複数のデジタル技術を用いて行なわれます。どのような技術が使われているのか確認してみてください。
RPA
RPAは、デジタルロボットによって行なわれる自動化システムです。データ入力やデータ整理といった事務作業を、人の代わりにロボットが作業をします。
ハイパーオートメーションでは、入力されたデータを管理する際に活用されます。各号機からのデータをRPAが集計し、そのデータを基にAIが分析し結果を出力するわけです。
ほかにも、マニュアルの作成やメールの送信といった業務も、RPAによって行なえます。
製造業務は主に実働が多いことから、事務仕事と無縁と思うかもしれません。ですが、データ入力や在庫管理など、製造部門でも事務仕事をする機会はたくさんあります。
生産プロセスを自動化するにあたって、RPAも必要とされる技術といえるでしょう。
近年、人手不足や業務効率化の課題を背景に、RPA(Robotic Process Automation/ロボティック・プロセス・オートメーション)に注目が集まっています。本記事では、RPAの基本から導入メリット、他システムとの違い、[…]
iPaaS
iPaaS(Integration Platform as a Service)は、複数のクラウドやシステムを統合するデジタル技術です。システム間のデータ連携を行なうことで、業務の自動化を実現します。
例えば、Excelとメールを連携するとします。それにより、「Excelに入力された数値を、メールで送信する」といった一連の流れが可能となります。
本来ならExcelにデータを入力するだけで終わってしまいますが、iPaaSによってシステムをつなぎ合わせることで、メールで送るといった操作につなげられるようになるわけです。
ハイパーオートメーションでは、さまざまなデジタル技術が使われています。デジタル技術同士を連携させるためにも、iPaaSは欠かせません。
AI
AIは、コンピューターを学習させるデジタル技術です。情報を学ぶことでコンピューターが成長し、学んだデータを基に、コンピューター自らが判断して実行できるようになります。
以前までは学習した情報を基に実行するだけでしたが、近年では自らが新しく作り出せるようにもなりました。テキスト、画像、音楽、動画などのコンテンツ生成に活用され、現在では生成AIが主流となってきています。
ハイパーオートメーションでは、AIによって物事を判断します。「データ入力が終わったらデータを送信する」「トラブルが解消されたら運転を開始する」といったように、物事の切り替えをAIによって判断するわけです。
ほかにも、画像認識や音声認識などの判別もAIによって行なわれるなど、人が判断していた業務をAIが代わりに行ないます。
製造業界では、近年、AIによる考えが広まりつつあります。機械による自動化は革新的であり、多くの企業がAIに注目しているといえます。 ですが、期待する一方で不安な点も多く、導入に踏み切れない企業も少なくはありません。「作業が効率[…]
OCR
OCR(Optical Character Recognition)は、画像データから文字を読み取りテキストデータへ変換する技術です。本来なら読み取りが難しい手書き文字なども、OCRがスキャンし分析することで、テキストデータとして読み取れるようになります。
ハイパーオートメーションでは、手書きデータの入力作業を自動入力する際に活用されます。現場では計測したデータを手書きで記録することも多いですが、OCRならそのまま読み取ることが可能であり、手入力をする手間がありません。作業効率が向上するだけではなく、ヒューマンエラーの防止にもつながります。
ほかにも、紙媒体をデジタル管理に移行する際に使われるなど、アナログからデジタルを移行する際に必要な技術です。
BPMS
BPMS(Business Process Management System)は、業務プロセスを最適化する技術です。業務プロセスを見える化することで、業務の管理や業務の見直しなどができるようサポートします。
業務プロセスの管理にはワークフローシステムがありますが、ワークフローシステムはタスクの効率化を目指すのに対して、BPMSはプロセス全体を改善することを目的としています。
ハイパーオートメーションでは、業務プロセスを管理するために活用されます。プロセスの設計や実行、管理や最適化など、効率よく生産が行なえるようプロセス全体を調整します。
また、継続的な改善もBPMSの役割です。効率化を目指すだけではなく、スケジュールや顧客ニーズに合わせたプロセスの変更も行ないます。
トラブルなく生産を行なうためにも、プロセス全体を管理するBPMSが必要です。
まとめ:ハイパーオートメーションは“自動化の集大成”であり、業務改革そのもの
ハイパーオートメーションとは、デジタル技術を組み合わせて自動化させる仕組みのことです。データ入力を自動化させるRPA、画像の読み込みを自動化させるOCR、アプリケーションの連携を自動で行なうiPaaS、そして、それらデジタル技術を統括して扱うAIなど、さまざまなデジタル技術の集大成によって構成されています。
以前から自動化する仕組みはありましたが、データ入力や部品の組み立てなど、限定的な自動化が一般的でした。もちろん、限定的な自動化でも充分な効果が期待できましたが、タスクの切り替えは人が行なうなど、人の手が必要な場面は多かったです。
しかし、生成AIの登場によって判断業務ができるようになりました。今までは人が判断し切り替えてきた業務も、生成AIによって自動化されるようになります。
ハイパーオートメーションによって働き方が大きく変わるといっても過言ではなく、導入は業務改革そのものといえるでしょう。
DXが推奨されていることから、今後はデジタル管理された生産が主流となってきます。時代に合わせた生産を行なうためにも、ハイパーオートメーションの導入を検討してみてください。