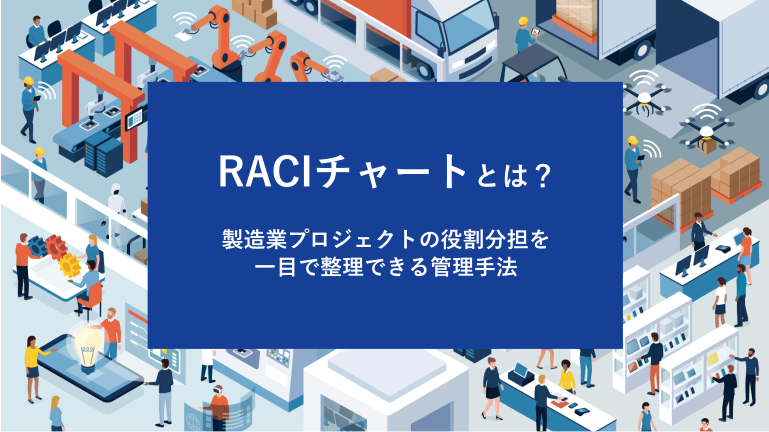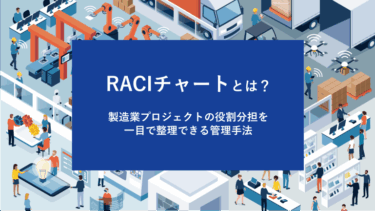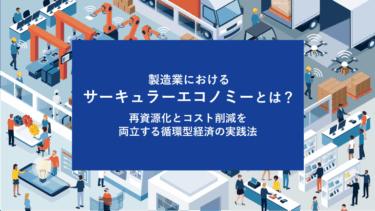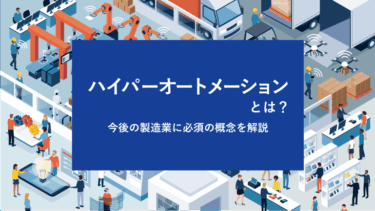新しいプロジェクトを進める際、まずは役割分担から始めるのが一般的です。「誰が設計をするのか」「誰が責任者になるのか」など始めにしっかり決めておくことが、プロジェクト成功のカギといえます。
新しいプロジェクトを進める際、まずは役割分担から始めるのが一般的です。「誰が設計をするのか」「誰が責任者になるのか」など始めにしっかり決めておくことが、プロジェクト成功のカギといえます。
しかし、プロジェクトが大きくなるほど役割分担は複雑化しやすくなります。行なうべき工程も多くなり、「誰が何をするのか」がわからなくなってしまうでしょう。
RACIチャートは、そんな複雑化する役割分担をわかりやすくするためのツールです。各工程やメンバー、それぞれが担当する役割を一つの表にまとめることで、「誰がどの役割なのか」を明確化します。
それぞれの役割がわかれば、各工程間の連携も取りやすくなります。スムーズに作業が進むことで、生産効率を高めることにもつながるでしょう。
RACIチャートとはどのようなツールなのか。ツールの仕組みや作り方、使用する際の注意点など、RACIチャートについて紹介します。
RACIチャートとは?

RACIチャートとは、プロジェクトメンバーの役割を明確にするツールのことです。参加メンバーとそれぞれのタスクを一つの表にまとめることで、誰がどの仕事や役割を担当しているかを一目でわかるようにします。
役割決めは、プロジェクトを円滑に進めるためにとても重要な要素です。各自が自分の役割を理解することで、行なうべき仕事の範囲がわかるようになります。報告や質問をする際も「誰に連絡や相談をすればいいのか」がすぐにわかり、スムーズに進められるでしょう。
また、担当者や責任者がわかれば、トラブルが生じた際の原因究明がしやすいです。担当者や責任者から現場の様子を聞き取ることで、現状を理解しやすくなります。
RACIチャートは、ただ自分の役割を確認するための表ではありません。ほかの人の役割を知ることができ、それによって連携を取りやすくしてくれます。
「誰に聞けばいいのかわからない」といったトラブルを防ぐためにも、RACIチャートを使って、各役割を明確化してください。
製造現場で役割分担が曖昧になる理由
そもそも、製造現場で役割分担が曖昧になる理由は、チームや部門間での意思疎通ができていないからです。連携がとれていないことで所在がわからず、結果として責任の範囲が曖昧となってしまいます。
連携がとれていない理由としては、近年問題となる人材不足が挙げられます。人手が不足していることで連絡を取って暇がなくなり、その結果、連携先の情報が入ってこなくなるわけです。
また、人手不足は業務の属人化を誘発させます。人手が不足していることから同じ仕事を担当することになりますが、長く仕事を続けることでほかの人が対応できなくなります。ほかの人から見て「なんの仕事をしているかわからない」ことも、役割が曖昧になる理由といえるでしょう。
ほかにも、報告・連絡・相談ができていない、標準化ができておらず作業にばらつきが出る、急な変化によって現場が混乱しているなども考えられます。
理由はいろいろ挙げましたが、共通することは情報が共有されていないことです。役割分担を曖昧にしないためには、情報共有をするための仕組みが必要といえます。
RACIチャートの4つの役割をわかりやすく解説
RACIチャートでは、「Responsible(実行責任)」「Accountable(最終責任)」「Consulted(相談・助言)」「Informed(報告のみ)」の4つの役割を割り当て整理します。
それぞれの役割について確認をしてみましょう。
R(実行責任)
Rは、実際に作業する人です。部品を加工するタスクの場合は加工する人が、製品を検査するタスクの場合は検査する人がRに該当します。
また、同じ作業を複数人で行なう場合は、作業者全員の欄にRを記載します。
ただ、複数人いると責任の所在がわかりにくいことから、責任の代表者を一人だけ選ぶこともあります。
企業によって使い方は異なりますので、事前にチャート作成者が決めておくといいでしょう。
A(最終責任)
Aは、タスク間の責任者です。部門長やチームリーダーなど、担当するタスク全体を統括する人がAに該当します。
また、作業の状況を説明する立場であることから、Aを「説明責任者」と呼ぶこともあります。
当然ですが、最終的な責任者ですので該当者は一人だけです。責任者となりそうな人が複数いる場合は、最も立場が上の人にAを振り分けてください。
最終責任者も作業をする場合は、Rと兼任することもあります。
C(相談・助言)
Cは、タスクの疑問や相談に対応する人です。コンサルタントや熟練者など、タスクのサポートやアドバイスをする人がCに該当します。
主な作業内容は、タスクが成功するためのサポートです。タスクにトラブルが生じた際の解決法や、より効率的に作業を行なうためのアドバイスなど、タスク担当者からの相談に対して回答を行ないます。
そのため、プロジェクトの内容によっては、外部の人が該当することもあります。
また、相談役が多いと誰に相談すればいいのか迷ってしまうため、相談役は基本的に少ない方がいいです。専門が違うなら問題ありませんが、専門が同じ場合は一人に決めておきましょう。
なお、相談役はあくまでも相談役であり、プロジェクトの決定権や実施権はありません。責任もありませんので、プロジェクトが失敗に終わっても責任を押し付けないようにしてください。
I(報告のみ)
Iは、進捗や結果を受ける人です。経営陣や上司など、タスクの報告を受ける人がIに該当します。
Cの相談者とは異なり、Iは報告を受けるだけの人です。Cと兼任することもありますが、基本的には一方的に報告されるだけの相手と思っていいでしょう。
ただ、報告内容に問題がある場合は、報告者である最終責任者に質問や確認などの連絡をすることもあります。
RACIチャートの作り方
RACIチャートの作り方について紹介します。
プロジェクトのタスクを洗い出し
まずは、プロジェクトのタスクをすべて洗い出すことから始めます。実際の流れをイメージしながら、作業内容を明確にしてください。
各タスクを細分化した方が明確にできますが、あまり細分化し過ぎるとチャート図が複雑化しわかりにくくなります。そのため、通しで行なう作業はある程度まとめてもいいでしょう。
洗い出したタスクはプロジェクトの流れに沿って、表の縦軸に記入していきます。
関係者(部署・役割)を並べる
次は、プロジェクトの関係者を並べていきます。参加メンバーの名前を表の横軸に記入をしてください。
また、企業全体で挑むようなプロジェクトの場合は、個人名ではなく部署名で記入をするといいです。営業部や製造部といったように、部署単位でまとめましょう。
ほかにも、マネージャーやリーダーなど役割名で記入するなど、プロジェクトの規模や内容に合わせて変えてください。
R/A/C/I を割り振る
表にタスクと関係者を記入できたら、次は「R(実行責任)」「A(最終責任)」「C(相談・助言)」「I(報告のみ)」をそれぞれ振り分けていきます。
「山田さんは加工を担当するから、加工の欄にRを記入」「木村さんは加工経験者だから、加工の欄にCを記入」といったような感じです。
役割を兼任するような場合は、「R/A」のように「/」を用いて記入しましょう。
また、役割は必ずしもすべて振り分ける必要はありません。担当しないタスクの欄は空欄のままにします。
それぞれを振り分けると、以下のような感じとなります。
| 山田 | 田中 | 佐藤 | 木村 | |
|---|---|---|---|---|
| 加工 | R/A | I | C/I | |
| 組み立て | R | R/A | C/I | |
| 検査 | R/A | I | C/I | |
| 箱詰め | R/A | C/I | ||
| 集計/管理 | R/A |
ダブり・責任抜けをチェック
表が完成したら、内容が合っているかをチェックします。「作業が重複していないか」「A(最終責任)の記入抜けがないか」など、それぞれのタスクで確認しましょう。
特に注意するのはA(最終責任)のダブりです。基本的にAは各タスクで一人だけですので、複数いるようなら一人にしてください。
合意形成して確定
最後に、完成した表をメンバー全員に確認して情報共有をします。表に記された役割に基づき、作業を開始してください。
もし、問題があるようでしたら表を修正します。技術や時間的に作業が難しいといった場合もありますので、作業員の意見も交えて組みなおしましょう。
製造業におけるRACIチャートの活用例
どのような場面でRACIチャートを活用すればいいのか。主な活用例をいくつか紹介します。
新製品開発プロセス
主な活用例として、新製品を開発する際が挙げられます。プロジェクトをスムーズに遂行するため、設計、試作、製造、品質管理などの各段階で、誰が実行し誰が最終責任者かを明確にします。
責任者がわかれば、各タスク間での連携も取りやすくなります。リアルタイムに情報共有を行なえるようになり、スムーズにプロセスを進行できるでしょう。
生産ラインの改善
生産ラインを改善する際にも、RACIチャートは活用できます。担当者、承認者、アドバイスをする技術者、進捗を報告する関係者などを整理することで、各タスク間の意思決定を迅速に行なえます。
生産ラインの改善においても、意思疎通は重要な要素です。情報共有が不十分だと問題点がわからず改善が進みません。改善場所を特定するためにも、充分なコミュニケーションが必要といえます。
また、情報共有を強化することは、生産性を向上させることにもつながります。円滑な情報共有によって、生産効率が向上するでしょう。
生産ラインの改善に必要なことは、生産現場を知ることです。生産状況を確認するためにも、責任者や担当者を把握する必要があります。
サプライヤー管理
サプライヤーの管理にも、RACIチャートを活用可能です。調達担当者、承認責任者、関連部署、供給元への連絡先などを明確にすることで、調達戦略に役立ちます。
例えば、コスト削減をするために資材管理を見直すとします。その際、相談先となるのが調達担当者や営業担当者です。RACIチャートによって担当者がわかっていればすぐに連絡を取って、資材変更の相談ができます。
サプライヤーとの連携を強化するためにも、RACIチャートによる管理は必要となります。
注意点・デメリット
責任の所在が一目でわかるRACIチャートですが、使用においての注意点もあります。
使い方によっては逆に現場を混乱させてしまう可能性もありますので、使い方に注意してください。
過度に複雑にすると運用できない
RACIチャートは、過度に記入をすると表が複雑化しわかりにくくなります。「誰が責任者なのか」や「誰に相談すればいいのか」などで迷ってしまい、RACIチャートの意味がなくなってしまいます。
また、記入する文字が「R」「A」「C」「I」の4つだけなのもわかりにくくする理由です。RACIチャートに慣れていないと、どれがどの役割なのか混乱してしまいます。
誰が見てもすぐに理解できるよう、シンプルにまとめることを心がけてください。
A(最終責任)が複数になると混乱を招く
Aの選定は、各タスクで一人だけにしてください。「最終責任」というように、Aはそのタスクの統括を行なう存在です。Aが複数いてしまうと、誰に責任があるのかがわからなくなってしまいます。
責任の所在を追求できるよう、Aは必ず一人だけを選出しましょう。
RとAの混同
RACIチャートを作成する際は、RとAが混同しないよう注意してください。Rは作業者、Aは責任者といったように、それぞれ該当する人が異なります。
責任者が、作業者に指示を出すだけのケースも珍しくはありません。そのような場合は、責任者はAのみの記入となります。
RとAを兼任する場合も多いですが、作業者が必ずしも責任者を兼任しているわけではないことを知っておきましょう。
RACIを担わないメンバーの役割は可視化できない
RACIチャートには、RACI以外の役割を可視化できないデメリットもあります。RACIチャートで記入するのは「R」「A」「C」「I」の4つの役割のみであり、それら以外の役割は記入しません。
そのため、それ以外の役割がある場合は、別に注釈や補足資料を用意し、作業内容を知らせる必要があります。
プロジェクトの規模が大きくなると、役割も多くなりがちです。役割が複雑化しそうな場合は、別の方法で管理することも検討してください。
定期的な更新をしないと古い情報が残る
プロジェクトによっては、RACIチャートを定期的に更新する必要もあります。タスクが変更した際には責任者も変わるため、変更内容に合わせて表を変更する必要があるからです。
古い情報のままでは、間違った相手と連携を取ってしまいます。もちろん、間違った相手とでは正しい生産が行なえず、現場が混乱してしまうでしょう。
現場を混乱させないためにも、タスクの修正が行なわれるたびに、RACIチャートも更新してください。
RACIチャートの類似のフレームワーク
RACIチャートと同じく「役割の明確化」を目的としながらも、より細かい責任区分や意思決定プロセスを整理するために活用されるフレームワークがあります。
プロジェクトの複雑さや組織文化に応じて、RACIだけでなくこれらの拡張版を使い分けることで、より精緻な役割定義が可能になります。
RASIC/RASCI
RACIチャートと同じく、役割を明確化するためのフレームワークとして「RASIC」や「RASCI」と呼ばれる拡張版モデルがあります。
RACIの構造に「Support(支援者)」などの役割を追加し、より細やかな責任分担を整理できるようにした形式です。
現場によっては「C」を「Control(統制者)」の意味で用い、品質チェックや承認プロセスの監督など、成果物の妥当性を担保する役割として位置づけるケースもあります。
監査やコンプライアンスが重視される業務で役立ち、プロセス全体の整合性やリスク管理を強化できます。
ただし、文献や組織によって表記や定義が揺れやすく、RASIC と RASCI を別物として扱わない方が混乱が少ないため、本記事ではまとめて紹介します。
※RASIC/RASCI は組織によって定義が異なることがあるため、導入時は自社で意味づけを統一しておくことが重要です。
DACI
DACIは、議論や意思決定に特化した役割分担フレームワークで、主に「Decision Maker(意思決定者)」を中心にプロジェクトを推進します。
RACIとは異なり、議論をリードする責任者(Driver)、専門的な意見を提供するアドバイザー(Advisor)、意思決定を受け取るインフォームド(Informed)など、意思決定プロセスに重要な役割を明確化できます。
議題ごとに素早く合意形成したいケースで効果を発揮します。
まとめ:役割の見える化が現場改善の第一歩
RACIチャートは、それぞれの役割を見える化するためのツールです。それぞれの役割を表にまとめることで、誰がどの役割なのかを一目でわかるようにします。
役割の見える化は、スムーズな情報共有をするために必要な要素です。誰がどの役割なのかがわかれば、相談や連絡がしやすくなります。
より連携を強化するためにも、RACIチャートによってそれぞれの役割を把握しておきましょう。