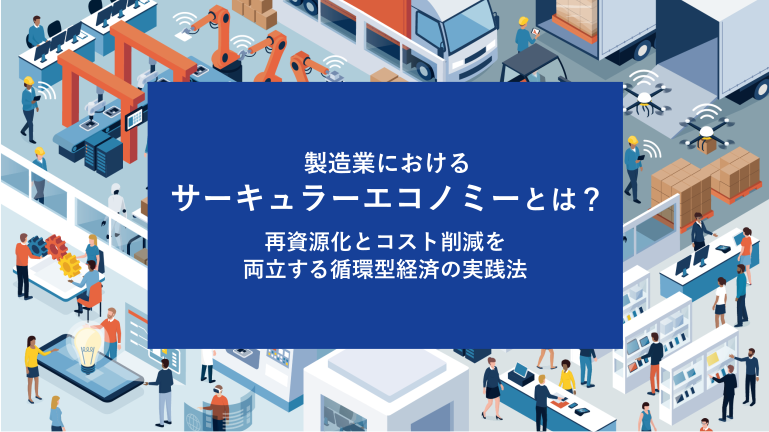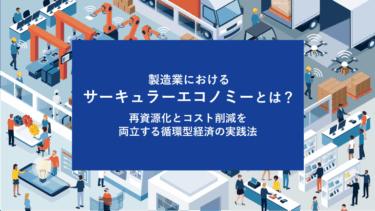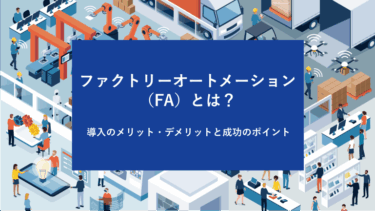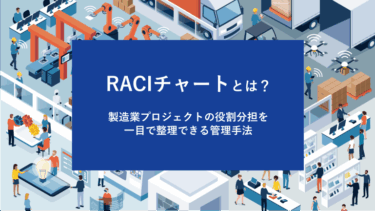近年、世界的に問題視されている環境汚染。このまま“使い捨ての経済”を続けていて、本当に未来は守れるのでしょうか?温暖化やそれに伴う海面上昇など、地球環境の悪化は年々深刻化しています。
サーキュラーエコノミーは、環境負荷の低減を目指す取り組みの一つで、資源の循環や廃棄物の最小化を重視します。
これ以上地球環境を悪化させないためにも、2020年3月11日にEUが「新循環型経済行動計画(CEAP)」を公表しました。さらに2024年7月18日には「ESPR」が施行され、製品の設計段階から循環性を高める枠組みが動き出しています。各国でも同様の取り組みが広がっています。
サーキュラーエコノミーとはどのような活動内容なのか。必要とされる理由や実施の進め方など、サーキュラーエコノミーについて紹介します。
サーキュラーエコノミーとは?
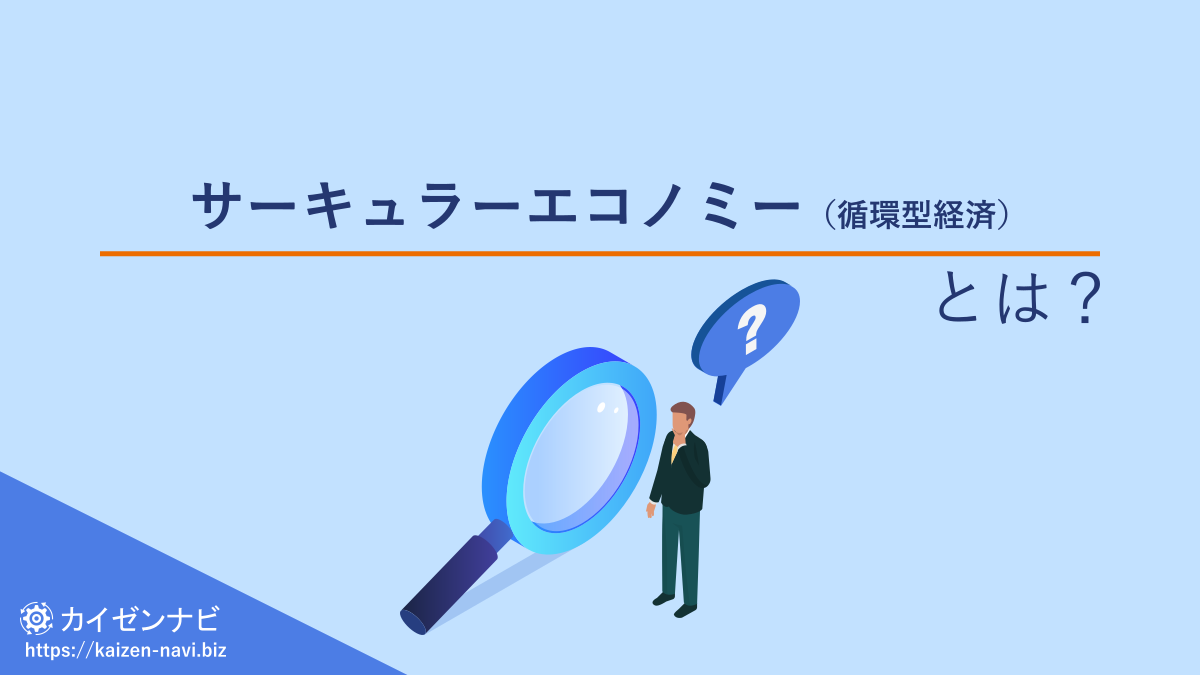
サーキュラーエコノミーとは、モノを循環させる仕組みのことです。日本語では「循環経済」や「循環型経済」と訳され、廃棄や汚染を極力発生させず、資源を持続的に活用する経済モデルを指します。環境負荷の低減を目指し、世界各国でその導入が進められています。
資源を再利用するという点ではリデュースやリサイクルと共通していますが、サーキュラーエコノミーは、そもそも廃棄物が出ないように設計段階から工夫する点が特徴です。リサイクルは出た廃棄物への対応が中心である一方、リデュースは発生抑制(上流対策)を目的としており、サーキュラーエコノミーとも高い親和性を持ちます。
日本では、サーキュラーエコノミーの実現を目指す方針として「循環経済ビジョン2020」が発表されました。大まかな内容としては「3R(リデュース、リユース、リサイクル)から循環型経済への転換を目指す」ものであり、よりエコノミーに力を入れた方針となっています。
また、国際的な支援団体として「エレン・マッカーサー財団」も存在しており、日本だけではなく、世界的にサーキュラーエコノミーによる取り組みが行なわれています。
リニアエコノミー(直線型経済)との違い
リニアエコノミーとは、直線型に資源を消費する仕組みのことです。生産、消費、廃棄を一つの流れとし、大量に消費をして廃棄することで経済を回します。
当然ですが、廃棄したモノはゴミであり、改めて使われることはありません。焼却処分などはありますが、処理をしないとゴミは溜まる一方といえるでしょう。
一方で、サーキュラーエコノミーは資源を循環させる仕組みです。生産から消費する流れは同じですが、廃棄するのではなく生産に再利用されます。
資源が循環するのが特徴であり、使用済みの資源がゴミとして破棄されにくいです。最終的なゴミの量が少ないことで、ゴミが溜まりにくくなっています。
ゴミ処理問題の深刻化
近年は、ゴミの処理も課題とされています。経済が回ることは良いことですが、生産に伴い廃棄される量も増えているからです。海洋プラスチック問題やコンビニの食料品廃棄問題など、耳にしたことのある人も多いでしょう。
ゴミが増えれば処理する量も増加し、その結果として温室効果ガスの排出量も増加します。埋立地の確保が難しくなる地域もあり、地域によっては最終処分場の逼迫が課題とされています。こうした背景からも、サーキュラーエコノミーによる廃棄物削減の取り組みが重要になっています。
リニアエコノミーのままでは、将来的に世界経済が立ちいかなくなる可能性があります。そのような事態にしないためにも、サーキュラーエコノミーへの切り替えが必要なのです。
製造業に求められる「循環」の考え方
製造業における循環とは、資源を使いまわすことにあります。ただ資源を消費して生産をするのではなく、資源を効率よく循環させることで経済を循環させます。
従来の製造では、資材を消費し経済を回すことが一般的でした。大量生産によって大量消費が促進され、企業の利益となります。しかし、その考えでは大量廃棄へとつながってしまい、結果として環境汚染を深刻化させます。エネルギー消費も激しくなることで、温室効果ガスも大量に排出してしまうでしょう。
そのため、製造業界では資源の消費を抑えた新しい製造が求められます。世界的な課題に向き合うためにも、サーキュラーエコノミーに適したビジネスモデルへの変更が必要です。
SDGsの12番目「つくる責任・つかう責任」との関係
近年注目されるSDGsですが、目標の12番目に「つくる責任・つかう責任」を掲げています。簡単に説明すると、「考えて消費をすること」であり、「ムダに作って廃棄をしないためにも、必要な分だけ作って必要な分だけ使うようにしましょう」といった意味があります。
中でも、12.5番目に記された内容「2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する」は、サーキュラーエコノミーに通ずるものがあります。
そのことから、SDGsの実現に、サーキュラーエコノミーは効果的といえるでしょう。
ほかにも、目標の9番目である「産業と技術革新の基盤をつくろう」や目標の13番目である「気候変動に具体的な対策を」など、SDGsにはサーキュラーエコノミーに関係する項目が多いです。
2015年の国連サミットにおいて、新しくSDGsが採択されました。世界の問題を解決するための取り組みであり、現在の問題解決はもちろん、将来への禍根を残さないためにも、取り組みが必要とされます。 SDGsを成功させるためには、国[…]
- 参考サイト
- SDGsジャパン「目標12のターゲット・実施手段と指標」/参照日:2025年11月10日時点
- SDGsジャパン「目標9のターゲット・実施手段と指標」/参照日:2025年11月10日時点
- SDGsジャパン「目標13のターゲット・実施手段と指標」/参照日:2025年11月10日時点
なぜ今、製造業で注目されているのか
近年注目されている理由には、以下のようなことが挙げられます。
資源価格高騰・脱炭素経営・法規制
サーキュラーエコノミーが注目されている理由は、資源価格が高騰しているからです。近年は戦争や円安などの影響により物価高が続いており、それに伴い生産コストも上がっています。生産コストを少しでも抑えるため、再利用可能な資源や仕組みに注目が集まっているわけです。
また、環境保全の観点からも、サーキュラーエコノミーは注目されています。地球温暖化を防ぐための取り組みとして、近年は脱炭素経営が推奨されています。
特に、製造業は温室効果ガスの排出量が多い業界です。国内総排出量のうち約35%が産業部門からの排出ともいわれており、すべての企業において将来的な排出量の減少が目指されています。
ほかにも、2022年に施行されたプラスチック資源循環法を始めとした法規制によって生産の見直しが必要になるなど、さまざまな理由からサーキュラーエコノミーへの注目が高まっています。
製品ライフサイクル全体での最適化の必要性
サーキュラーエコノミーが注目されるのに伴い、製品ライフサイクル全体の見直しもされるようになりました。製品ライフサイクルとは、製品が登場してから衰退するまでの推移を示す概念のことであり、大まかに言えば「売れ行き」や「製品知名度」を意味します。
製品ライフサイクルは、主に「導入期」「成長期」「成熟期」「衰退期」の四段階によって構成されます。製品が認知されるのが導入期であり、売れ行きが伸び、注目を集めるのが成長期です。そして、売れ行きが頭打ちとなるのが成熟期であり、売れ行きが低下するのが衰退期となっています。
当然ですが、衰退期に製品を大量に作っても、製品を売るのは難しいです。大量に作ったとしても、売れ行きが悪いことで多くの製品は廃棄されてしまうでしょう。製品の廃棄はゴミを出すことにつながり、SDGsの取り組みに反することとなります。
そのため、ゴミを出さないための見直しが必要といえます。「衰退期になるにつれて生産数を減らす」といったように、それぞれの期に合わせた生産を行なうことで、ゴミになる可能性を減らすことができるのです。
SDGsを実現させるためにも、製品ライフサイクル全体での最適化が必要といえるでしょう。
製造業でのサーキュラーエコノミー実践事例
では実際に、製造業界におけるサーキュラーエコノミーの取り組みについて確認してみましょう。
経済産業省が公開する資料の中から、いくつか紹介していきます。
- 参考サイト
- 経済産業省 関東経済産業省「管内自治体・企業におけるサーキュラーエコノミーの取組事例」/参照日:2025年11月10日時点
- 経済産業省 環境省「循環型の事業活動の類型について」/参照日:2025年11月10日時点
再利用の事例(経産局掲載企業の取り組み紹介)
「株式会社yuni」では、使用済み寝具から素材を再利用しています。回収した寝具を自社工場で分解・洗浄・滅菌をし、取り出された資材を使って新しい寝具を作るのです。
ほかにも、「協栄産業株式会社」では使用済みペットボトルをリサイクルして樹脂資源にするなど、使用済みの資材を再利用することで、サーキュラーエコノミーの取り組みに貢献しています。
また、「株式会社ごみの学校」ではリサイクルやサーキュラーエコノミーの活動をカードゲームに落とし込み、子供でも楽しみながら学べる環境を整えています。
埼玉県ではサーキュラーエコノミーの活動を実施する企業に対して補助金を支援するなど、間接的にサーキュラーエコノミーを補助する取り組みも行なわれています。
製造プロセスの最適化(環境省資料よりトヨタ・日本製鉄の例)
再利用の工夫だけでなく、設計段階から再利用を前提とした工夫も進められています。
トヨタ自動車では、ワイヤーハーネスにプルタブ式アース端子部を採用しています。プルタブ式によりパーツの取り外しが容易になり、再利用性が向上します。
また、日本製鉄では軽量鋼材である「ハイテン(高張力鋼)」を開発しています。ハイテン材を使った車は燃費が良く、従来の車と比較してエネルギー消費が少ないです。排気ガスの排出量も少なくなることで、循環型経済への取り組みに貢献しています。
ほかにも、ダイキン工業では入れ替え式の基板などメンテナンス性を高める設計を導入。長寿命化への寄与は製品や運用によって差があるため、個別評価が必要です。
サーキュラー化を進めるためのステップ
サーキュラーエコノミーは今後必要となる取り組みです。世界的にも推進がされており、製造業界はもちろん、すべての業界・企業で求められています。
自社でも取り組みが行なえるよう、進め方についても確認しておきましょう。
現状把握(廃棄物・エネルギー使用量の見える化)
まずは、自社の現状を把握することから始めます。生産に使われる資源量や生産工程などを確認し、どのように消費されているのかなどを確認してください。特に、消費エネルギーなどは目に見えにくい項目です。グラフなどにまとめ、わかりやすいよう視覚化すると良いでしょう。
また、製品によって、廃棄量や消費量は異なります。それぞれの影響をまとめ、影響の大きい製品から対応できるようにしてみてください。
改善活動とデジタルツールの導入
現状がまとまったら、改善案を立案します。企業での取り組みとして「破材を集め加工企業に売却する」、自分たちでできる取り組みとして「再生資源を使う」や「詰め替え可能な製品を開発する」など、チームで話し合っていろいろ提案してみてください。
改善案が決まったら、実際に試してみます。そして、問題がないようなら正式な導入として業務に組み込んでいきましょう。
また、サーキュラーエコノミーの実施に向けて、デジタルツールの導入も検討してみてください。「生産をデジタル管理すれば消費を少なくした効率的な管理が行なえる」といったように、より効果的にサーキュラーエコノミーが実施できます。
ほかにも、デジタルツインを使えば「試しで生産をする必要がなく検証が行なえる」など、便利なデジタルツールは多く、効率よく取り組みが行なえるようになります。
サプライチェーン全体の連携強化
改善活動が定着したら、他部門との連携にも注目してみましょう。「営業部門との連携を強化することで必要な分だけを生産でき、ムダな生産を減らすことができる」といったように、連携の強化はサーキュラーエコノミーの実施につながります。
ほかにも、「連携を強化すれば業務が効率化されエネルギー消費量を減らせる」など、サーキュラーエコノミーの取り組みにサプライチェーン全体の連携強化は効果的です。
また、サーキュラーエコノミーは企業全体で実施すべき取り組みです。事務部門では書類に使われた紙が、梱包部門ではフィルムやテープが毎日のように廃棄されています。
生産部門だけが取り組むのではなく、他部門でも活動を見直し、企業全体で取り組むようにしましょう。
まとめ:サーキュラーエコノミーは「コスト削減×ブランド価値向上」の両立策
サーキュラーエコノミーとは、資源を循環させ、廃棄を少なくする取り組みのことです。従来のリデュースやリサイクルのように廃棄されるのを前提とするのではなく、廃棄そのものを減らすことで、環境汚染を防ぐことを目的とします。
環境汚染は、全人類の課題といっても過言ではありません。未来の自然を守るためにも、今後は生産のあり方を見直す必要があるでしょう。
また、サーキュラーエコノミーは環境だけではなく、企業にとってもメリットとなります。資源の再利用やエネルギーの消費軽減が行なえればコスト削減になりますし、世界的に推進されていることから、取り組む姿勢はブランドの価値を高めることにつながります。
環境はもちろん企業の未来を守るためにも、サーキュラーエコノミーを意識してみてください。