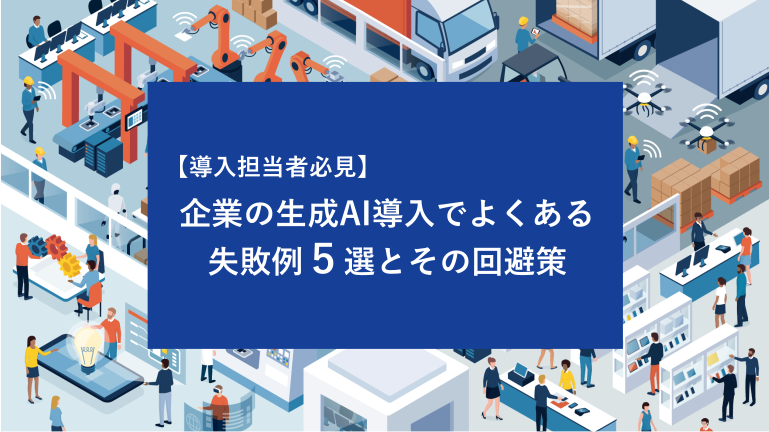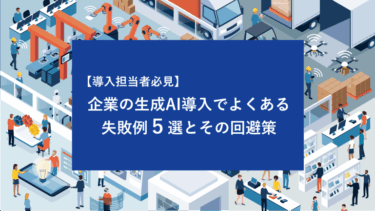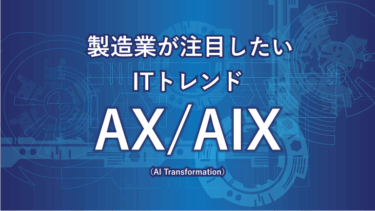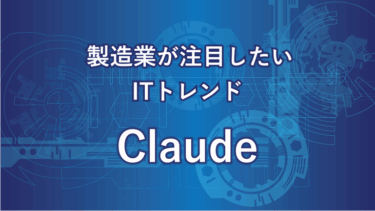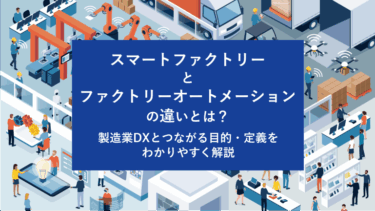自動化によって業務サポートをしてくれる生成AI。業務効率の改善やコスト削減が期待できることから、生成AIの導入を検討する企業は近年増え続けています。
しかし、生成AIを導入すれば必ずしも業務が向上するわけではありません。場合によっては業務や企業の負担となる場合もあります。
生成AIの導入に失敗しないためにも、失敗する原因を理解し、失敗しないための対策と準備を行なう必要があるでしょう。
どのようなことが失敗の原因となるのか。失敗例や失敗しないためのチェックポイントなどを紹介します。
なぜ今、企業に生成AI導入が求められているのか?
そもそもなぜ、生成AIが注目されているのでしょうか?
生成AIの導入が求められている理由には、以下のようなことが挙げられています。
業務効率・生産性の大幅な向上
生成AIが求められる理由は、業務効率を向上させるためです。集計結果の自動入力やスケジュール調整など、AIが業務をサポートすることで業務時間を大幅に短縮できます。
AIサポートによって手すきとなれば、その分の時間を別の業務に費やせます。簡単だけど手間がかかる業務をAIに、応用力が必要な業務を人間が担当することで、効率よく生産を進められるでしょう。
特に、近年は顧客ニーズの変化が激しく、市場情報も激変しがちです。人の手で地道に市場調査しているようでは、変化に対応できなくなります。
ニーズに合わせた製品展開をしていくためにも、AIによる情報収集やニーズ予測が必要です。
コスト削減・人手不足の対策としての期待
コスト削減や人手不足の解消が期待できる点も、AIが期待される理由です。AIによって業務効率が向上することにより、従来よりもリソースを少なくして生産が行なえます。
近年は、どの業界でも人手不足が懸念されています。作業員が足りないことから、業務を減らす企業も少なくありません。そのような場合でも、AIで労働力を確保すれば、人手不足を補うことができます。
コスト削減や人手不足の解消は、どの企業も直面する大きな課題です。企業の成長を目指すためにも、課題への取り組みが必要といえるでしょう。
ChatGPTなど生成AIの急速な普及
AIが普及したことも、AIが期待される理由の一つです。ChatGPTなどの生成AIの登場により、業務での活用が現実的になってきました。
今までは、AIといえば最先端の技術といった認識が一般的でした。未来の技術であることから、手の届かない技術と思った人も多かったことでしょう。しかし、無料で誰でも使える生成AIが登場したことで認識が一変します。誰でも簡単に生成AIが使えることで、AIは身近な存在となったのです。
「AX(AIトランスフォーメーション)」とは、AIを軸にした業務変革を意味する言葉で、DX(デジタルトランスフォーメーション)に続く次のフェーズとされています。
時代に合わせた取り組みとして、AIへの注目が高まっているわけです。
デジタル技術によって新しい働き方を目指すDX(Digital Transformation)。デジタルへの移行は業務効率を大きく向上させることから、多くの企業がDXに興味を持ち、デジタル化への移行に取り組んでいます。 そんなD[…]
経営層からのトップダウン指示が多い傾向
現場ではなく、経営層が導入を求める場合もあります。AIの導入は業務を大きく改善し、利益を向上させるものです。企業をより良く成長させるため、経営層から現場へAIの導入を催促します。
特に、近年はDXへの取り組みが進められる時代です。時代に合わせた経営にするため、経営層からの指示も多くなるでしょう。
経営戦略の一環として、AIが注目され導入が求められています。
【導入前に知っておくべき】生成AI導入でよくある失敗例5選
AIを導入することで、業務効率は大きく改善されます。コスト削減や人手不足の解消といった課題の対策にもなり、今後は生成AIの利用が重要になってくるでしょう。
しかし、考えなしに導入しても望む結果は得られません。場合によってはAIの導入が負担となり、業務や経営を圧迫する要因にもなってしまいます。
導入に失敗しないためにも、失敗例について学ぶ必要があるでしょう。
ツール導入が目的化し、業務課題と紐づいていない
失敗例:
『「使い道は導入してから考えればいいや」と導入をしたが、導入した後の使い道に困り、AIを持て余してしまった』
導入目的を決めないまま導入した場合の失敗例です。AIを導入したものの、使用目的が不明瞭であることでAIを持て余してしまいます。
もちろん、AIの使い道はいろいろあるため、後からでも業務に活かすことは可能です。しかし、「AIのために仕事を探す」こととなってしまい、導入が本末転倒になってしまうでしょう。
AI導入は目的ではなく手段です。業務改善という明確な目的を持つことが重要です。
AIを導入する際は、「なぜAIが必要なのか」「AIを導入するとどのように変わるのか」などをしっかり考えることが大切です。
データ活用・セキュリティ体制が未整備
失敗例:
『AIを導入したものの、学習が必要なことを知った。学習データを用意しておらず、AIが未熟なままなことで業務利用ができなかった』
学習データの準備に問題がある場合の失敗例です。学習データの不備により、AIが育たず業務に活用ができません。
AIは、初めから何でもできるわけではなく、学習させて育てる必要があります。しかし、学習データに問題があると、AIの学習は進まず成果を上げられません。場合によっては間違った内容を学んでしまい、使い物にならなくなってしまうでしょう。
AIを導入する際は、AIを育てるためのしっかりしたデータを用意する必要があります。
また、社内環境の整備も必要です。パソコンやサーバーのスペックが低すぎると、AIの稼働を阻害してしまいます。問題なく動かすためにも、動作水準を満たした動作環境を整えてください。
AIに過度な期待をしてしまう
失敗例:
『「AIを導入すれば業務が楽になる」と思っていたが、思ったよりも楽にならなかった。むしろ、AI学習などの業務が増えた』
AIに期待しすぎた場合の失敗例です。AIを過信しすぎるあまり、何でもAIに任せようとして失敗してしまいます。
AIに詳しくない人だと、「AIは何でもできる」ものと勘違いしがちです。自動で業務を進めてくれるのなら、すべてAIに任せて楽をしようと思うことでしょう。
しかし、実際には何でもできるわけではありません。AIは計算や分析などは得意でも、応用力が必要な業務は苦手とするからです。全くできないわけではありませんが、人が作業をする方が効率よく終わる場合もあります。
また、AIは育てる手間もあります。学習データを用意するのはもちろん、処理方法の具体的なフィードバックも必要です。さらに、AIと正しく付き合うためにAIの知識も必要だったりと、実用までには時間がかかるでしょう。
AIの導入によってできることは広がりますが、何でもできるわけではありません。学習したことしかできず、学習には時間やコストがかかります。「AIで全部やろう」と考えて適用範囲を広げすぎると、どれも中途半端となりがちです。時間やコストは有限ですので、目的を絞って利用するようにしてください。
情報漏洩・セキュリティ対策不備
失敗例:
『個人情報を入力した結果、AIが学習をしてしまい、別で利用した際に個人情報を出力してしまった』
セキュリティ対策が不十分だった場合の失敗例です。機密情報をAIが学習してしまったことで、情報漏洩をしてしまいます。
特に、ChatGPTのような不特定多数が使う生成AIは情報漏洩がしやすいです。学習データを同じクラウドサーバーに保存しているため、別のアドレスから質問をしても答えてしまいます。
また、管理会社から漏洩するリスクもあります。管理会社がハッキングされることで、AIが学習したデータがそのまま抜き取られてしまうでしょう。
情報漏洩をさせないためには、機密情報を入力しないことが大切です。そして、入力をさせないためにも、従業員のネットリテラシーを育てる必要があります。
担当者・人材/体制不足
失敗例:
『AIを導入したが、扱える人がおらず、AIを持て余してしまった』
AI人材が不足している場合の失敗例です。AI人材がいないことで使い方がわからず、担当者が決まらないことで、そのまま持て余してしまいます。
AIは、「指示をすれば勝手に業務をしてくれる」わけではありません。ほかの機械やツールと同じように、人間が操作をすることで作業を開始してくれます。そのため、AIの使い方がわからないと、業務に活かすことはできません。無理に活かそうとしても、操作に手間取り業務が長引くだけではなく、間違った結果を出してしまうでしょう。
また、AI学習にも利用者の知識が必要です。知識がないまま育てようとしても、効率よく育たないばかりか、間違ったデータまで学習してしまいます。
AIを正しく活用するためには、AIに精通した担当者が必要です。そして、誰もがAI担当者になれるよう、研修や運用マニュアルなどの社内制度を充実させる必要があります。
生成AI導入失敗を回避するためのチェックリスト
AIを導入する際は、AIを迎えるための準備が必要です。充分な準備ができていない状態で導入をしても、AIを業務に活かせません。
では、どのような部分に注意して導入を進めればいいのでしょうか?
導入目的・課題の明確化
AIを持て余さないためにも、導入する際は目的を明確にしてください。具体的な目的がないまま導入をしてしまうと、AIの使い道が見つからず、AIを導入する意味がなくなってしまいます。
「○○が問題だから業務を自動化したい」といったように、目的を明確にしておけば導入後にAIを持て余す心配はありません。どのように業務が変化するかまで予想できれば、AIの結果に落胆することもないでしょう。
導入の目的に限らず、AIを導入する際はしっかりとした導入プランを用意したうえで取り組みを進めてください。
業務フローと現場ニーズの把握
生産現場を混乱させないためにも、現場の声をしっかり確認してください。勝手に導入を進めてしまうと、変化に対応できず現場が混乱してしまいます。
自動化すれば業務が楽になるのは確かですが、すべての業務で必要になるとは限りません。生産プロセスが既にできており、何も不自由がなければ導入する必要がないからです。そのような生産プロセスの中で無理にAIを導入しても、プロセスに無理が生じて別の問題が発生してしまうでしょう。
AIはあくまでも便利ツールの一つであり、ツールを使うのは現場で働く作業員です。導入が必要かどうかは、それぞれの現場の意見をしっかり聞くことが重要です。
もちろん、管理側から改善の提案をしてもいいです。現状は問題なくても、話しを聞いて考えが変わることもあります。なんにせよ、管理側だけで導入を進めるのではなく、現場側としっかり話し合って決めることが大切です。
データと環境整備
AIを育てるためにも、質の良い学習データをしっかり揃えてください。データが少ないとAIは育たず、業務利用までの時間がかかってしまいます。
過去数年分の自社データだけではなく、政府機関が発表したデータや海外の最新情報など、さまざまなデータを用意しておきましょう。
また、AIの学習準備だけではなく、環境づくりも行なっていきます。最新のパソコンへの新調やサーバーの準備、AI人材の育成制度など、必要なことを準備してからAI導入を行なってください。
ツール選定とシステム検証
目的に合わせて使えるよう、ツール選びはしっかり行なってください。生成AIごとに特徴がことなるため、適性が低いAIを選んでしまうと、思ったような効果が得られなくなります。
個人情報も扱うならセキュリティが高いAIツール、マニュアル作成に使うなら画像やグラフも作れるAIツール、メールに使うなら言い回しが自然なAIツールといったように、目的に合うツールを選ぶと不自由なく利用できます。
また、社内システムとの相性も大切です。ツールによっては、規格が違うことで既存のシステムと併用できないものもあります。特に、海外で開発されたツールは合わない場合が多く、本格的な導入の前に確認しておく必要があるでしょう。
「購入したけど使えなかった」では、ムダな出費となってしまいます。相性が合わない場合も考慮して、無料でお試しができるツールから試してみるといいです。
人材・運用体制の準備
AIが使えないといったことがないよう、AI人材の育成も行なってください。AI人材がいないと、AIが使えないどころかAIの育成も満足にできなくなります。
また、AI担当者が一人いればいいわけではありません。担当が一人だけだと業務が属人化してしまい、他の人が担当になれません。
研修やマニュアルを用意することでAI人材を育て、透明性のある運用体制にすることで属人化を防ぐようにしましょう。
セキュリティ・ガバナンス
情報漏洩を防ぐためにも、セキュリティ対策を行なってください。情報漏洩は企業の信用を落とすことから、絶対に防がなければなりません。
最新のウイルス対策ソフトを導入し、外部から不正アクセスされないよう対策を取りましょう。特に、海外サイトを経由する場合は注意が必要です。利用するAIがどこの国のものなのかも、意識してみてください。
また、従業員のセキュリティ意識も育てる必要があります。セキュリティ意識が低いままでは、考えなしに機密情報をAIに学習させてしまいます。
機密情報を守るためにも、セキュリティ意識の高い管理を行なってください。
効果検証と継続的な改善
継続的な改善ができるよう、環境や体制を整えてください。継続的な体制ができていないと、時代に合わせて企業が成長できません。
近年は、市場情報が激しい時代です。顧客ニーズも変化しやすく、変化に合わせた生産体制が求められています。変化に合わせて改善するためにも、定期的に業務内容や現場を見直す必要があるでしょう。
長期的な改善を目指す方法としてPDCAと呼ばれるフレームワークも存在します。簡単に説明すると、「計画(P)」「実行(D)」「評価(C)」「改善(A)」を繰り返し行なう方法であり、繰り返し行なうことで前の結果にプラスして結果が良くなっていきます。有名な改善方法ですので、ぜひ参考にしてみてください。
成功企業の共通点とは?現実的な生成AI導入ステップ
生成AIの導入は、段階を踏むことが大切です。導入にはさまざなことが必要ですが、一度に進めても、やることが多くて手が回らなくなってしまいます。中途半端な取り組みにしないよう、一つずつ課題を進めていきましょう。
基本的な流れとしては、「目的の定義」「業務適用」「ルールの選定」「社内教育」「適応の拡張」の順に進めていきます。
- 目的の定義:どのようにAIを使うのかを定義する
- 業務適用:AIを導入し、小規模な範囲で利用してみる
- ルールの選定:AIを使う際のルールや規則を決める
- 社内教育:AI知識やルールを作業員に伝授する
- 適応の拡張:より広い範囲で利用をする
目的の定義は、導入目的を明確にすることです。なぜ必要なのかを明確にし、導入プランを決めていきます。
業務適用は、試験導入してみることです。小規模な範囲で利用してみて、どのような結果となるかを検証します。報告書の作成やスケジュールの調整など、別の業務で使い勝手を確認してみるのもいいでしょう。
ルールの選定は、使用する際の決まり事を決めることです。業務適用で得た結果を基に、安全に使うためのルールを決めていきます。
社内教育は、使い方を作業員に教えることです。AIの使い方はもちろん、使用上のルールやネットリテラシーなども含めて、AI人材の育成を進めましょう。
適応の拡張は、業務適用の範囲を広げることです。1ラインだけで適用していたのをすべてのラインで適用するといったように、利用範囲を広げていきます。
もちろん、紹介したステップは一つの方法であり、絶対ではありません。とはいえ、一つずつ取り組むことは大切ですので、参考にしてみてください。
また、現場を巻き込むことも重要な要素です。実際に使用する人の意見を蔑ろにするようでは、生産はうまくいきません。「現場を巻き込むコミュニケーション設計」を指標とし、現場とよく話し合って、導入を進めてみましょう。
まとめ:生成AI導入は「目的と現場起点」がカギ
導入に失敗する主な原因は、管理者主体でプロジェクトを進めているからです。管理者側と現場側の認識にズレが生じることで、導入してもうまくいかず失敗をしてしまいます。
管理者側だけがAI導入に尽力しても、AIを使う現場側の理解や熱量がないと業務に結びつきません。導入を成功させるためには、管理側と現場側の両方が協力し合い、同じ考えを持って取り組むことが大切といえます。
また、目的を持って導入を進めることも大切です。AIを導入する理由は業務改善をするからであり、AIを導入すること自体が目的ではありません。ツール選定より「なぜ・誰のために使うか」が重要といえるでしょう。
失敗例を参考に対策を取り、成功パターンを再現してみてください。そして、段々と導入先を拡張し、社内全体にAIを浸透させていきましょう。