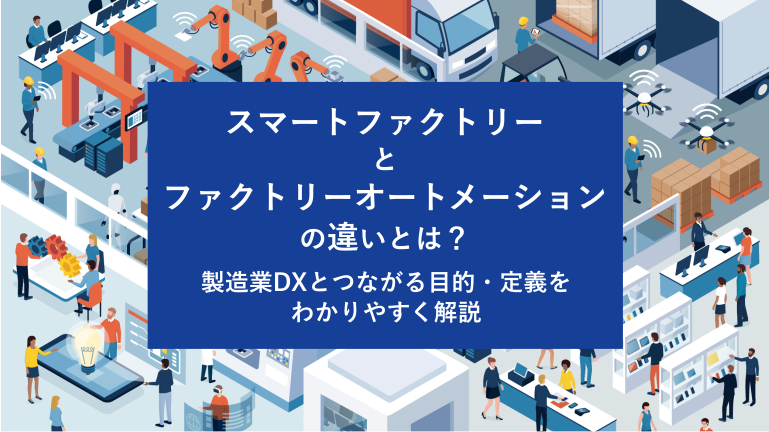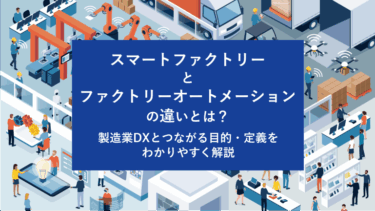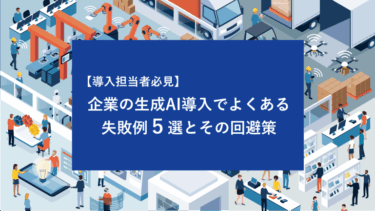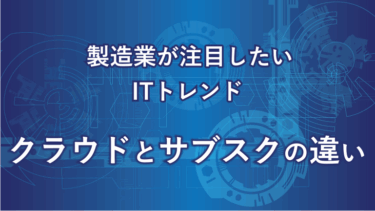近年取り組みが進められる工場のデジタル化。デジタル技術による最適化された工場のことをスマートファクトリーと呼び、DXが目指す変革の一環として世界的に浸透しつつあります。
工場の自動化やデジタル化を進めたいけれど、「スマートファクトリー」と「ファクトリーオートメーション(以下、FA)」の違いがよく分からない――。そんな声は製造現場で少なくありません。
この記事では、両者の定義と違いをわかりやすく整理し、中小企業でも実践できる導入ステップと注意点まで解説します。読めば、自社に合った自動化の第一歩が明確になります。
デジタル化による取り組みを正しく進めるためにも、それぞれの違いについて知っておく必要があるでしょう。
スマートファクトリーとFAは何が違うのか?それぞれの定義や違いについて紹介します。
スマートファクトリーとは?
そもそも、スマートファクトリーとはどのようなモノなのでしょうか?FAとの違いを確認する前に、定義や目的などを確認してみてください。
スマートファクトリーの定義
スマートファクトリーとは、デジタル技術によって生産体制を自動化するだけでなく、工場全体の生産性や品質、稼働効率を最適化する次世代型の工場のことです。
IoTやAI、ビッグデータ解析などを活用し、設備やシステムを相互につなげることで、現場全体が連携しながら柔軟かつ効率的に稼働できる仕組みを実現します。
ほかにも、作業用ロボットの導入やARシステムを使用した在庫管理なども、スマートファクトリーの一環といえます。
導入の目的と得られるメリット
スマートファクトリーを導入する目的は、自動化による生産体制の変革です。自動化によって安定した生産が可能となり、生産数や品質を高く保ちやすくなります。
ヒューマンエラーも減ることで、不良品の発生や入力ミスといった生産トラブルを防ぐこともできるでしょう。
また、自動化によって人材不足も解消されます。近年は労働人口の減少によりどの企業も人材確保が課題となっていますが、自動化が実現すれば、少ない人数でも生産を回すことが可能となるわけです。
ほかにも、労働の負担が軽くなることで従業員の満足度も向上します。従業員のやる気が出れば仕事の能率が上がるのはもちろん、離職率を下げることにもつながります。
スマートファクトリーの導入は、企業と従業員のどちらに対してもメリットがあるわけです。
背景にある製造業DXの流れ
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を用いた変革のことです。IoTやAIといったデジタル技術を導入することで従来の業務体制を一変させ、より働きやすいよう変えていきます。
スマートファクトリーとDXの違いは、技術的な変革と概念的な変革にあります。スマートファクトリーは技術的な変革であり、デジタル技術によって生産効率を向上させます。
一方で、DXは概念的な変革です。デジタル技術を導入する点は同じですが、DXは働き方や環境を変えます。IoTを導入すればリモートワークが可能になりますし、AIを導入すれば情報処理を減らすことができるでしょう。
大まかなイメージとしては、DXを実現させる取り組みの一つがスマートファクトリーです。スマートファクトリー化によって労働環境が変化し、働き方改革(DX)へとつながっていきます。
また、スマートファクトリーは既存の効率化、DXは新しい可能性を生み出すといった違いもあります。効率化によって業務が変革され、そこから新しい業務や価値が生み出されます。
DXの実現に必要なのはスマートファクトリーだけではありませんが、DXを実現させるためには、スマートファクトリーの実現は欠かせない取り組みといえるでしょう。
ファクトリーオートメーション(FA)とは?
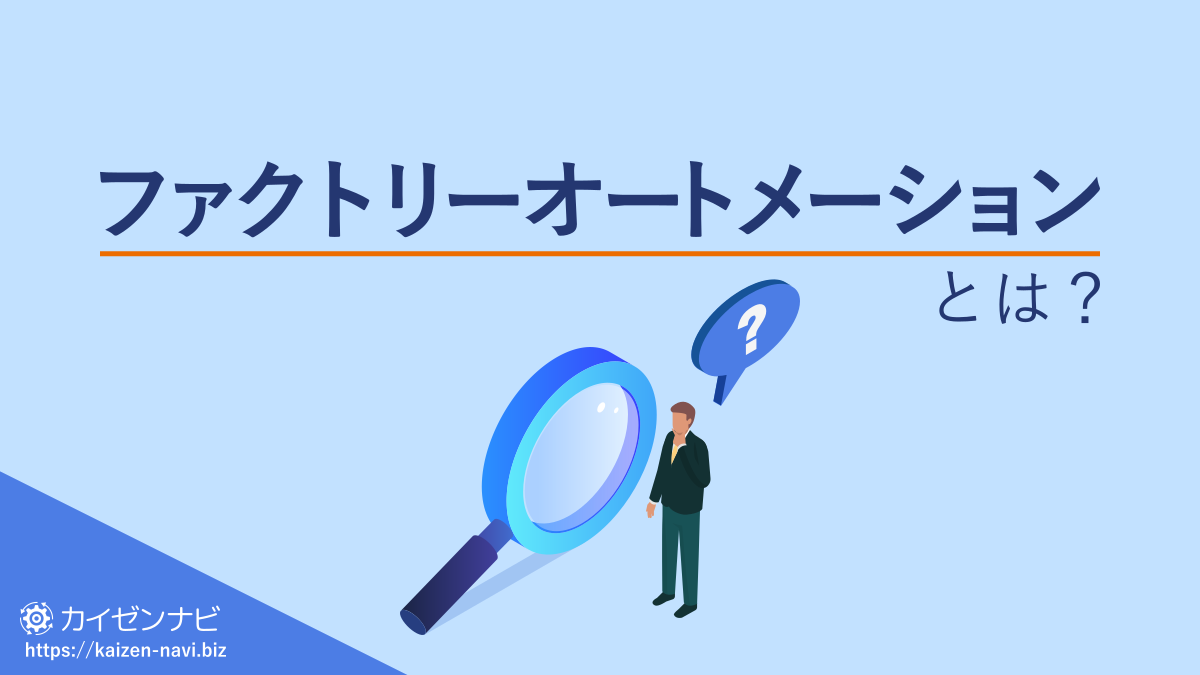
FAとは、どのような意味があるのか。定義や技術要素などについて紹介します。
FAの定義と技術要素
FA(ファクトリーオートメーション)とは、生産工程を自動化するための機械設備や制御システムを指します。例えば、ロボットアームによる製品の運搬、研磨機によるバリの除去、センサーによる品質検査など、主に物理的な作業を自動で行う装置やシステムが対象です。
そのため、FAは機械や設備の導入が中心であり、情報の活用やネットワーク連携は主目的ではありません。ここでいうFAは、IoTやAIのような情報ネットワーク技術そのものではなく、機械的な自動化を実現するハードウェアやその制御装置を中心としています。
FA導入の狙いと得られる成果
FAを導入する目的は、生産能力の向上にあります。生産が自動化されれば生産速度が向上し、生産数を上げることが可能です。ヒューマンエラーやボトルネックなどの生産トラブルも減少することで、生産数や品質を安定化させられます。
また、自動化によって効率化が進めば、コスト削減にもなります。不要な業務が減れば従業員の労働負担も減少し、仕事の安全性も高まるでしょう。
FAが果たしてきた製造現場での役割
FAは、主に労働力の一つとして活用されてきました。近年は労働人口の減少によりどの企業でも従業員が不足しており、その穴埋めとなる形でFA化がされています。
代表的なモノとしては、産業用ロボットが挙げられます。部品を加工するロボット、製品を組み立てるロボット、製品を運ぶロボットなど、近年ではどの製造現場でもFAによる生産が見られるでしょう。
もちろん、生産性を向上させる役割もあります。QCD(品質、コスト、納期)の向上は製造業における課題の一つですが、FAによって自動化が進めば、QCDを向上させられます。
さまざまな課題解決にFAは活用され、生産における足りない部分を補う役割があります。
スマートファクトリーとFAの違いとは?
スマートファクトリーとFAは、どちらも工場の自動化を目的とした取り組みです。どちらも同じ取り組みに思えますが、何が違うのでしょうか?
技術の範囲と目的の違い
スマートファクトリーとFAでは、それぞれ以下のような違いがあります。
| スマートファクトリー | FA | |
|---|---|---|
| 目的 | 工場全体の最適化・効率化 | 生産工程ごとの自動化 |
| 技術 | IoT・AI・ビッグデータなど | ロボット・センサー・ITシステムなど |
| 範囲 | 全工程・全体最適化 | 各工程の部分的最適化 |
| ゴール | データ活用で「考えて動く」工場 | 自動で「作る」 |
目的や範囲を見てもらえればわかりますが、スマートファクトリーは工場全体の最適化なのに対して、FAは工程の最適化と対象が限定的です。
また、技術に関しても、スマートファクトリーはシステムを対象としているのに対して、FAは端末を対象としています。
以上のことから、FAはスマートファクトリーの一端であるといえるでしょう。生産工程をFA化していくことで、スマートファクトリーが実現されるわけです。
そのため、FAは工程の自動化をゴールとして目指します。そして、FAを効率的に活用できるよう、データを活かせる環境を整えることがスマートファクトリーでのゴールとなっています。
情報の「つながり」がスマートファクトリーの鍵
スマートファクトリーでは、情報のつながりを強めることが大切です。「つながり」とはモノとモノとのつながりのことであり、互いに連携し合うことで、効率の良い生産体制を構築できます。
例えば、生産管理システムと作業用ロボットのつながりが挙げられます。ロボットだけの導入(FA)だと生産業務を自動化するだけですが、IoTによって生産管理システムとつながることで、納期に合わせて生産速度を調整できるようになります。
また、AIによる監視を行なえば、リアルタイムで生産管理もできます。トラブルが発生した際はすぐに対応ができるほか、他部署との連携も迅速に行なえるでしょう。
ほかにも、ビッグデータに保存された過去の設計図を基に製造を行なうなど、つながりによってできることが大幅に広がります。
スマートファクトリーを実現させるためには、IoTによる工場ネットワークの構築が不可欠なのです。
スマートファクトリーはFAの“進化形”と捉えるべきか?
人によって考え方は異なりますが、基本的には、スマートファクトリーはFAの進化形と捉えて問題ありません。スマートファクトリーは工場全体の最適化を目指す取り組みであり、工程の一部分を最適化するFAよりも規模や目指す目的が大きいからです。FAからスマートファクトリーへと進化することで、生産につながりを取り入れています。
技術的に例を挙げるなら、FAはロボットを操作して効率化を目指すのに対して、スマートファクトリーは生産システムからの情報を基にロボットを操作します。在庫や工程間の情報を基に生産を進めれば、ボトルネックや過不足などを防ぎつつ、安定した生産が行なえるでしょう。
FAだけでも生産能力は向上しますが、工程を自動化するだけでは限界があります。より企業を成長させるためには、スマートファクトリーやDXを目指すことが大切です。
中小企業がスマートファクトリーを成功させるための手順と注意点
デジタル技術の導入は、今後の製造業において欠かせない取り組みです。デジタル化が推奨される近年において、今後はスマートファクトリーやFAを基準とした生産が主流になっていくことでしょう。
時代に合わせた生産を行なうためには、スマートファクトリーやDXに向けたデジタル技術の導入が必要となります。
しかし、導入にはコストがかかり、気軽に導入を進めるのは難しいです。また、考えなしに導入を進めても現場をムダに混乱させるなどのリスクもあります。
導入に失敗しないためにはどうすればいいのか?導入の進め方や考え方について紹介します。
まずは何から始めるべきか?
導入を進める際は、まずは目的や課題を明確にすることから始めてください。FAの目的は生産工程の効率化であり、効率化すべき部分がわかっていないと導入を進められません。
生産記録や従業員の意見などを参考にしながら、適用すべき部分を決めていきます。
そして、該当する部分が決まったら、どのように改善したいかを現場作業員も含め話し合います。生産数を気にする経営層はもちろんですが、実際に作業する作業員側の考えも大切です。しっかり話し合い、関係者全員が納得するプランを立案しましょう。
FAを活かしながらスマート化するための考え方
FAの導入ができたら、次はFAを活かす仕組みを考えます。ロボットによって効率化に成功したら、生産システムと連結して工程間のリアルタイム情報を仕入れるといったように、次なる変革を目指してください。
考え方のポイントは、FA化する場合と同じです。次なる目的や課題を明確にし、改善に必要となるシステムを立案しましょう。
また、データの可視化も意識するといいです。データで情報のやりとりが行なわれると、人は現在を把握できません。データを可視化することで現状の把握ができ、属人化を防ぐことにもつながります。
ほかに、継続的に続けることも大切です。近年は市場状況の変化が激しく、顧客ニーズに合わせた生産方法が重要になっています。変化に合わせた生産を行なうためにも、定期的にシステムや仕組みを見直す必要があるでしょう。
製造業DXに向けたロードマップの描き方
FAとスマートファクトリーの取り組みは、最終的に製造業DXへとつながっていきます。製造業DXの目指し方として、以下のように行なっていくといいでしょう。
- 現状を分析し課題を可視化する
- デジタル化へ移行するための基盤を構築する
- 改善案の立案と導入プランの決定
- デジタル技術を導入する
- ビジネスモデルのデジタル化を行なう
基本的には、FAとスマートファクトリーの進め方と同じです。それぞれを実施し、その延長としてビジネスモデルのデジタル化(業務内容や工程の改善)を行ないます。
また、実施する際は、段階的に行なうことが大切です。広い範囲で実施してしまうと、企業の負担が大きくなり、業務に支障をきたしてしまいます。ラインや部署で細かく区切り短期的な変革を繰り返すことで、DXへの取り組みが浸透しやすくなるでしょう。
グローバル化によって製造業界も劇的な変化を求められていますが、急いで変化しても中小企業は対応できません。長期的に計画を立てて、無理のない変革を目指してください。
まとめ:スマートファクトリーとFAの違いを理解して、DX推進の第一歩を踏み出そう
スマートファクトリーとFAの違いは、簡単にまとめるとデジタルか物理的かの違いです。
IoTやAIといったデジタル操作によって自動化を目指すのがスマートファクトリー、ロボットやセンサーといったモノを使って自動化を目指すのがFAといえます。
どちらも自動化を目的としていますが、デジタルな改善と物理的な改善では内容が異なります。導入を成功させるためにも、それぞれの特徴をよく理解したうえで取り組む必要があるでしょう。
とはいえ、スマートファクトリーはFAの進化型ともいえ、FAの延長線上にスマートファクトリーの取り組みがあります。そのため、完全に分けて考える必要はありません。DXを目指す取り組みとしてスマートファクトリーを、スマートファクトリーを目指す取り組みとしてFAを実施といったように、先を見据えた変革を目指してみてください。