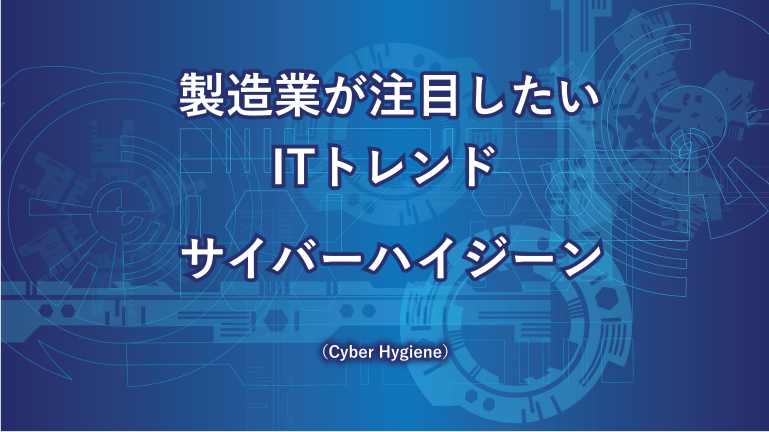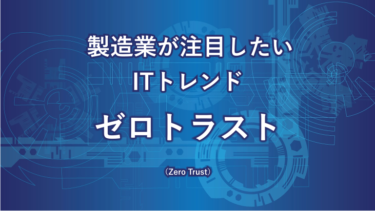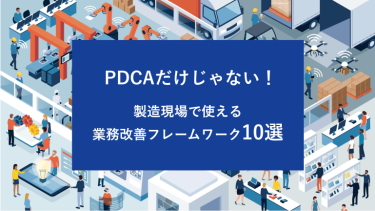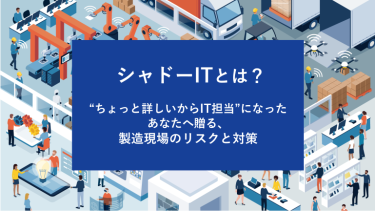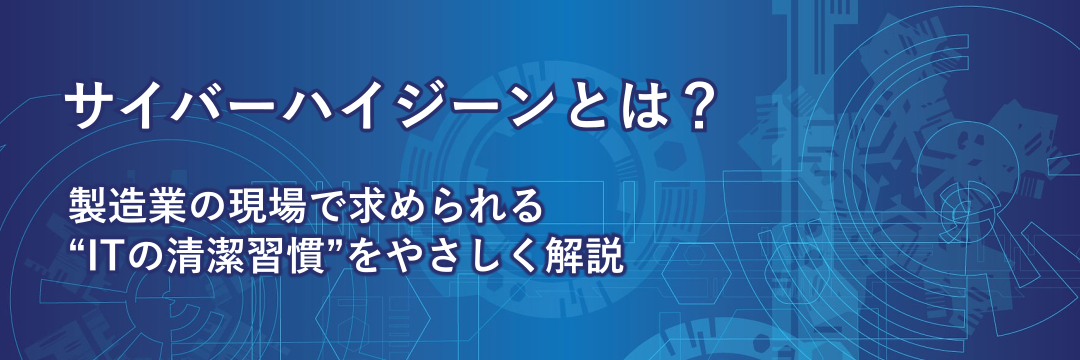
企業に甚大な被害をもたらすサイバー攻撃。金銭の要求や情報の流出など、サイバー攻撃による被害は、企業にとっての致命傷となります。
サイバーハイジーンは、そんなサイバー攻撃を防ぐための取り組みです。セキュリティソフトを導入することだけが、サイバー攻撃への対策ではありません。
サイバー攻撃を防ぐにはどのようなことをすればいいのか?サイバーハイジーンが必要とされる背景など、サイバーハイジーンについて紹介します。
サイバーハイジーンとは?
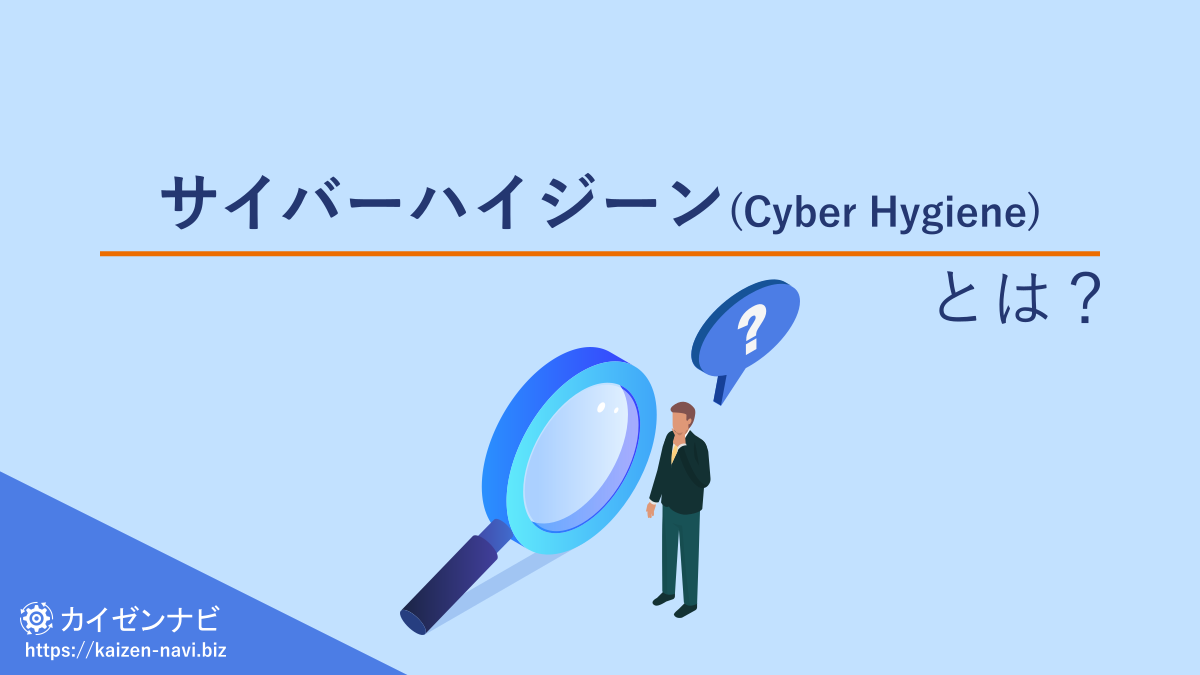
サイバーハイジーンとは、サイバー攻撃をされないよう、普段から対策をしておく取り組みのことです。「ハイジーン(Hygiene)」は「衛生・清潔」といった意味があり、コンピュータウイルスに感染しないよう、サイバー空間の衛生管理を徹底します。
具体的な例としては、「不審なメールを開かない」「パスワードを秘匿する」などが挙げられます。
ほかにも、「社員へのセキュリティ教育」や「利用規約の制定」などもあり、社員の意識改革を含め、サイバー攻撃をさせない環境を整えていきます。
サイバーハイジーンが注目される背景
サイバーハイジーンが注目される背景には、近年進められるIT化が関係します。IT化によってさまざまなモノにIT技術が組み込まれるようになりましたが、同時にサイバー攻撃をされるリスクが高まっています。
警察庁が2024年に発表した報告によると、サイバー攻撃されたIPアドレスの件数は、1日に9,144.6件(令和5年)を超えるそうです。2019年と比較すると約2倍の件数が報告され、年々サイバー攻撃による被害が深刻化しています。
また、会社の規模で比較した場合、大企業よりも中小企業での被害が増加していることも挙げられています。これは、中小企業の方がサイバーセキュリティが甘く、サーバーの脆弱性を突くことで、簡単にサイバー攻撃ができてしまうからです。
警察庁2024年報告によれば、中小企業の被害が増加。複数の解説では“前年比37%増”とされる報告もあり、中小企業のセキュリティ対策を見直す必要があるでしょう。
サイバー攻撃と聞くと「お金を持ってそうな大手企業が対象」と思うかもしれませんが、中小企業も被害に遭っています。「自分の会社は大丈夫」とは思わず、サイバー対策に取り組むことが大切です。
- 参考サイト
- 警察庁サイバー警察局「令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」/参照日:2025年12月08日
- 内閣官房サイバー安全保障体制整備準備室「サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議 アクセス・無害化措置に関するテーマ別会合 第1回参考資料(サイバー攻撃の情勢)」/参照日:2025年12月08日
なぜ製造業にとって重要なのか?
サイバーハイジーンが重要視される理由には、以下のようなことが挙げられます。
製造現場の「IT化(スマートファクトリー化)」が進行中
サイバーハイジーンが必要とされる理由には、工場のIT化(スマートファクトリー化)が挙げられます。IT技術の導入によって生産がより効率的になりますが、デジタル管理になることで、サイバー攻撃をされる隙を作ってしまうのです。
IT化の基本は、IoTやAIを活用したネットワーク技術です。工場全体をネットワークでつなげることにより、データ分析に基づいた生産やリアルタイムな情報共有などを可能にします。ほかにも、作業ロボットを遠隔操作するなど、IT化によってできることが大幅に広がるでしょう。
しかし、IT化によるネットワークの構築は、外部サーバーともつながることを意味します。外部サーバーとつながることで不正アクセスが可能となり、マルウェアの感染や情報流出のリスクが高まってしまいます。
サイバー攻撃による被害は、自社情報が奪われるだけではなく、顧客からの信用も失ってしまいます。そのような被害を防ぐためにも、サイバーハイジーンによる対策が必要なのです。
従来の「制御系ネットワーク」はセキュリティを想定していなかった
従来の制御系ネットワークでは、セキュリティを想定していなかったことも大きいです。従来の制御系ネットワークは自社サーバーを用いた社内ネットワークだったため、外部からアクセスされる心配がありませんでした。
しかし、近年はクラウドサービスを利用した外部ネットワークが主流となっており、不正アクセスを防ぐためのセキュリティが求められています。
IT化によって新しい制御系ネットワークへの移行が推奨されていますが、従来の考えのままでは、不正アクセスを防ぐのは難しいといえるでしょう。
IT化を実現するためには、従来の考え方を見直し、セキュリティ意識を高める必要があります。
多くの攻撃は「基本的対策」で減らせる
攻撃のすべてを防ぐことはできません。しかし、基本的なサイバーハイジーンを徹底するだけでも、一般的な侵入手口の大部分を未然に抑止できます。例えば次のような取り組みです。
-
パッチ適用/OS・ソフトの自動更新の有効化
-
多要素認証(MFA)+長いパスフレーズの徹底
-
不要サービスの無効化・既定権限の見直し(最小権限化)
-
リムーバブルメディア(USB等)の管理
-
従業員教育(フィッシング対策・取扱いルール周知)
さらにゼロトラストの原則を組み合わせ、仮に突破されても被害を最小化できる体制を整えましょう。
最初からすべてを完璧にする必要はありません。導入しやすい項目から段階的に適用し、効果と運用負荷を見ながら範囲を広げていくのが現実的です。
中小企業でも、優先順位付けと段階導入により、費用対効果の高いサイバーハイジーンが実現できます。
DX(デジタル・トランスフォーメーション)化が話題となる近年。様々な業界でデジタル化、DX化が進んでいます。クラウドサービスの利用によって働き方も以前とは変わってきており、IT技術の発展に多くの企業が注目をしています。 ですが[…]
まず着手すべき3つの基本対策
いざサイバーハイジーンを行なうにしても、どのようなことをすればいいのかわからないと思います。
基礎的な取り組みではありますが、取り組みをいくつか紹介しますので、実際に行なう際の参考にしてみてください。
| 対策 | 目的 | ベースライン |
|---|---|---|
| OS・ブラウザ・主要ソフトの自動更新ON | 既知脆弱性の封じ込み | Windows Update、各主要ソフト、macOS、主要ブラウザを自動更新に。VPN/メールゲートウェイ等の境界機器は優先して最新化(検証→本番の二段階リング運用)。 |
| MFA+長いパスフレーズ | 資格情報悪用の抑止 | 12〜16文字以上のパスフレーズ、使い回し禁止、共有はパスワードマネージャの共有保管庫を使用。メール/SSO/VPNはMFA必須。※定期強制変更は不要(漏えい時のみ変更)。 |
| バックアップの強化 | 復旧力の確保 | 3-2-1原則(媒体3つ・場所2つ・1つはオフサイト)、不可変(WORM)コピーを1系統用意し、月1回の復元テストを実施。 |
まず、この3つができているか確認することで、「侵入されにくくする(更新・MFA)+やられても戻れる(バックアップ)」を短期間で実現できます。
- 参考サイト
- NCSC(UK)“Password policy: updating your approach”, 2023./参照日:2025年12月08日
- NIST SP 800-63B “Digital Identity Guidelines: Authentication and Lifecycle Management”, Rev.3, 2017/参照日:2025年12月08日
中小製造業でもできる!実践ポイントと導入のコツ
上の最優先3つを現場運用に落とす段取りに絞って解説します。
OS・ブラウザ・主要ソフトの自動更新ON
パッチ適用は、生産ラインの停止と衝突させない限り進みません。そこで、毎月の設備点検や計画シャットダウンの枠に、あらかじめ「検証→本番」の二段階更新を組み込みます。
まずは検証用端末や非クリティカルな機器で挙動を確認し、問題がなければ本番群へ波及させる、というリズムを“カレンダーに固定”します。境界機器(VPN、メールゲートウェイ、リモート保守装置)は攻撃の入口になりやすいため、最優先で最新化します。
どうしても更新できない事情がある場合は、例外を放置せずに記録します。理由・影響・暫定対応・期限・責任者をA4一枚にまとめ、期限切れの自動リマインドをかけておきます。例外は“無期限の放置”ではなく、“期限付きの選択”に変換するのがコツです。
MFA+長いパスフレーズ(共有端末を意識)
認証まわりは、いきなり全社で変えると現場が混乱します。まずは影響の大きいところから。
メール、SSO、VPNといった外部接続や全社基盤にMFAを義務化し、展開は「管理者→経理・購買→役員→全社」の順で進めます。SMSよりTOTPやプッシュ認証を優先すると、セキュリティと運用のバランスが取りやすくなります。
- パスワードは12〜16文字以上のフレーズ形式を標準
- 使い回しはしない
この二点を徹底するには、パスワードマネージャの“共有保管庫”を配るのが近道です。現場に多い共有端末では、個人アカウントの利用と短時間ロックを基本にし、A4一枚の「OK/NG例付きパスワードガイド」を配布して定着を促します。
なお、定期的な強制変更は不要で、漏えいが判明・疑われた時に速やかに変更する方が実務に適います。
バックアップ(復元テストまでがバックアップ)
バックアップは“取る”だけでは意味がありません。“戻せる”状態まで含めて仕組み化します。
媒体を3つ、保管場所を2系統、うち1つはオフサイト——いわゆる3-2-1原則に、削除や改ざんに強い不可変(WORM)コピーを1系統加えます。クラウドやNASのスナップショット機能でもよいので、まずは一つ“触れないコピー”を確保しましょう。
そして月に一度、実際に復元テストを行ないます。1ファイルのピンポイント復元と、システム全体の丸ごと復元の両方を試し、手順書を更新します。
製造に固有のデータ(レシピ、PLC設定、図面)は保管場所が分散しがちなので、バックアップ対象を棚卸して漏れを防ぎます。
全体をスムーズに進める共通のポイント
取り組みをスムーズに進めるためのポイントについても紹介します。
現場リーダーや班長を巻き込む
サイバーハイジーンに取り組む際は、上の人を巻き込むようにします。企業の構図はピラミッド形なため、上の存在を巻き込むことで、広く取り組みを伝えられるからです。
また、規則を作る意味でも重要といえます。同僚が決めた規則だと強制力は低いですが、上の者が決めた規則なら、多くの人が従ってくれるでしょう。
取り組みをスムーズに進めるためにも、まずは現場リーダーや班長に相談することから始めてみてください。
「罰則」ではなく「守ったら安心」という前向きな伝え方
取り組みを進める際は、前向きな気持ちで行ないます。堅苦しく取り組みを進めると、心身が疲れてしまうからです。罰則を気にするあまり、業務に支障も出てしまうでしょう。
「守らなければ罰則」といった緊張感のある現場にするのではなく、「守ったら安心」といった、のびのびと働ける現場を作るよう意識してください。
一気に全部やるのではなく、1項目ずつ段階的に導入する
取り組みを進める際は、一度に行なうのではなく、段階的に行なうようにします。ガイドラインの作成、点検スケジュールの調節、外部デバイスの指定などどれも大切ではありますが、一度に行なうと、変化によって現場が混乱をしてしまうからです。
1項目ずつ試していき、社員の間でしっかり浸透したら、次の項目を導入していきましょう。
まとめ:まずは“小さな一歩”として清潔習慣から始めよう
サイバーハイジーンとは、サイバー攻撃をされない環境を整える取り組みのことです。セキュリティプログラムを導入するのはもちろん、規則や教育を設けることで、継続的な安全を確保します。
近年は、IT化への取り組みが世界的に進められています。IT化によって業務が効率化されることから、IT化を目指す企業は多いことでしょう。
しかし、IT化への移行は、同時にサイバー攻撃をされるリスクが高まることを意味します。従来のセキュリティ意識のままでは、サイバー攻撃を防ぐのは難しいです。
セキュリティ意識を高め安全に作業をするためにも、まずはサイバーハイジーンを習慣化することから始めてみてください。