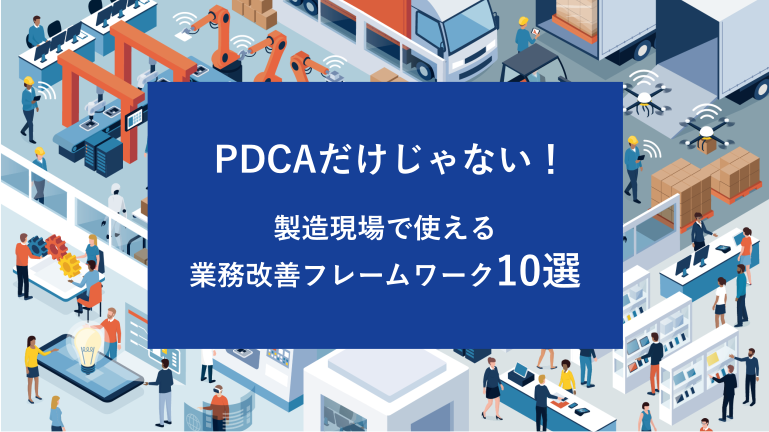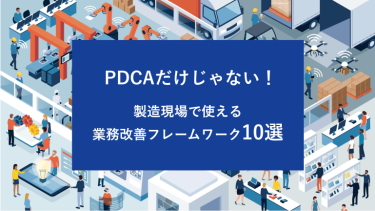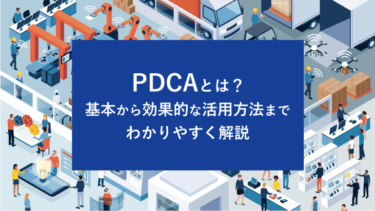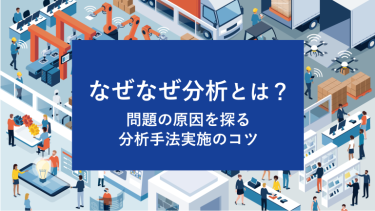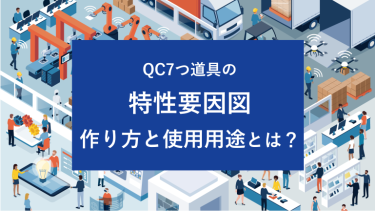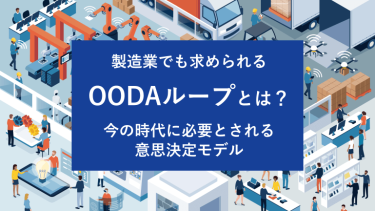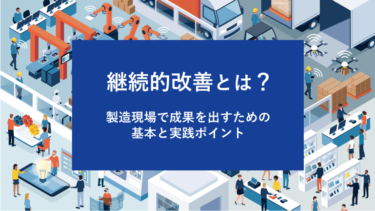業務改善といえば、真っ先に思い浮かぶのが「PDCA」。その定番手法にも、実は限界があるのをご存知でしょうか?
PDCAは、業務改善を目的としたフレームワークとして有名です。1950年代にアメリカの統計学者によって発表されて以来、多くの企業で活用されてきました。今でも、PDCAを方針とする企業は多いです。
しかし、近年では別の方法で業務改善が行なわれるケースも増えています。市場やIT技術の変化が激しく、初動が遅いPDCAでは限界を感じるためです。激しい変化に対応するためには、状況や目的に合わせた、適切なフレームワークを選ぶ必要があります。
PDCAサイクル以外のフレームワークにはどのようなものがあるのか?製造現場で使えるフレームワークについて紹介します。
PDCAだけじゃない!改善フレームワークを使い分けるべき理由
業務改善を効率的に行なうためには、フレームワークを使い分けることが大切です。PDCAと使い分ける理由について紹介します。
PDCAの利点と限界
PDCAとは、「計画(Plan)」「実行(Do)」「評価(Check)」「改善(Act)」の4項目から構成されるフレームワークのことです。PDCAの流れを1サイクルとし、繰り返し行なうことで、業務内容の改善を目指します。
PDCAの特徴は、次に行なうことが明確なことです。基本的な段取りが決まっているため、業務改善初心者でも、改善の流れを直感的に理解できます。
また、繰り返すことで精度や練度も高まります。サイクルを繰り返すごとに結果や実力が積み重なり、堅実に業務改善を目指せるでしょう。
しかし、実行には段取りが必要なことから、柔軟性に乏しい欠点もあります。方向を変化させるためには再度段取りを組む必要があるなど、迅速な対応が難しいです。
ほかにも、段取りが決まっているため、形骸化しやすい点もあります。慣れてしまうと「とりあえずサイクルを回せばいい」と思うようになり、革新的なアイデアが出にくくなります。
近年は、グローバル化やデジタル化により、市場やIT技術の変化が激しい時代です。変化する顧客ニーズへの対応が求められるなか、段取りを組んでの対応では遅いといえるでしょう。
PDCAでも対応はできますが、初動の遅さから市場競争で後手に回りがちです。そのことから、近年では「PDCAは古い」ともいわれ、新しいフレームワークが好まれています。
課題別に適したフレームワークを使う重要性
PDCA以外のフレームワークが登場したことも、使い分ける理由の一つです。それぞれのフレームワークには得意とする方向性があり、課題に合わせて使い分けることで、より効率よく業務改善を目指せます。
例えば、顧客ニーズに合わせた製品展開についてです。製品を売るためには顧客ニーズに合わせる必要がありますが、PDCAで生産をしていては、ライバル企業に先を越されてしまいます。場合によっては、製品リリースをする前に、市場が変化してしまうかもしれません。
変化が激しい課題に対しては、OODAループを始めとした、速度を重視したフレームワークが効果的といえるでしょう。
PDCAでも多くの課題に対応できますが、効率よく業務改善を行なうためにも、課題や目的に合わせてフレームワークを使い分けることが大切です。
製造現場で使える改善フレームワーク10選
ここからは、実際の現場で使われている改善フレームワークを11個(PDCAサイクルを含む)紹介します。それぞれの特徴を理解し、現場の課題に適したものを選びましょう。
PDCAサイクル
PDCAサイクルは、繰り返して改善を目指すフレームワークです。計画したプロセスを実行し結果を評価、評価した内容を基に改善し新しくプロセスを計画するといったように、サイクルを繰り返すことで、前サイクルよりも良くしていきます。
- 計画:目標を明確にし、計画を立案する
- 実行:計画を実行する
- 評価:実行した内容を基に、目標とのズレを分析する
- 改善:評価に基づき、改善策を立案する
柔軟性に乏しく迅速に結果を出すのが苦手ですが、持続性が高いのが特徴です。サイクルが半永久的に続きますので、業務改善を長く続けられます。
PDCAの考えを職場風土に根付かせることで、将来を見越した継続的改善が可能となります。
ビジネスで改善を進めるうえでよく聞く「PDCAサイクル」。この記事では、PDCAサイクルの基本から、実際にどう活用できるかを詳しく説明します。また、この記事を読むことで、業務改善をどのように進めるかの具体的な方法が理解できるようにな[…]
ECRS
ECRSとは、ムダを減らすことで改善を目指すフレームワークです。「排除(Eliminate)」「結合(Combine)」「交換(Rearrange)」「簡素化(Simplify)」の4項目から構成されており、業務を当てはめて考えることで内容を簡略化できます。
- 排除:ムダなことをなくす
- 結合(分離):複数の業務をまとめる(業務が複雑なら分離する)
- 交換(代案):やりやすいよう順番を入れ替える(別の方法が良ければ入れ替える)
- 簡素化:業務を単純にする
例えば、「A素材を持ってくる」→「A素材を加工する」→「B素材を持ってくる」といったプロセスがあるとします。そのままのプロセスだと3工程必要ですが、AとBの素材を同時に持ってくれば2工程で済みます。
ほかにも、ビーカーにラインを引いて秤で液体の量を測る必要をなくすなど、ヒューマンエラーが生じないように簡素化します。
業務のムダを減らすことで、作業効率の改善や業務負担の軽減が実現できるでしょう。
ECRSの並びは、改善による効果が大きい順です。ECRSを利用する際は、ムダなことを排除することから始めてみてください。
製造現場で必要なことは、より「作業効率」や「生産性」を向上させることです。作業時間を短くすれば生産性が上がり、企業の利益につながります。 他にも、コスト削減や人材の削減、ミスの削減なども重要な要素であり、それらの問題は、製造業[…]
なぜなぜ分析
なぜなぜ分析とは、連想することで根本的な原因を見つけるフレームワークです。問題に対して「それはなぜか?」を繰り返すことで、改善すべき課題が決められます。
例えば、1日の生産数が目標を達成しなかったとします。「なぜ達成しなかった」のかを考えた場合「機械の稼働開始が遅かった」が考えつきました。そして、同じように「なぜ」を繰り返すことで「朝の掃除が遅かった」「掃除道具の場所がわからなかった」と連想が続き、「生産数を上げるためには朝の掃除を早くする必要があり、そのためにも、掃除道具を準備しやすいようにする」ことが、今後の対策として導き出されます。
もちろん、「稼働率が低かった」のように、ほかにも考え付く場合は、そちらでも同じようになぜなぜ分析を行なっていきます。それぞれの課題を解決することで、業務が大幅に改善されるでしょう。
「なぜ?」を5回繰り返すことで、根本的な原因に辿り着くといわれています。無理に「なぜ?」を繰り返す必要はありませんが、原因究明をする際は、5回を目安に「なぜ?」を繰り返してみてください。
製造業に限らず、原因究明はとても重要です。原因が特定できないままだと改善もままならず、同じトラブルを招いてしまいます。トラブルが続くと生産効率などが低下してしまい、納期が遅れることで顧客との信頼関係も悪化してしまうでしょう。 […]
特性要因図(フィッシュボーン図)
特性要因図とは、問題の原因を洗い出すためのフレームワークです。ある結果に対して、関連する要因を視覚的に整理することで、原因同士の関係性や、根本的な要因を明らかにできます。
構造としては、背骨のような一本の軸(中心線)に、思いつく要因を枝のように追加していく形式です。さらに、その枝に対しても細かく要因を付け加えていくことで、原因が階層的に可視化され、対処すべき問題点が明確になります。
この図の形状が魚の骨や葉脈に似ていることから、「フィッシュボーン図(魚の骨図)」とも呼ばれています。
また、特性要因図は数値を使わずに構造化できるため、製造業だけでなく、営業やサービス業などあらゆる業種で活用可能です。シンプルかつ柔軟性のある分析手法として、多様な業務改善の場面で役立つフレームワークといえるでしょう。
特性要因図というフレームワークについて知っていますか?「QC7つ道具」における手法の一つであり、特性要因図を活用することで、課題に対する原因究明が分かりやすくなります。 原因究明は、品質改善にとても重要な要素です。品質は企業の[…]
5W1H
5W1Hとは、状況を整理・伝達するためのフレームワークです。「いつ(When)」「どこで(Where)」「だれが(Who)」「なにを(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」の6項目から構成され、問題が起きた状況を当てはめて考えることで、発生原因を正しく把握できます。
原因究明に必要なのは、正確な情報です。正しい情報が多いほど発生した状況が正しくわかり、改善策を立案しやすくなります。状況の漏れがないよう、状況把握をする際は5W1Hを意識してください。
特に、対策に慣れていない新人だと、報告に穴が空きやすいです。5W1Hを問題報告のフォーマットとすることで、誰でも同じように報告ができます。形式も揃うことで、記録として残しやすくもなるでしょう。
ちなみに、自動車会社で有名なトヨタ自動車では、5Wのことを「5Whys(1H)」としています。5Whysとは、「なぜ?」を5回繰り返し問題解決を目指す方法であり、つまりは「なぜなぜ分析」のことを指します。
トヨタ自動車にあやかって、なぜなぜ分析のことを5W1Hとする場合もありますので、間違えないよう注意してください。
QCストーリー
QCストーリーとは、目標達成までの流れを示すフレームワークです。PDCAサイクルと同じように、8つのステップを順番に行なうことで、目標の達成を目指します。
- テーマ設定:題材となる問題や課題を明確にする
- 現状把握:情報を収集し、現状を正しく把握する
- 目標設定:現状と比較して、目標を設定する
- 原因分析:原因を分析し、根本的な原因を明確にする
- 対策立案:根本原因について話し合い、対策を計画をする
- 対策実施:計画した対策を実施する
- 効果確認:実施内容を分析し、効果を評価する
- 標準化:効果のある対策を標準化し、継続的に取り組めるようにする
PDCAサイクルとは異なり継続的な改善を目的としておらず、代わりに、対策を業務へ定着させることを目的としています。標準化によって、誰でも同じような結果を出せるようになります。
もちろん、効果確認で結果が出ない場合は、PDCAサイクルと同じように繰り返しても良いです。明確な効果が出るまで行なってみてください。
ちなみに、QCストーリーには「問題解決型」「施策実行型」「課題達成型」など、いくつかのストーリーが存在します。上記で紹介した流れは、問題解決型のスト-リーです。
- 問題解決型:原因究明を目的としたタイプ
- 施策実行型:問題がすでに把握しており、改善を目的としたタイプ
- 課題達成型:今後の目標達成を目的としたタイプ
タイプは異なりますが、基本的な流れはどれも同じです。細かな部分は目的に合わせて変更してみてください。
OODAループ
OODAループとは、即応性のある意思決定フレームワークです。「観察(Observe)」「状況判断(Orient)」「意思決定(Decide)」「行動(Act)」の4項目から構成され、順番にステップを踏むことで、今後の方針を決定します。
- 観察:現状からわかる情報を収集する
- 状況判断:収集した情報を整理し、状況を正しく判断する
- 意思決定:把握した状況を基に、次の行動を立案・選定をする
- 行動:決定した行動を実行する
PDCAサイクルと同様にステップを踏むのは同じですが、OODAループは行動(実施)が最後に来る点が異なります。PDCAサイクルは実施の後の評価・改善を重視していますが、OODAループは行動前を重視しているのが特徴です。
そのため、OODAループは実施直前に変化があっても修正がしやすく、変化しやすい近年の市場状況に対応がしやすいといえるでしょう。
「とりあえずやってみよう」の考えが強く、スピーディに実行できます。
ただ、OODAループは行動までの早さを重視していることから、方向性がぶれやすい傾向があります。充分な計画をするわけではないため、失敗することもよくあります。
また、行動後を重視していないことから、継続的な改善にも向きません。もちろん、行動後に改善を行なうのも良いですが、繰り返す場合は、別のフレームワークを使うことになります。
長期的な改善を目的としたPDCAサイクルと、短期的な改善を目的としたOODAループ。それぞれ特徴が異なりますので、目的に合わせて使い分けると良いです。
近年、需要が広まるOODAループ。デジタル化社会による影響により、様々な業界で注目されるようになりました。 以前はPDCAサイクルを始めとした各サイクルを用いていた企業も、インターネットの普及によって高速化された情報の変化には[…]
KPT法
KPT法とは、振り返り式のフレームワークです。「継続すること(Keep)」「問題点(Problem)」「実施内容(Try)」の3項目から構成され、プロジェクトの内容を振り返ることで、今後の成長へつなげます。
- 継続すること:成功した内容。うまくいったことから次回以降も続けること
- 次回の課題:失敗した内容。次回に向けた課題とすること
- 実施内容:実施内容のまとめ。今後行っていく内容をまとめる
プロジェクトを、成功と失敗の両面で評価します。課題の早期発見はもちろん、良かった点から、今後の方針を決めることも可能です。
シンプルだからこそ汎用性が高く、さまざまな場面で活用できます。
KPT法とは、現状を見直し改善を目的としたフレームワークのことです。元々はエンジニアの間で活用されていた手法ですが、近年では他の業種にも活用可能なことから、さまざまな業界からも注目されてきています。 「現状を振り返って改善点を[…]
Hoshin Kanri(方針管理)
Hoshin Kanriとは、目標と個人の作業状況を管理するフレームワークです。日本語では「方針管理」と表記し、チームが目標を達成できるよう、メンバーに仕事を割り振ります。
Hoshin Kanriでは、チームの管理に「Hoshin Kanri マトリクス」を使用します。東西南北に目標や目的(イニシアチブ)を記載し、隣り合う方角の目標との関係性を示します。
そして、記載されたマトリクスを確認しながら、チームやメンバーは担当する業務をこなしていきます。
マトリクスに目標を記載し管理することで、現在やるべきこと・していることが明確となり、段階的に目標を達成しやすくなるでしょう。
DMAIC(リーンシックスシグマ)
DMAICとは、原因分析を目的としたフレームワークです。「定義(Define)」「測定(Measure)」「分析(Analyze)」「改善(Improve)」「定着・制御(Control)」の5項目から構成され、順番にステップを踏むことで、改善した内容を業務へ定着させます。
- 定義:題材となる問題や目標を明確にする
- 測定:現状を把握するため情報収集をし、問題点を明確にする
- 分析:測定データから原因を特定し、問題が生じた理由を考える
- 改善:改善策を立案し、実行する
- 定着・制御:効果のある改善策を標準化し、業務に定着させる
業務改善の流れを統一することで、改善がスムーズに進められるだけではなく、情報共有もしやすくなるでしょう。
カンバン方式
カンバン方式とは、トヨタ自動車が開発した生産管理方式です。情報が書かれたカンバンを工程間でやりとりすることで、情報共有が正確に行なえます。
例えば、後工程で部品を4つ消費したとします。その情報をカンバンに記載し前工程に送ることで、前工程は消費した部品の数がわかるわけです。後は、消費した数に合わせて生産を行なえば、ムダのない生産が可能となります。
トヨタ自動車では、業務改善の方法として、生産におけるムダを減らす取り組みを行なっています。カンバン方式もその取り組みの一つであり、カンバン方式によって、計画的に生産が行なえるでしょう。
製造業において、適切な在庫管理を行うことはとても重要です。 欠品が発生すると販売機会を損失してしまい、逆に造りすぎると過剰在庫になってしまうため、バランス良く製品を製造していく必要があります。 自動車メーカー「トヨタ自動車」は[…]
フレームワーク選定のコツと組み合わせ例
紹介したフレームワークは、組み合わせて使うことも可能です。それぞれ特徴が異なるからこそ、合わせて使うことで、より業務改善を深堀できます。
いくつか例を紹介しますので、組み合わせの参考にしてみてください。
単独ではなく、複数をステップで連携させる使い方が有効
フレームワークは単独でも使えますが、組み合わせて使うこともできます。なぜなぜ分析は原因の特定を目的にしたフレームワーク、QCストーリーは業務改善を目的としたフレームワークといったように、フレームワークごとに目的が異なるからです。
QCストーリーの原因分析をする際になぜなぜ分析を活用すれば、スムーズに原因分析が行なえるでしょう。
組み合わせ例1:問題が曖昧で改善策が思いつかない
問題が曖昧で改善策が思いつかない場合は、「5W1H」「なぜなぜ分析」「QCストーリー」の3つを活用すると良いです。
まず始めに、問題を明確にするため5W1Hを活用します。問題が発生した状況を整理することで、生じた問題がわかるようになります。
問題がわかったあとは、なぜなぜ分析によって原因を特定します。そして、その原因を基にQCスト-リーを組むことで、業務改善のフローチャートが完成するでしょう。
問題点を整理するためにも、トラブルが生じた際は、まず5W1Hから始めてみてください。
組み合わせ例2:日々の業務の改善
日々の業務改善をする場合は、「PDCAサイクル」「KPT法」の2つを活用すると良いです。
まずは、PDCAサイクルによって計画を実施するところまで行ないます。そして、その結果を評価する際に、KPT法を活用します。
KPT法を活用することで、成功部分と失敗部分の両方を評価できます。次のサイクルへ向けた改善案の立案はもちろん、計画による効果も明確になることで情報共有がしやすくなるでしょう。
PDCAサイクルに限らず、効果を分析する際は、KPT法を活用してみてください。
組み合わせ例3:品質トラブルの改善
品質トラブルの改善をする場合は、「DMAIC」「特性要因図」の2つを活用すると良いです。特性要因図とは因果関係の追求を目的としたフレームワークの一つであり、なぜなぜ分析のように要因を追求していくことで、原因の相互関係や根本的な要因を見つけます。
まずは、DMAICによって測定をするステップまで行ないます。そして、次のステップである分析を行なう際に、特性要因図を活用して原因究明を行ないます。
特性要因図のメリットは、図で示すことで全体像が把握しやすいことです。情報を整理しながら分析ができ、チームで情報共有もしやすくなるでしょう。
特性要因図は、品質改善を目的とした「QC7つ道具」の一つです。ほかにも便利なフレームワークがありますので、紹介したフレームワークにこだわらず、状況に合わせていろいろなフレームワークを組み合わせてみてください。
まとめ:改善の質を高める“道具箱”を持とう
業務改善といえば昔からPDCAサイクルが定番でしたが、近年ではさまざまなフレームワークが活用されています。時代が変わることで製造業界も変化し、それに伴う形で業務の改善も変化しているのです。
もちろん、現在でもPDCAサイクルは活用可能です。継続的な改善を得意とすることから、日常的に行なう業務改善に適しています。PDCAを企業に根付かせることで、継続的な成長が期待できるでしょう。
フレームワークは、あくまでも業務改善をするための道具に過ぎません。そして、道具を使いこなせるかは利用する人によります。改善の質を高めるためにも、道具箱の中身を増やし、状況や目的に合わせてフレームワークを選べるようにしましょう。