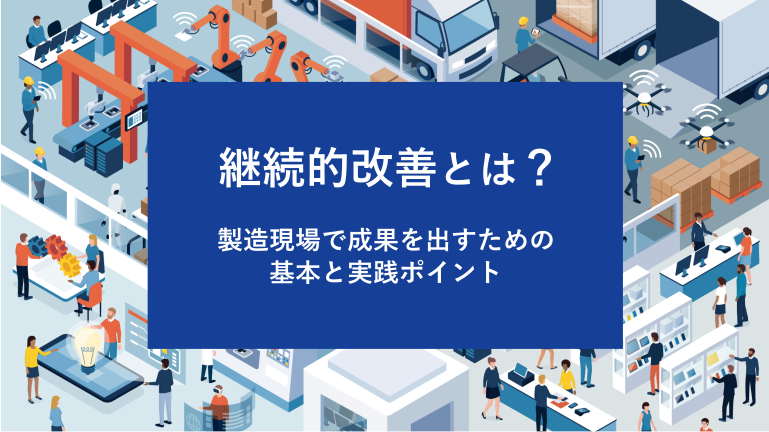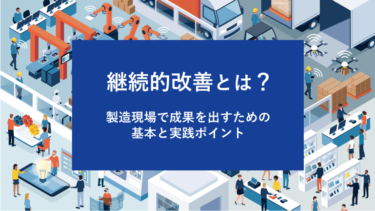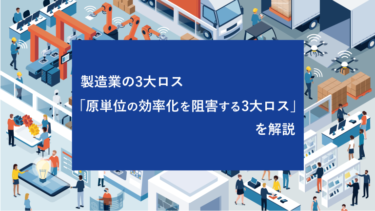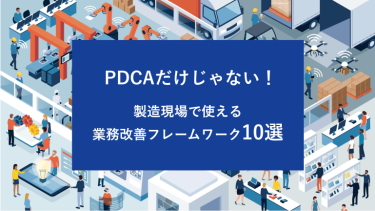より良い業務改善を目指す継続的な改善。現在の状況よりもさらに良くなることを目的としており、変化が激しい製造業界において、必要な取り組みといえます。
しかし、中には「一度改善をすれば充分」と思う人もいるでしょう。継続的に続けるには計画的に取り組む必要があり、面倒に感じるでしょう。
継続的改善はなぜ必要とされているのか。継続的改善の目的や導入の進め方などを紹介します。
継続的改善とは?その定義と基本概念
継続的改善とは、継続的に改善を行ない、より良い状態を目指す取り組みのことです。一度の改善で完了とせず、今後も改善を考慮しながら活動を続けます。
多くの場合、一度改善をしたら、一旦完了とするのが一般的です。以前よりも良くなっているなら、新しく手を加える必要はないと思うでしょう。
しかし、一度の改善で満足してしまっては、企業の成長は望めません。特に、近年は技術や販売市場の変化が激しいことから、変化がないと時代に取り残されてしまいます。
市場競争に勝つためにも、常に改善を追求していく姿勢が求められるのです。
継続的改善の意味と目的
継続的改善を実施する目的は、自社の持続的な成長と競争力を強化するためです。変化する市場情勢に対応するためには「一度きり」の改善では足りず、変化に合わせた「継続した改善」が求められます。
具体的に示すと、PDCAを運用することが挙げられます。PDCAとは業務内容を段階的に改善していくフレームワークのことであり、「計画(Plan)」「実行(Do)」「測定・評価(Check)」「対策・改善(Action)」を繰り返し行なうことで、継続的な改善を目指します。
市場の情勢が変化したらPDCAサイクルによってプロセスを改善して標準化し、再度市場情勢の変化を迎えたら合わせて再びPDCAサイクルによるプロセスの改善といったように、改善を続けていくことで、顧客満足度を満たします。
改善活動との違い
改善活動とは、現状の業務をより良くするための活動のことです。継続的改善と内容自体は似ていますが、継続的改善は「継続的な改善」を目的としているのに対して、改善活動は「一時的な改善」を目的としています。
つまりは、改善活動を続けていくことが、継続的改善につながるといえるでしょう。
また、継続的改善の対象範囲は、「人」「モノ」「仕組み」など多岐にわたります。業務を改善する取り組みにはほかにもQC活動や5Sなどがありますが、QC活動は品質管理、5Sは現場管理と活動範囲が専門的です。
QC活動や5Sなど改善する取り組みはいろいろありますが、それらすべてを統括する取り組みが、継続的改善(改善活動)となります。
ISO9001の継続的改善
ISO9001には、「10.3」の項目に「継続的改善」が記載されています。ISO9001の冒頭に記載されている「品質マネジメントの原則」としても触れられており、ISO9001の中心的考えでもあります。
ISO9001とは、国際標準化機構(ISO)が定めた品質マネジメントシステムの規格のことです。企業の製品やサービスが一定の品質を保っていることを示すものであり、規格の取得は、ISOによって品質が保証されていることを意味します。
ISO9001の考えでは、短期的な視点による改善よりも、長期的な視点による改善を評価しています。国際的な評価を得るためには、長期的な改善計画が必要といえるでしょう。
なぜ継続的改善が必要なのか?
なぜ業務改善を継続して続ける必要があるのか。その理由について紹介します。
製造現場が抱える典型的な課題
継続的な改善が必要な理由は、品質向上を目指し、顧客満足度を高めるためです。他社との市場競争に勝つためには、顧客ニーズを満たす必要があります。変化の激しい顧客ニーズを満たすためにも、変化に合わせた改善が求められます。
また、形骸化や属人化といった問題も、近年では課題として挙げられています。人材不足の影響から教育や交代がうまくいかない状態です。継続的な改善によって生産プロセスを見直し、生産が問題なくできるよう体制を整えます。
ほかにも、生産におけるムダを省くことで、コスト削減や納期の短縮などの課題解決も目指します。
それら製造現場が抱える典型的な課題を解決するためにも、一度の改善で終わらせず、継続的に改善し続ける必要があるでしょう。
改善を続ける文化がもたらす効果
改善を続けることは、文化を作ることも意味します。続けることで活動が定着し、職場風土を形成するからです。継続的改善が根底的な文化となることで、企業の成長を促すことにつながります。
有名な文化としては、トヨタ自動車が掲げる「トヨタ生産方式」が挙げられます。トヨタ生産方式とは、トヨタ自動車が開発した生産のムダを排除する方式であり、ムダを排除することで、作業時間の削減や段取り時間の削減などを実現しました。
作られた文化は自社の財産ともいえ、製品やサービスの質を高めてくれます。
また、洗練された現場は、作業員のモチベーションを高めることにもなります。環境がより良くなれば、さらに作業員のモチベーションは高まり、離職率を下げる結果にもなるでしょう。
継続的な改善は、ただ生産プロセスを改善するだけではなく、企業の根底を作ることも意味します。
継続的改善の進め方|基本フレームと現場導入のコツ
継続的な改善はどのように行なえばいいのか。この見出しでは、基本となるフレームワークや、現場導入のコツなどを紹介します。
PDCAを運用するだけでは不十分?
継続的改善の基本は、PDCAを運用することです。計画した内容を実行し結果を評価、そして、評価した内容を基に新しい計画を立案することで、前サイクルよりも改善された、より良いプロセスを実行できます。
しかし、PDCAサイクルをただ回せばいいわけではありません。形式的に回していては、作業が形骸化してしまいます。改善すべきポイントにも目が向かなくなり、意味のない時間や労力を浪費してしまうでしょう。
そのため、PDCAサイクルを行なう際は、目的を持って取り組むことが大切です。チームで話し合い、具体的な施策を考えることで、1サイクルごとに意味が生まれます。
また、PDCAサイクル以外にも、「QC7つ道具(例:パレート図、特性要因図など)」のような問題解決を目指したフレームワークも存在します。PDCAサイクルと組み合わせて行なうことで、より効果が期待できるでしょう。
PDCAは「計画」「実行」「測定・評価」「対策・改善」は4項目ですが、ほかにも、「計画」の前に「目標設定」を付け足したり、「改善」の後に「標準化」を行なったりなど、PDCAに囚われない継続的改善を行なってください。
現場に定着させる5つの実践ポイント
PDCAサイクルを運用する際は、以下のようなポイントを踏まえて行なうと、より良い改善が行なえます。
- 小さな改善でも承認・評価する
- 改善内容を“見える化”して共有
- 改善前後の数値・効果を記録する
- 1人1改善ルールで全員参加を促す
- 成功した改善は標準化→横展開へ
1.小さな改善でも承認・評価する
一つ目は、小さな改善であっても評価することです。PDCAの基本は小さな改善の積み重ねであり、繰り返し行なうことで大きな成果につながります。
PDCAが失敗する原因の一つとして、「効果を求めすぎる」ことが挙げられます。改善するのだから効果が出るのは当たり前と考え、劇的な変化を求める人は多いです。
しかし、劇的な変化は簡単ではなく、立案をするのが難しくなります。すでにサイクルを繰り返して改善を重ねている場合は、尚更、改善案が思い浮かばないでしょう。
劇的な案が思い浮かばず手詰まりとなってしまわないよう、小さい改善案も立案し、実施することが大切です。
2.改善内容を“見える化”して共有
二つ目は、誰でも改善内容がわかるようにすることです。改善内容を見える化することで、情報共有がしやすくなります。
改善内容がわからないと、次の改善に活かすことができません。チームで話し合うこともできず、すぐに立案が行き詰ってしまいます。活動内容がわからないことから、「何をしているのか」「なぜ行なうのか」も不明となり、チームのモチベーションを下げる結果にもなるでしょう。
PDCAで大切なのは、多角的に評価することです。別の意見や視点を取り入れることで、新たな問題点が見つかり、より良い改善を可能にします。
チームが一丸となって継続的改善に取り組めるよう、活動内容や結果を見える化し共有してください。
3.改善前後の数値・効果を記録する
三つ目は、結果を記録することです。記録をしないと改善による効果がわからず、さらなる改善が難しくなります。
特に、数値の記録はとても大切です。変化が一目瞭然であり、評価しやすいといえるでしょう。
評価をするためなのはもちろん、資料として残したり、人に説明するためにも、活動内容はすべて記録するようにしてください。
4.1人1改善ルールで全員参加を促す
四つ目は、チーム全員で活動に参加することです。活動に参加することで継続的改善への自覚を持てるようになり、自発的に取り組むようになります。
改善までの経過を知ることで、継続的改善の理解度も高まるでしょう。
また、参加を促す際は、1人1改善のルールを決めておくと良いです。考えを発言することで、より活動をしている実感が持てます。立場ごとの視点が得られ、多角的に評価できます。
5.成功した改善は標準化→横展開へ
五つ目は、改善の横展開も考えることです。一つの改善ばかりに固執せず、派生させることで幅広い改善を目指します。
もちろん、一つのことに取り組むのは大切ですが、改善を続けていけばいつかは頭打ちとなります。結果が出にくくなることで、チームのモチベーションも低下してしまうでしょう。
頭打ちになっていると感じたら、成功した活動を標準化して業務へ落とし込み、横展開することで、幅広い改善を目指してください。
継続的改善を現場に定着させるには?
PDCAサイクルで改善をしたら、内容を標準化して日々の業務に定着させます。実際に効果が出てこそ、意味のある活動といえるでしょう。
継続的な改善を現場に定着させるには、どのようにすればいいのでしょうか?
継続の壁と乗り越え方
継続的改善を現場に定着させるためには、継続ができるようにすることが大切です。いくら効果があるとしても、活動に手間がかかるようでは、次第に活動が面倒になります。
継続の壁を乗り越える方法はいろいろありますが、特に有効的なのは活動を習慣化させることです。日常的に活動を行なえば、「活動することが当たり前」と思うようになり、活動のモチベーションを落とすことなく続けられます。
ただ、日常的に行なうことで形骸化する問題も出てきます。毎日行なうからこそ、行なう意味を忘れがちです。
表面だけなぞった意味のない活動にしないためにも、定期的に研修を設けるなどして、活動の意味を理解させることも大切です。
中堅社員にこそ求められる役割
継続的改善を行なううえで、中堅社員はリーダーシップを取ることが大切です。活動は作業員一人ひとりが自主的に取り組む必要がありますが、好き勝手に行動されてしまうと、活動全体に支障が出てしまいます。目指す方向を統一するためにも、中堅社員が活動のリーダーとなって、チームを牽引する必要があります。
また、後輩の育成や組織内コミュニケーションの円滑化なども、中堅社員の役割となります。リーダーシップも含め、組織全体のパフォーマンスを向上させることが、中堅社員の主な役割といえるでしょう。
PDCAの話し合いをする際も、チーム全体が活動に参加できるよう、進行を促してください。
まとめ:継続的改善は“文化”と“仕組み”の両輪で進める
継続的改善とは、単なる業務プロセスの見直しではなく、企業文化として根づかせていく取り組みです。
PDCAや各種フレームワークを活用しながら、「文化」と「仕組み」の両輪で支えることで、変化に強く、持続可能な製造現場を実現できます。
今こそ、自社に合った改善の仕組みを整え、継続的な成長を目指してみてはいかがでしょうか。