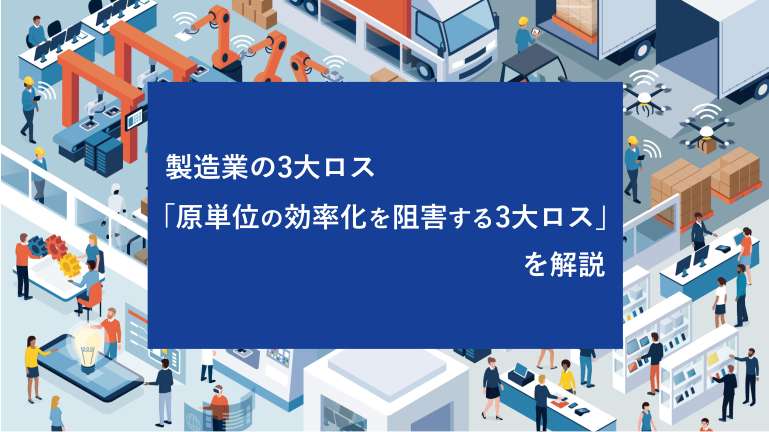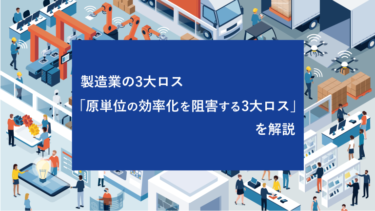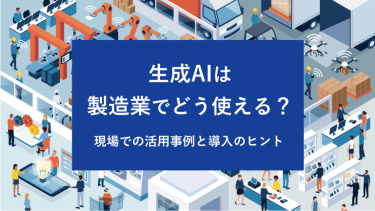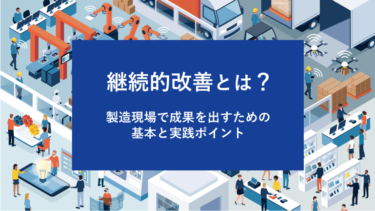企業の利益を損なう生産ロス。ロスの発生により、時間、資材、人材など、さまざまな生産コストを余計に消費することから、生産ロスの減少は製造における課題の一つとして挙げられています。
中でも、原単位の浪費を増やすロスのことを「原単位の効率化を阻害する」と呼び、大きく3つに分けて考えることができます。省エネによる出費削減を目指すためにも、ロスの内容や対策について知っておく必要があるでしょう。
原単位の効率化を阻害する3大ロスとはどのような生産ロスを指すのか。ロス改善に向けたTPM活動についても紹介します。
製造業における原単位の効率化を阻害する3大ロスとは?
原単位の効率化を阻害する3大ロスとは、時間、エネルギー、資産などが増やすロス(要因)のことです。「歩留まりロス」「エネルギーロス」「型・治具ロス」の3項目が挙げられ、生産リソース(コスト)を増やしてしまいます。
生産リソースの効率化は、企業の利益を増やすために重要な要素です。作業時間を節約できれば生産数が増えますし、エネルギー消費を抑えられれば出費を少なくできるでしょう。
製造業における重要な要素としてQCD(品質、コスト、納期)が挙げられており、その一つとしてコストが数えられています。
コスト削減による自社の利益向上、さらには、顧客満足度の向上を目指すためにも、原単位の効率化を目指し、それを阻害するロスを解決する必要があります。
原単位とは?
原単位とは、一定量の生産物をつくるために使用する、または排出するものや時間などの量のことです。簡単に説明すると、生産に必要となる燃料や時間などのことを指します。
つまりは、「原単位の効率化を阻害するロス」とは、省エネを阻害するロスともいえるでしょう。
近年は、CO2削減などの理由から、省エネ対策が推奨されています。SDGsを意識したクリーンな生産を目指す意味でも、原単位を意識することが大切です。
原単位の効率化を阻害する3大ロス
原単位の効率化を阻害する3大ロスとはどのようなロスを指すのか。それぞれのロスについて確認してみましょう。
歩留まりロス
歩留まりロスとは、製品の出来高に関するロスのことです。歩留まりとは投入リソースに対する出来高の割合を示すものであり、何らかの原因によって、想定よりも出来高が悪くなります。
例えば、製品を100個作るとします。しかし、実際に生産を行なってみると70個しかできませんでした。100個分の生産リソースを投入したのに完成品が70個では、30個分の生産リソースをムダにしたといえるでしょう。
ほかにも、精度が低い加工で予定よりも資材を削り過ぎてしまったなど、生産リソースに対して結果がそぐわないと利益が少なくなります。
利益を増やすためには、原単位を意識した効率のよい生産が求められます。
エネルギーロス
エネルギーロスとは、消費エネルギーに関するロスのことです。生産に問題があることで、電気、燃料、水などの生産リソースを過剰に消費してしまいます。
単純に、消費エネルギーが多いと金銭がかかります。最近は電気代やガソリン代も高くなっており、節約を意識する人も多いことでしょう。
工場や会社は規模も大きく、その分の出費も多くなります。残業時間を減らして機械の稼働率を減らしたり、蛇口をこまめに閉めて節水するなどをして、省エネ対策をすることが大切です。
型・治具ロス
型・治具ロスとは、治具(道具)の製作に関するロスのことです。ムダに修理や製作を繰り返すことで、出費がかさんでしまいます。
特に、製作を外注している場合は、金額も高くなります。稼いだ金銭を治具の製作に費やしていては、会社の利益になりません。
消耗や破損を抑えるためにも、治具を大切に扱う必要があります。
生産効率を阻害する16大ロス
製造の現場では、「原単位の効率化を阻害する3大ロス」以外にも、ロスとなる要素がほかにもあります。利益を向上させるためにも、ほかのロスについても確認をしておいてください。
人の効率を阻害する5大ロス
人の効率を阻害するロスとは、作業効率を下げるロスのことです。ムダな要素や要因によって作業に問題が生じ、生産数を下げてしまいます。
人の効率を阻害するロスには、以下の5つが挙げられます。
- 管理ロス
- 動作ロス
- 編成ロス
- 自動化置換ロス
- 測定調整ロス
管理ロスとは、指示待ちができていない時に発生するロスのことです。材料が到着するのに待つ時間など、作業員への管理(指示)ができていないことで人材や時間をムダにしてしまいます。
動作ロスとは、作業が遅い時に発生するロスのことです。作業動線が悪く遠回りしてしまうなど、動作が効率化していないことで時間をムダにしてしまいます。
編成ロスとは、ライン作業に遅れが生じた時に発生するロスのことです。ボトルネックによって後作業が停止してしまうなど、流れ作業の問題によって時間をムダにしてしまいます。
自動化置換ロスとは、アナログ作業をする時に発生するロスのことです。測定結果を手作業で入力するなど、デジタルでできることをアナログ作業をすることで、人材や時間をムダにしてしまいます。
測定調整ロスとは、不要な検査を繰り返す時に発生するロスのことです。検査や測定を何度も必要以上に繰り返すことで、人材や時間をムダにしてしまいます。
作業効率の低下は、生産数を低下させる要因となります。また、効率が悪いことで作業員への負担も大きくなり、不満や怪我などが生じてしまうでしょう。生産数を上げるのはもちろん、作業員が気持ちよく作業するためにも、ロスを削減する必要があります。
設備効率を阻害する7つのロス
設備効率を阻害するロスとは、設備や機械の稼働を止めてしまうロスのことです。何らかの理由によって設備や機械を止めてしまい、生産数を下げてしまいます。
設備効率を阻害するロスには、以下の7つが挙げられます。
- 故障ロス
- 段取り・調整ロス
- 刃具交換ロス
- 立上がりロス
- チョコ停・空転ロス
- 速度低下ロス
- 不良・手直しロス
故障ロスとは、設備や機械の故障により発生するロスのことです。故障によって設備や機械を動かすことができず、生産ができなくなります。
段取り・調整ロスとは、段取りの遅れにより発生するロスのことです。ロットの切り替えなどの段取りが悪いことで、生産を止めてしまいます。
刃具交換ロスとは、治具交換の遅れにより発生するロスのことです。治具の交換やメンテナンスなどが遅れることで、生産を止めてしまいます。
立上がりロスとは、生産開始が遅れることで発生するロスのことです。立上げの準備が遅れてしまうことで、時間をムダにしてしまいます。
チョコ停・空転ロスとは、小停止を繰り返すことで発生するロスです。たとえ数秒の停止であっても繰り返せば停止時間は長くなり、結果として大停止と変わらない時間、機械を止めてしまいます。
速度低下ロスとは、機械の動作が遅いことで発生するロスのことです。機械の調子が悪く稼働率が低下することで、生産数を下げてしまいます。
不良・手直しロスとは、不良品の対応によって発生するロスのことです。機械の修理、指導のやり直し、不良品の廃棄など、不良品の発生によって作業が増えることで、本来の生産業務を邪魔してしまいます。
設備や機械の停止は、生産数を下げる要因となります。修理が必要な場合は出費もあり、大きな利益損害となるでしょう。生産数を下げないためにも、生産を止めない対策や工夫が必要です。
シャットダウンロス
シャットダウンロスとは、意図的に機械を止めた時に発生するロスのことです。メンテナンスや清掃など、機械の故障とは別に機械を止めますが、止めている時間は生産ができず、故障などと同じように生産数を下げる結果となります。
シャットダウン中の整備は、安全かつ効率よく作業する上で欠かすことができない要素です。そのため、防ぐことのできないロスともいえるでしょう。ロスとなる時間を少しでも短くするためにも、計画的に作業を進めることが大切です。
また、シャットダウンロスは設備や機械に関係することから「設備効率を阻害するロス」に含めて考えることもあります。
しかし、シャットダウンロスは意図的かつ防げないロスであることから、ほかのロスとは別に扱うなど、評価する人によって意見は分かれるようです。
ロスを削減するためのTPM活動の8本柱
TPM(Total Productive Maintenance)活動とは、生産現場全体が一丸となって取り組む安全活動・考えのことです。一人ひとりが意識して活動に取り組むことで、より大きな効果となります。
ロスを減らすための対策は必要ですが、一人二人が頑張っても、結果はあまり期待できません。ライン作業のように複数人が協力して作業する現場もあるため、結果を出すためには、生産に関わる全員が意識する必要があります。
全従業員が協力しロスを削減するためにも、以下の8項目を意識し取り組むようにしてください。
- 教育・訓練の体制づくり
- 安全・衛生と環境の管理体制づくり
- オペレーターの自主保全体制づくり
- 品質保全体制づくり
- 保全部門の計画保全体制づくり
- 製品・設備開発管理体制づくり
- 管理・間接部門の効率化体制づくり
- 生産システム効率化の個別改善
教育・訓練の体制づくり
作業員の能力を高めるための活動です。必要な知識や技術を取得することで、ミスを減らし作業能率を高めることができます。
また、技術を標準化すれば、スキルによるばらつきをなくせます。効率よく作業が進められ、品質の維持や生産効率の向上が期待できるでしょう。
また、16大ロスやTPM活動を理解させる意味でも必要です。TPM活動は生産現場全体が一丸となって取り組むことが重要であり、一人ひとりの保全意識が求められます。表面だけなぞって活動を続けていても、次第に活動は形骸化してしまい、意味を成さなくなってしまいます。
意識改善には、「なぜ必要なのか」「どのような効果があるのか」を理解させることが大切です。TPM活動を続けていくためにも、しっかりとロスによる影響や活動の意味を伝えてください。
安全・衛生と環境の管理体制づくり
生産によって発生する負荷を改善するための活動です。労働環境を見直すことで、臭い、汚い、危ないといった負担を改善し、作業がしやすい環境を整えます。
環境が悪いとミスや労災が起こりやすくなるため、トラブルを防ぐ意味でも環境づくりは大切といえるでしょう。
良い環境は作業員のモチベーションも向上させ、作業能率も高めてくれます。
また、環境負荷を減らすことも、SDGsを掲げる近年では重要になっています。排水やプラスチックの処理なども見直し、公害ゼロを目指してください。
オペレーターの自主保全体制づくり
オペレーター(作業者)自らが保全を行なう活動です。点検や清掃はもちろん、必要なら補修や補給も行ない、設備や機械が正常に作動するよう取り組みます。
機械に最も触れる人物はオペレーターです。日常的に使用しているからこそ異変に気が付きやすく、最も保全がしやすい人物といえます。
自分で使う設備や機械は自分で管理ができるよう、扱い方を身に着けさせておく必要があるでしょう。
また、オペレーターだけが身に着けているようでは、他の人が代わりをできずに属人化する恐れがあります。オペレーター以外の人も管理ができるよう、指導やマニュアルの準備を行なってください。
品質保全体制づくり
不良品を発生させないための活動です。不良品を通さない検査体制の構築はもちろん、ゴミの混入を防ぐための清掃や不良品の排出を防ぐためのメンテナンスなど、品質が保たれるための体制を整えます。
品質はQCDの一つにも挙げられており、品質の低下は顧客満足度を下げる要因となります。製品ロスを防ぐためだけではなく、顧客からの信用を保つためにも、重要な保全活動です。
保全部門の計画保全体制づくり
長期的に保全を行なうための活動です。点検時期やメンテナンスの頻度、補修のやり方や部品交換の方法など、保全スケジュールや保全マニュアルの管理を行ないます。
事前に計画を立てておけば、効率よく保全作業が行なえます。急なトラブルに対しても、落ち着いて対応ができるでしょう。
また、効率よく進めることで、機械を止める時間を最小限に抑えられます。結果として、ロスの削減につながるわけです。
近年は、AIを活用した管理も行なわれており、予知保全を基にした計画保全も可能になっています。
製品・設備開発管理体制づくり
ロスを発生させない開発・設計を行なう活動です。開発段階からメンテナンス性や整備効率などを考慮することで、将来的なロスを減らすことにつながります。
使われる素材や形状によって、故障リスクや使いやすさは大きく変わってきます。より良いモノを作るためにも、研究部門を始め、他部門との連携をしっかり取れるようにしましょう。
管理・間接部門の効率化体制づくり
生産部門以外に関係するための活動です。研究部門や搬入部門など、間接的に関わる部門も強化することで、より効率的に生産が行なえるようになります。
TPM活動は、生産部門だけではなく、生産に関わる全ての人が対象です。他部門の連携を強化するのはもちろん、それぞれの部門内で効率化を進めることが大切といえます。
特に重要なのは、他部門に渡った情報共有です。生産休止に気が付かず生産をしてしまうなど、情報共有に遅れが生じると、ムダな生産をしてしまいます。情報に間違いがあっても、必要とする製品は作れないでしょう。
効率のよい生産を行なうためには、迅速かつ正確に情報共有することが大切です。そのためには、連絡するための方法を見直したり、生産管理システムなどによる一元管理をする必要があります。
生産システム効率化の個別改善
生産システムを見直し、効率化することでロスを減らす活動です。一つずつムダを改善しておくことで、生産全体が効率化されます。
個別に進める理由は、一度に改善を進めても手が回らないからです。見直す部分は製品の設計から出荷までと幅広く、どこから手を着ければいいのか迷ってしまいます。そのため、各プロセスを個別に調査し、一つずつ確実に改善していくことが重要となります。
設備の効率化や作業の標準化、作業動線の改善など、効率よく作業するためにはどうすればいいかを見直してみてください。
まとめ:3大ロスを可視化すれば、改善の軸が見える
利益を上げるためには、原単位を下げることがとても重要です。出費を抑えれば、その分を利益として加算できます。
しかし、原単位ははっきりと目に見えるものではなく、意識しづらい要素です。たとえ出費がかさんでいたとしても、気が付かずにそのまま生産を続けてしまうでしょう。
そのようなことがないよう、原単位は可視化することが大切です。目に見えて比較ができれば、どの程度消費しているかがわかります。問題箇所がわかれば、改善の軸も見えてくるはずです。
原単位の効率化を阻害する要因を改善し、出費を抑えた効率のよい生産を目指してみてください。
また、原単位の可視化は、生産管理システムを利用するとわかりやすいです。生産効率の向上も期待できますので、ぜひ活用してみてください。