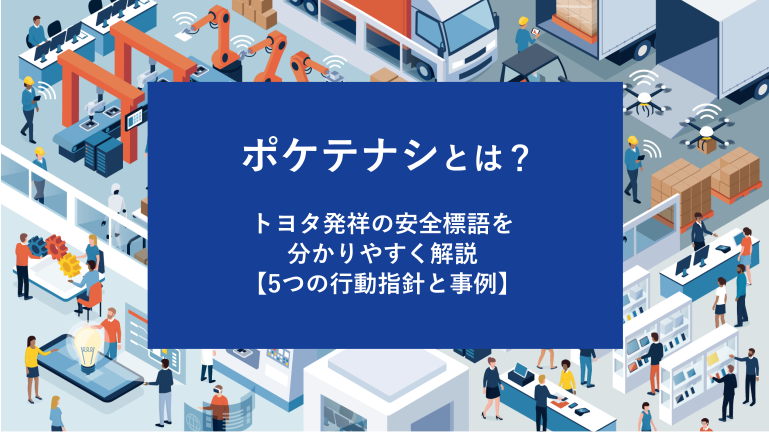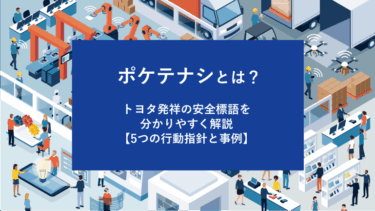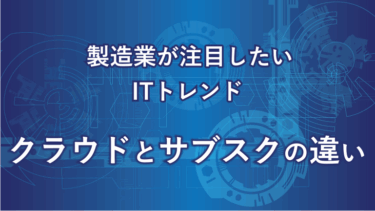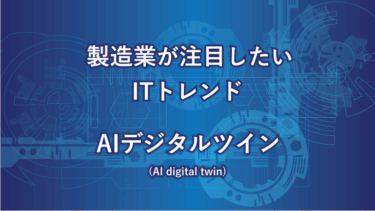普段、工場内での安全対策は何を行なっていますか?安全対策は仕事をするうえで重要な要素であり、どの企業も、それぞれが違った安全対策を取っていると思います。
その中でも近年、歩行時の安全行動をまとめた標語「ポケテナシ」が注目されています。トヨタが現場の安全意識を高める目的で示したシンプルな5行動で、導入しやすさから多くの企業が採用しています。
より安全な労働環境を目指すためにも、ぜひ「ポケテナシ」について確認してみてください。「ポケテナシ」の意味や導入効果などを紹介します。
ポケテナシとは何か
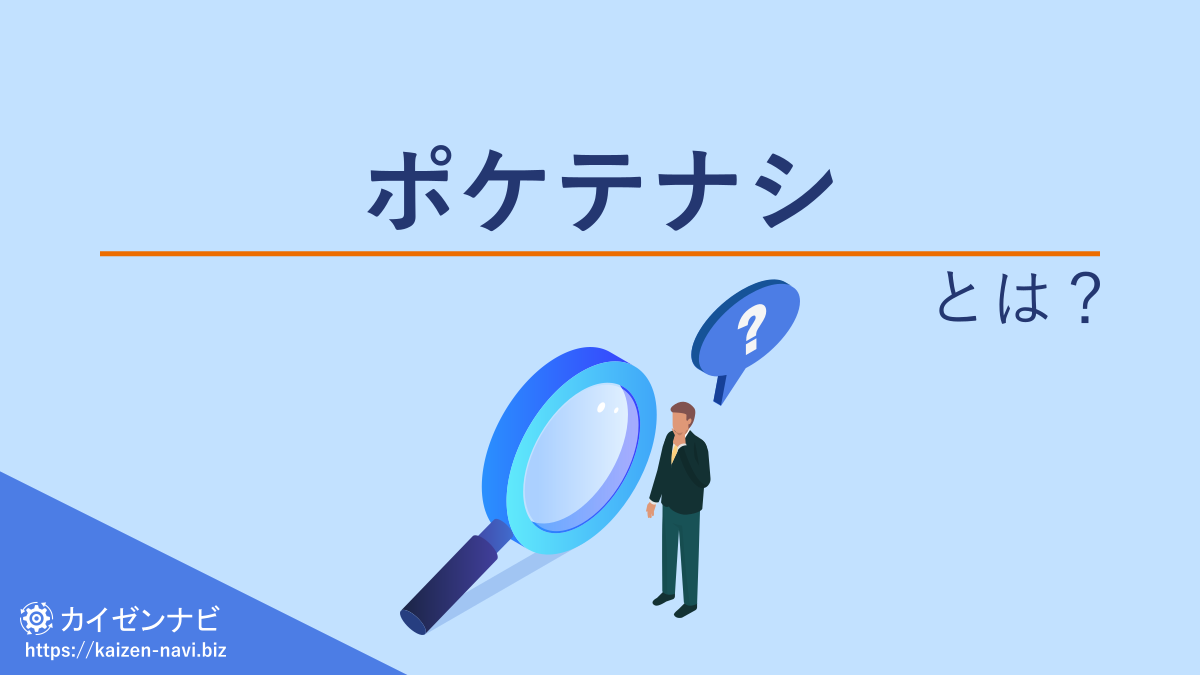
「ポケテナシ」とは何なのか。「ポケテナシ」と呼ばれるのには、以下のような理由があります。
トヨタが提唱した安全標語「ポケテナシ」の定義
「ポケテナシ」とは、トヨタが提唱した歩行に関する安全標語のことです。現場での事故を未然に防ぐための行動方針として5つ挙げており、それら5つの行動方針を合わせて「ポケテナシ」と呼びます。
「ポケテナシ」という言葉の由来と背景
「ポケテナシ」と呼ばれる由来は、単純に言葉が覚えやすいからです。5つの取り組みをそれぞれ覚えるのは大変ですが、「ポケテナシ」だけなら、ユニークな言葉であることから覚えやすいといえます。
もちろん、言葉の中身を覚える必要がありますが、取り組みの個数や頭文字などがわかれば、内容も覚えやすくなるでしょう。
「ポケテナシ」の目的は、安全に行動をするためのものです。そのため、言葉で覚えるだけでは意味がなく、体で覚える必要があります。
物事を覚える際に大切なことは、繰り返すことです。繰り返すことで言葉や内容が反復され、より深く記憶されていきます。そして、繰り返すためにはわかりやすいことが大切です。長い言葉だと繰り返すのも面倒になり習慣化されません。
内容を反復しやすくするためにも、覚えやすいようまとめられています。
ポケテナシの5つの要素と行動指針
「ポケテナシ」には、それぞれ以下のような意味や目的があります。
「ポ」ポケットに手を入れて歩かない

「ポ」は、「ポケットに手を入れて歩かない」ことです。ポケットに手を入れたままでは、転んだ際などですぐに手を出すことができません。受け身が取れないことで大怪我をするリスクができてしまいます。
そのような事故を防ぐため、移動中はポケットから手を出して、いつでも手が使えるようにする必要があります。
また、両手に物を持っている状態も同じです。ポケットに入れているときと同様に、何かあってもすぐに手が出せないでしょう。荷物が多い時は台車を使うなどして、常に手がフリーな状態を保つようにしてください。
「ケ」携帯電話を歩きながら使用しない

「ケ」は、「携帯電話を歩きながら使用しない」ことです。電話をしたままでは、注意が散漫し周囲の状況を把握できません。音も聞こえにくいことから、周囲に対して無防備状態といえます。後ろから台車が迫ってきていても、電話した状態では気が付かずに衝突されるおそれがあるでしょう。
そのような事故を防ぐためにも、移動中は電話やメールを確認しないようにします。ほかに意識が向かなければ、台車が迫ってきていても回避することができます。電話やメールをしたいときは、道の端に移動し、安全を確保したうえで利用してください。
また、歩きながら同僚と会話する人もいますが、電話する場合と同様に危険です。会話に夢中になるあまり、周囲への危機管理を怠ってしまうでしょう。
電話に限らず、何かする際は移動を止め、転倒や衝突がないよう気を付けてください。
「テ」階段の昇り降りは手すりにつかまる

「テ」は、「階段の昇り降りは手すりにつかまる」ことです。手すりを持ったまま階段を昇降すれば、階段で転んだ際でも一番下までの落下を防ぐことができます。
また、物を持った状態も同様に危険です。転倒時にとっさに手が出せないだけではなく、足元が見えないことで転倒しやすくなります。
階段の落下は、怪我や死亡のリスクが高く大変危険です。普段は問題がない人も、仕事の忙しさや疲れから足を踏み外す可能性もあるでしょう。万が一のリスクを踏まえ、年齢にかかわらず、階段を昇降する際は手すりにつかまるよう心がけてください。
また、古い工場だと手すりがない場合もあります。そのような場合は、いつ転倒しても大丈夫なよう、両手がフリーな状態で昇降するよう心がけましょう。
「ナ」斜め横断をしない

「ナ」は、「斜め横断をしない」ことです。斜め横断をすると相手の動線を邪魔してしまい、衝突するリスクが高まります。予期せぬ横断ならなおさら予想ができず、回避できずに衝突をしてしまうでしょう。
現場によってはフォークリフトや運搬ロボットも走行しており、衝突によって大怪我になりかねません。事故を回避するためにも、決まった場所での横断や、声かけや指差し確認による安全確認をすることが大切です。
「シ」指差呼称の徹底

「シ」は、「指差呼称を徹底する」ことです。指差すことで意識が向き、より注意して見ることができます。道を横断する際も、指差呼称により見落としを減らし、安全性をより高められるでしょう
また、声を出すことで、周囲に存在を伝えることにもなります。工場内は死角が多く、曲がり角で衝突事故になりやすいですが、声を出して存在を伝えていればお互いに衝突を避けられます。
長く仕事を続けるほど、業務に慣れて油断しがちです。リスクを理解し安全確認を心がけるためにも、行動をする際は指差呼称を徹底してください。
指差呼称は、認知資源を対象物に集中させ、見落としや誤判断を減らすための基本手法として産業安全分野で推奨されています。安全衛生情報サイトにも解説があります。
なぜポケテナシが重要なのか
「ポケテナシ」が注目されている理由には、以下のようなことがいえます。
現場で多い事故原因とヒューマンエラー
厚生労働省の令和5年データによると、製造業の休業4日以上の死傷者数は27,194件。内訳では「転倒」5,823件で2番目に多く、最多は「はさまれ・巻き込まれ」6,377件です。
全産業計では、事故の型別死傷者数で「転倒」が最多の36,058件、死亡者数の最多は「墜落・転落」204人です。
また、激突に関しても死傷者数は6,925件、死亡者数は47人です。
以上のことから、転倒や衝突など、移動による事故が多いことが予測できます。特に製造業は物が多く、ちょっとした不注意から労災になりやすいといえるでしょう。
労災件数を減らし安全に仕事をするためにも、「ポケテナシ」による取り組みが重要といえます。
安全文化を習慣化するための仕組み
安全文化を守るためには、小さいトラブルを解決していくことが大切です。大きな労災の陰には多数の小さなトラブルが発生しており、その小さなトラブルの一つが、大きな労災へと発展するからです。
製造業界では、このような関係のことを「ハインリッヒの法則」と呼びます。「1件の重篤な事故の背後には29件の軽度な事故があり、そのさらに背後には300件の事故未遂が存在する」と考えられています。
事故未遂は、あくまでも事故に発展していないだけで、状況が少し違えば事故に発展していた事案です。事故を減らすためには、まず事故未遂から解決していく必要があるでしょう。
安全文化を習慣化させる方法はいろいろありますが、最もシンプルなのは毎日の業務へ取り入れることです。毎日行なっていれば、自然と取り組みが身につき、意識せずとも安全対策を行なうようになります。
「ポケテナシ」は、内容の単純さから毎日の業務へ取り入れやすい取り組みといえます。安全文化を習慣化させやすいことも、「ポケテナシ」が注目される理由といえるでしょう。
トヨタでの運用事例
発案元であるトヨタでは、「ポケテナシ」を実施するため、以下のような取り組みを行なっています。
安全パトロールによる徹底
活動を掲げるトヨタでは、「ポケテナシ」が守られているかを確認するため、日常的に安全パトロールを実施しています。違反が見つかった場合にはその場で注意し安全の重要性を教えるなどをして、「ポケテナシ」の実施を徹底しているのです。
車の速度取り締まりと同じで、日常的なパトロールは従業員の安全意識を高めます。「動作を見られていないか」と心配になることで、積極的に実施するようになるわけです。もちろん、普段から行なっていれば習慣となり、意識せずとも自然に「ポケテナシ」を実施するようにもなります。
安全パトロールはただ違反者を見つけるために行なうだけのものではなく、取り組みを意識させることで、「ポケテナシ」を習慣化させているわけです。
ヒヤリハット事例の共有と教育活用
ヒヤリハット事例として、「ポケテナシ」を挙げることもあります。ヒヤリハットとは、「ヒヤリとした事例」や「ハッと気が付いた事例」を指す出来事であり、つまりは、事故寸前の出来事といえます。
例えば、「曲がり角を曲がった際にフォークリフトと衝突しそうになった」「搬送する資材が多く足元が見えない」といったことです。どちらも「ポケテナシ」に関係することであり、「ポケテナシ」を通じて安全確認や労働環境の改善を促せます。
情報を共有することで従業員全員がリスクを理解し、安全に気を付けて作業ができるようになるわけです。
経営層を含めた全員参加型の取り組み
「ポケテナシ」を実施するため、トヨタでは経営層も含め取り組みに参加しています。「ポケテナシ」の取り組みは、全従業員が取り組むべき内容であり、経営層も例外ではありません。現場以外の場所でも、「ポケテナシ」の実施はトラブル回避に役立ちます。
なにより、経営層が理解していないと、取り組みが順調に行なわれません。規則の変更や設備の改修などをする際は、経営層の協力が必要不可欠だからです。情報共有をして相互理解を深める意味でも、取り組みへの全員参加は重要といえるでしょう。
ポケテナシがもたらす効果
「ポケテナシ」は、ただ安全確認をするだけではありません。安全確認によって、さらなるメリットもあります。
「ポケテナシ」を意欲的に取り組むためにも、ポケテナシがもたらす効果について知っておきましょう。
事故リスクの削減とヒヤリハット防止
一つ目は、リスク回避やヒヤリハットの防止です。「ポケテナシ」は危険を事前に察知するための取り組みであり、実施することで、事故を未然に防ぐことができます。
生産における事故は、生産効率も低下させます。従業員の欠員による人手不足、作業機械の停止による生産の遅れ、動作エラーによる不良品の発生など、生産への悪影響は大きいです。
さらに、労災保険給付の支出、従業員のモチベーション低下などもあり、労災は絶対に防ぐべき課題の一つといえるでしょう。
「ポケテナシ」によって従業員の安全が守れるのはもちろんですが、ほかにも、生産効率を保つ・向上させる効果が期待できます。
安全意識向上とチームワークの強化
二つ目は、安全意識が向上することによるチームワークの強化です。「ポケテナシ」をチーム全員が取り組むことで、チーム内に連帯感が生まれます。
生産は、広い目線で見るとチームワークが重要な業種です。ライン作業が良い例であり、次の工程の人との連携がうまくいかないと、生産に遅れが生じてしまいます。
スムーズな生産を行なうためには、チームはもちろん他部門との連携が必要です。そのためにも、「ポケテナシ」を通じてチームワークを高める必要があります。
また、チームワークが高まれば、仕事もしやすくなります。作業効率が向上するだけではなく、離職率も低下するのです。従業員同士のサポートがしっかりしていることから新人も参入しやすくなり、人材不足の解消にもなるでしょう。
企業価値・信頼性の向上
三つ目は、企業の価値や信頼を向上させられることです。「ポケテナシ」によって生産効率が維持され、QCD(品質、コスト、納期)が向上することで顧客からの信頼を勝ち取ります。
また、安全な労働環境であることも、企業の価値といえます。働きやすい環境は、クリーンなイメージを持たれやすいです。従業員からは「働きやすい職場」、新入社員からは「従業員を大切にする職場」として見られ、高く評価されます。顧客や株主からも「安全を意識した無事故の職場」として評価され、好印象を持たれるでしょう。
価値や信頼の向上はブランドイメージを高め、企業の成長を促します。
ポケテナシを自社に導入するには
「ポケテナシ」を導入するためには、継続的な取り組みが必要です。ただ口頭で伝えるだけでは従業員の耳に残らず、すぐに取り組みを忘れられてしまいます。
「ポケテナシ」を定着させるための方法として、以下のようなことを行なってみてください。
まずは「定義と5つの行動」を徹底周知する
「ポケテナシ」を定着させるためにも、「ポケテナシ」の定義や行動を正しく伝えることが大切です。「ポケテナシ」を行なう理由やどのように行なうのかを具体的に周知させることで、取り組みを守るようになります。
取り組みが守られない理由の一つが、「取り組みの意味がわからない」からです。なぜ行なうのかがわからないと、効果に実感が持てません。実感が持てないことで次第に面倒にも感じるようになり、形骸化や消滅をしてしまいます。
そのような事態を防ぐため、従業員一人ひとりが取り組みを理解する必要があります。入社時の研修で教えるのはもちろん、定期的に安全講習も実施し、安全文化を伝えていくことが大切です。
ポスターやチェックシートなどツールの活用
より「ポケテナシ」を意識させるため、ポスターやチェックシートなどのツールを活用すると良いです。毎日目にする場所にポスターがあれば自然と頭に残りますし、チェックシートで確認させれば、自然と取り組みが身につきます。
イラストや写真などを使用すれば、直感的に取り組みを理解しやすくもなるでしょう。近年は技能実習生を含め、海外からの労働者も増えています。目が悪い人もいますので、画像によるわかりやすさはとても重要です。
また、「ポケテナシ」を必ずセットで運用する必要はありません。階段部分には「テ」についてのポスターを、フォークリフトの通り道となる場所には「ナ」のポスターといったように、場所に合わせて提示すると、取り組みを体感しやすくなります。
普段から意識する機会を増やし、無意識でも実施できるよう体に覚えさせましょう。
自社課題に応じた「+αルール」の追加
より安全性を高めるためには、自社に合わせた新しいルールを作ることも大切です。
例えば、「台車を運んでいる際にぶつかりそうになった」といったヒヤリハット報告があったとします。そのような場合は、「台車は2人以上で運び、1人が安全誘導を行なう」といったように、新しいルールを追加するわけです。
同じ製造業であっても、薬品工場と製紙工場とでは労働環境は変わります。危険が異なることでヒヤリハット報告も変わってきますので、自社課題に合わせたルールの改訂が必要なのです。
「ポケテナシ」の導入で満足するのではなく、課題を追求し、継続的な安全対策に取り組んでください。
導入チェックリスト
- 5要素の周知:朝礼での唱和/月1回テスト
- 掲示位置:階段(テ)、交差点(ナ・シ)、通路入口(ケ)、更衣室出口(ポ)
- ルール:歩行中の携帯電話操作禁止、台車は二人運搬+誘導を標準(ヒヤリハットに応じて+α)
- 監査:日次巡視、週次で違反是正完了を確認
- KPI:ヒヤリハット件数、携帯違反件数、転倒・激突発生率、指差呼称実施率
まとめ:ポケテナシは「小さな行動で大きな安全を守る」標語
「ポケテナシ」とは、歩行時の5つの小さな行動で大きな事故を防ぐ標語です。内容自体は単純ではありますが、取り組みを意識することで、仕事中の安全性を高めることができます。
労災は、従業員と企業のどちらにとっても避けたい事柄です。怪我や不良品の発生といった物理的な影響だけではなく、モチベーションの低下や信頼の低下といった、心理的な悪影響も与えてしまうでしょう。
「ポケテナシ」は、どれもが知ってすぐにできることばかりです。毎日の行動に少し気を付ければ良いだけの取り組みですので、ぜひ行なって見てください。
また、「ポケテナシ」以外の安全対策も大切です。有名な取り組みとしては、整理整頓からなる5S活動が挙げられます。企業全体で話し合い、労災ゼロの職場を目指していきましょう。