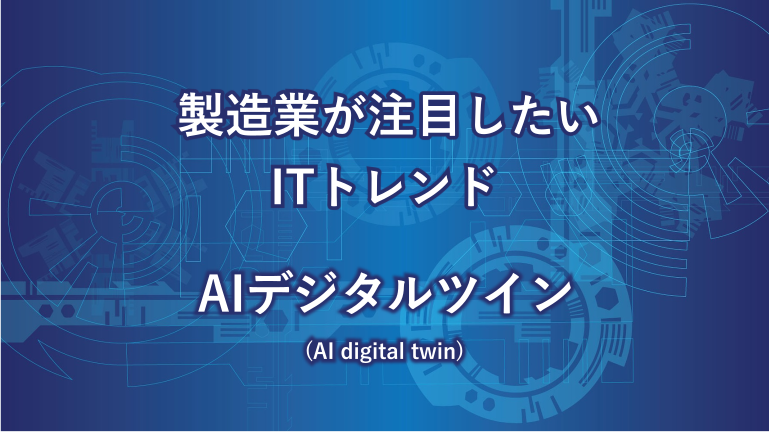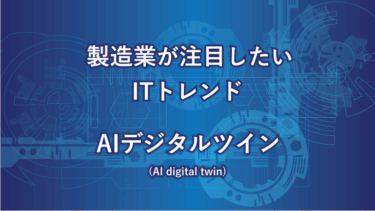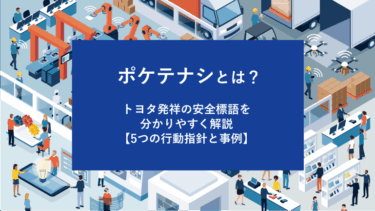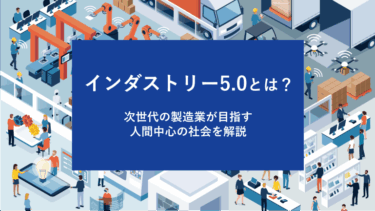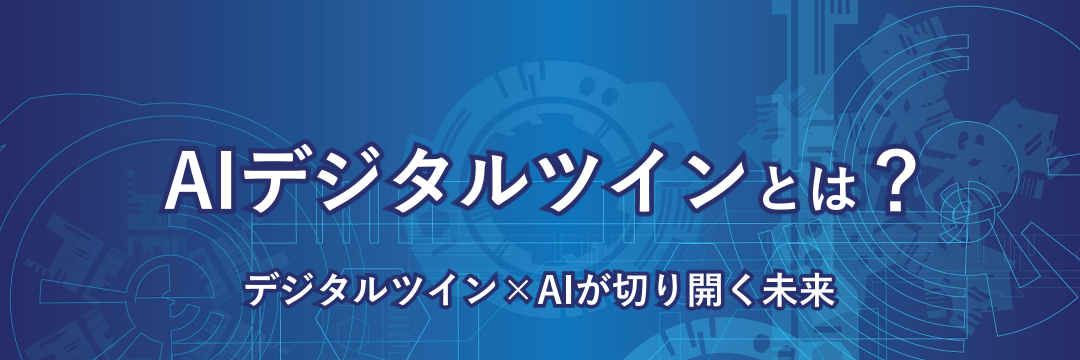
デジタルツインは、現実世界をデジタル空間に再現し、データをもとにシミュレーションや予測を行なう技術です。現実では困難な検証もデジタル上で実施できるため、世界中の企業や行政機関で活用が進んでいます。
そんなデジタルツインが、さらに進化を遂げつつあります。それが「AIデジタルツイン」です。AIを活用することで、従来以上に高精度かつ柔軟なシミュレーションを実現し、今後の社会基盤技術としても期待されています。
本記事では、AIデジタルツインの基本的な概念や、従来技術との違い、活用事例、そして将来性についてわかりやすく解説します。
AIデジタルツインとは?
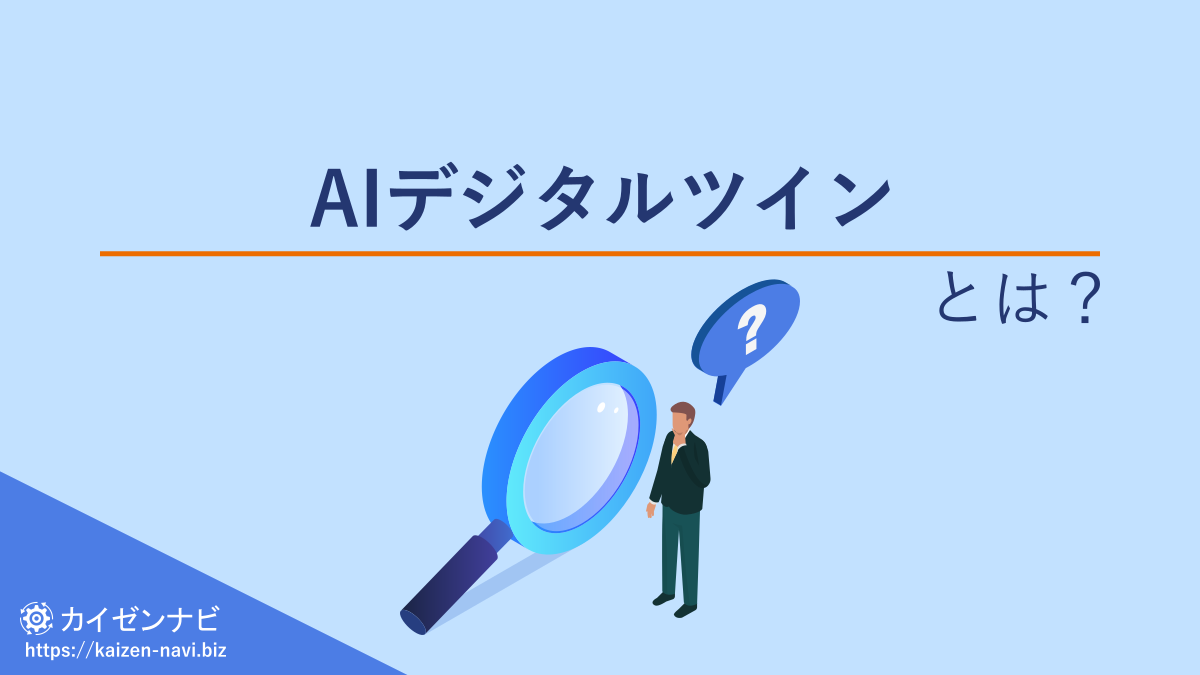
AIと付くことからAIを使った技術であることはわかりますが、実際にはどのような技術なのでしょうか?
AIデジタルツインの基礎定義について確認してみましょう。
基本定義
AIデジタルツインとは、AI(人工知能)を活用して高度化されたデジタルツイン技術です。従来のデジタルツインは、現実世界のデータをもとにデジタル空間で再現・分析を行なう技術でしたが、AIを組み合わせることで、より高速かつ高精度な処理や、予測、改善提案が可能になります。
基本的な構造は従来と変わりませんが、AIによってデータ分析・学習・意思決定の自動化が進み、「自ら進化するデジタルツイン」としての側面が強まっています。
補足:類似の技術である「メタバース」は、再現性よりも仮想空間の創造に重きを置いており、利用目的が異なります。混同しないよう注意が必要です。
別名(AIツイン/デジタルツイン×AI/デジタルツイン2.0)
AIデジタルツインには、いくつかの別名が存在します。たとえば:
-
AIツイン
-
デジタルツイン×AI
-
デジタルツイン2.0
いずれも、AI技術を組み込んだ新世代のデジタルツインを示す言葉であり、「次世代型のデジタルツイン」としての位置づけを表現しています。
従来型デジタルツインとの違い
AIによるサポートが行なわれることで、従来のデジタルツインとはどのような違いが出るのでしょうか?
デジタルツインの役割
AIデジタルツインとの違いを説明する前に、デジタルツインの役割について説明します。
デジタルツインは、高精度なシミュレーションを行なうために開発されたデジタル技術です。現実世界の状況をそのままデジタル世界に再現することにより、現実世界では難しいシミュレーションも、問題なくシミュレーションできるようになります。
例えば、津波被害のシミュレーションについてです。津波が来た際に「どのように水が流れるのか」「被害が大きい場所はどこか」などを検証したいですが、実際に津波を起こすわけにはいきません。計算によって検証する方法もありますが、机上の空論ではわからない部分も多く存在するでしょう。
そのような現実世界では難しい現象も、デジタル世界でなら簡単に再現できます。現実世界の街並みを再現することで、どのように変化するのかが一目瞭然となります。
ほかにも、成功するかわからないプロジェクトをデジタルツインによって安全に検証したり、巨大建造物の設計をデジタルツインによって再現するなど、さまざまな使われ方がされています。
デジタル空間なら、作成も削除もたやすくシミュレーションがしやすいです。気軽にシミュレーションできる場所としてデジタルツインが存在しています。
AIとの融合で広がる可能性
デジタルツインにAIを組み合わせることで、より精度の高いシミュレーションができるようになります。AIによってより高度な計算を高速で行なえるようになるため、シミュレーションの処理性能が向上するからです。デジタルツインの再現性自体も向上し、よりリアルなシミュレーションが可能となります。
ほかにも、AIの自動学習によって変化を再現しやすくなったり、予測精度が上がることで可能性の模索がしやすくなるなど、AIによってできることが広がります。
AIデジタルツインの特徴
AIデジタルツインは、従来のデジタルツインと比べ、以下のような特徴があります。
リアルタイム学習と自動化
AIデジタルツインの最大の特徴は、データを自動的に学習・最適化できる点です。シミュレーションの内容や結果を継続的に学習することで、より精密な再現や予測を実現します。
従来のアナログ作業では、数値の入力や調整に時間と手間がかかり、ヒューマンエラーのリスクも避けられません。しかしAIを活用すれば、こうした作業をすべて自動化でき、IoTと連携すればリアルタイムで数値の変化を反映することも可能です。
さらに、学習を重ねるほど精度が向上するのもAIならではの強みです。結果として、短時間で作業を終えられるだけでなく、コスト削減や業務効率化にも大きく貢献します。
未来予測とデータ補完
AIデジタルツインは、従来型に比べて精度の高い未来予測を実現できます。AIの強力な処理能力により、膨大なデータを高速に分析し、より確度の高いシナリオを立案できるためです。
さらに大きな強みが、データ補完能力です。シミュレーションに必要なデータがすべて揃うことは稀ですが、AIは既存データをもとに不足部分を推定・補完し、検証を可能にします。これにより、従来なら不完全に終わっていた検証も、より現実的な形で実施できるようになりました。
場合によっては、ほとんどのデータをAIが補完することも可能です。そのため、未知の領域や新しい分野でのシミュレーションにも対応でき、活用範囲は大きく広がります。
このように、AIのサポートによってデジタルツインは「再現ツール」にとどまらず、「未来を探索するツール」へと進化しています。
改善提案と意思決定支援
AIデジタルツインは、シミュレーションの実行にとどまらず、その結果を分析し、課題を抽出して改善策を提示することができます。単なる検証ツールから一歩進み、改善提案機能を持つアシスタントとして機能するのです。
さらに、統計データに基づく客観的な評価を行なうことで、意思決定を支援します。実現可能性の高い提案が示されれば、経営層やプロジェクト担当者は迷うことなく最適な方針を選択できるでしょう。
また、AIは人間が想定していなかった代替案を提示する場合もあります。これにより新たな選択肢が生まれ、プロジェクトをより円滑かつ柔軟に進められる点も大きな利点です。
メリットと課題
AIデジタルツインには、メリットだけではなく課題も存在します。
適切に活用するためには、それぞれの特徴に付いて知っておく必要があるでしょう。
主なメリット
-
プロセス全体を一元管理し、効率化を実現
-
膨大なデータをAIが処理することで精度向上
-
品質維持やリードタイム短縮を実現
-
コスト削減や労働負担軽減にも寄与
従来は「検証ツール」としての側面が強かったデジタルツインですが、AIを組み込むことで管理・最適化ツールとしての役割も拡大しています。
主な課題
-
大容量データの保存・処理に伴うストレージコスト
-
クラウド利用時のセキュリティリスク
-
専門知識を持つデジタル人材の不足
-
既存システムとの互換性や運用負荷
これらの課題を解決するためには、セキュリティ対策の強化や人材育成、システム統合の工夫が不可欠です。
活用シーン
AIデジタルツインをどのように活用すれば良いのか。それぞれの分野ごとに活用例について紹介します。
製造業での活用
製造業では、工場のデジタル化に活用されています。デジタルツインによって工場や生産ラインを再現することにより、生産工程をデジタル空間でシミュレーションします。デジタル空間でさまざまな流れを再現することで、より効率的な運用が見つかり、生産工程の効率化が行なえます。
また、可視化して管理する方法もデジタルツインの使い方です。現在の状況をそのままデジタルツインで再現し、物流の流れやボトルネックなどを一元管理できます。可視化をするためにはリアルタイム情報が必要ですが、AIのサポートがあれば難しくありません。AIデジタルツインだからこそできる活用方法といえるでしょう。
ほかにも、車の走行実験をデジタル空間で行なったり、新しい製品を作成したりなど、検証目的でデジタルツインが使われています。
医療分野での活用
医療分野では、技術の練習目的で活用されています。実際の症例をデジタルツインで再現し、その症例に対して手術などの処置を行なうことで、若手医療スタッフの技術向上を目指します。実践的な技術が身につくだけではなく、実例に対処することで自信を持てるようになります。
また、院内を可視化することも可能です。可視化によって医療スタッフや病床の稼働状況などが把握でき、運営の最適化が行なえます。患者のバイタルデータをリアルタイム参照すれば、患者の一元管理も可能になるでしょう。
スマートシティでの活用
スマートシティでは、防災目的で活用されています。津波の被害シミュレーション以外にも、地震や火災、停電など、さまざまな可能性を考慮して検証を行ないます。検証した結果を基に防災対策を行なうほか、救援方法のシミュレーションを行なうなど、災害大国である日本ならではの活用方法といえるでしょう。
ほかにも、都市全体をデジタル化することで3Dの観光マップを作成したり、インフラ整備のシミュレーションに活用したりもします。
都市全体だとデータ処理も大変ですが、AIの処理能力があれば、都市全体のデータ量であっても問題なく対応可能です。
日常生活での活用
日常生活の中でも、デジタルツインは活用されています。主な例としてはスマートホームが挙げられ、デジタルツインによって家をデジタル管理します。
また、デンマークのスーパーマーケットでは、「デジタルツイン冷蔵庫」を導入しています。今までは全て人の手によって温度調整などが行なわれてきましたが、デジタル化によって、全て自動で管理・調整を行なってくれるようになりました。冷蔵庫の扉を開けずに中の状況を把握できることから、電気代の節約にもなります。
ほかにも、普段食べている野菜の管理にデジタルツインが活用されていたりなど、知らないだけで、さまざまな場所でデジタルツインが活用されています。
今後の展望
AIデジタルツインは、製造業だけではなくさまざまな業界で可能性が期待されています。今後どのように展望するのか予測をしてみましょう。
デジタルツインからの進化の必然性
デジタルツインからAIデジタルツインへの進化は、激動する情勢の変化に対応するためのものです。
近年は、技術発展や世界情勢の変化が激しいことから、予測不可能な時代としてVUCA時代とも呼ばれています。情勢の変化が激しいからこそ、正しく変化を読み取る必要があるでしょう。
しかし、変化が激しいからこそ、正しく読み取るのは難しいです。データをたくさん集め予測を立てたとして、すぐに変化が生じるようでは対策が後手に回ってしまいます。
そのため、情勢を正しく読み取る方法としてAIが必要とされます。AIの高い情報収集能力と処理能力なら、情勢の変化に先駆け対処することも難しくはありません。
デジタルツインであっても、AIの必要性は同じです。迅速なシミュレーションやリアルタイムによる管理は、変化する顧客ニーズに応えるために必要といえます。AIデジタルツインに進化したことは、時代に合わせた必然性ともいえるでしょう。
また、AIの発展も必然性の一端です。近年はAI技術が劇的に進歩しており、デジタルツインに限らず、さまざまなデジタル技術で活用がされています。
DXの次の世代としてAX(AIトランスフォーメーション)が注目されているように、今後はAIの可能性が期待されているわけです。
今後の発展分野と可能性
現在は製造や搬送分野で活躍するAIデジタルツインですが、今後はさまざまな分野で見かけるようになると予想ができます。近年はデジタル社会への移行が推進されており、さまざまな分野でデジタル技術が取り入れられているからです。
実際に、多くの医療現場で活用されるほか、農業業界でもAIデジタルツインの活用が進められています。将来的には学校の勉強でAIデジタルツインを活用したり、運動力学をAIデジタルツインで研究してスポーツに反映したりするかもしれません。
総務省が発表した「デジタルツインの市場規模」によると、2022年から2035年の間に、約63倍もの成長が予測されています。今後も市場希望が拡大していく中で、さまざまな可能性が期待されます。
まとめ:AIデジタルツインがもたらす未来
AIデジタルツインは、AIによって演算処理を行なうデジタルツインのことです。従来のデジタルツインよりもAIによって処理速度が向上しており、より高度なレベルでデジタルツインを使うことができます。
デジタルツインは、今後のデジタル社会において欠かせない技術です。安全にプロジェクトを進めるため、デジタルツインを活用する機会も多くなるでしょう。
また、可視化も業務を進めるうえで欠かせないことです。作業の効率化だけではなく、品質維持による信頼性向上や属人化の防止など、製造における課題解決に役立ちます。
製造業以外でも、年々デジタルツインの活用は広まっています。製造業だけではなく、幅広い分野で、AIデジタルツインが活用されていくと予想ができるでしょう。
VUCA時代に対応するためにも、AI技術の進歩や発展に注目をしてみてください。
- AIデジタルツインの位置づけ整理
- AIデジタルツインは、次世代型デジタルツインの位置づけ
- AIの処理能力が加わることで、より高度なシミュレーションが可能
- できることが広がったことで、ほか業界でも可能性が期待されている
- AIを扱うための知識やコストが余計に必要であり、運用難易度が上がっている