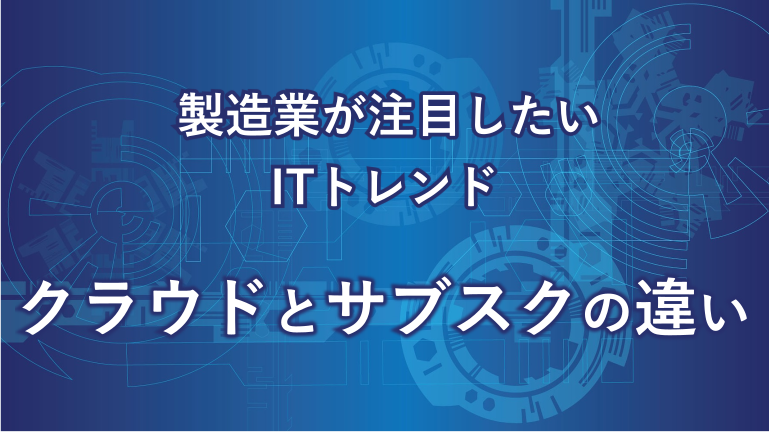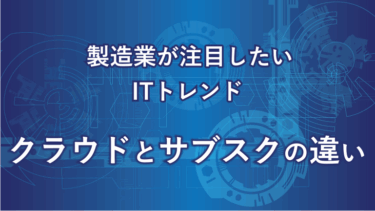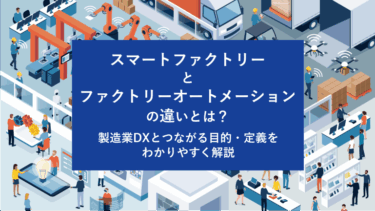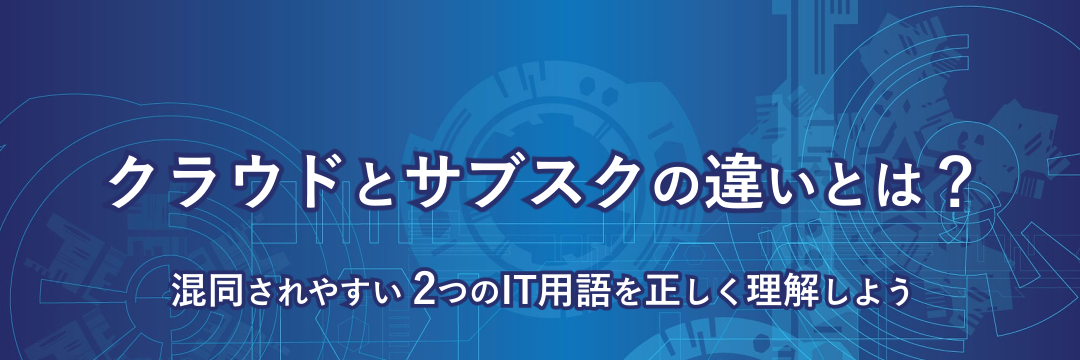
クラウドとサブスクは、日常でもよく耳にする用語です。どちらも便利な仕組みとして広く利用されていますが、一緒に使われることが多いため、混同されやすいという問題もあります。
しかし、クラウドは「提供の仕組み」、サブスクは「支払いの仕組み」と、それぞれまったく異なる概念です。誤解したまま使うと、サービス選定などで思わぬトラブルにつながる恐れもあります。
本記事では、混同されやすい2つのIT要素「クラウド」と「サブスク」の違いについて、わかりやすく解説します。
「クラウド」とは何か?
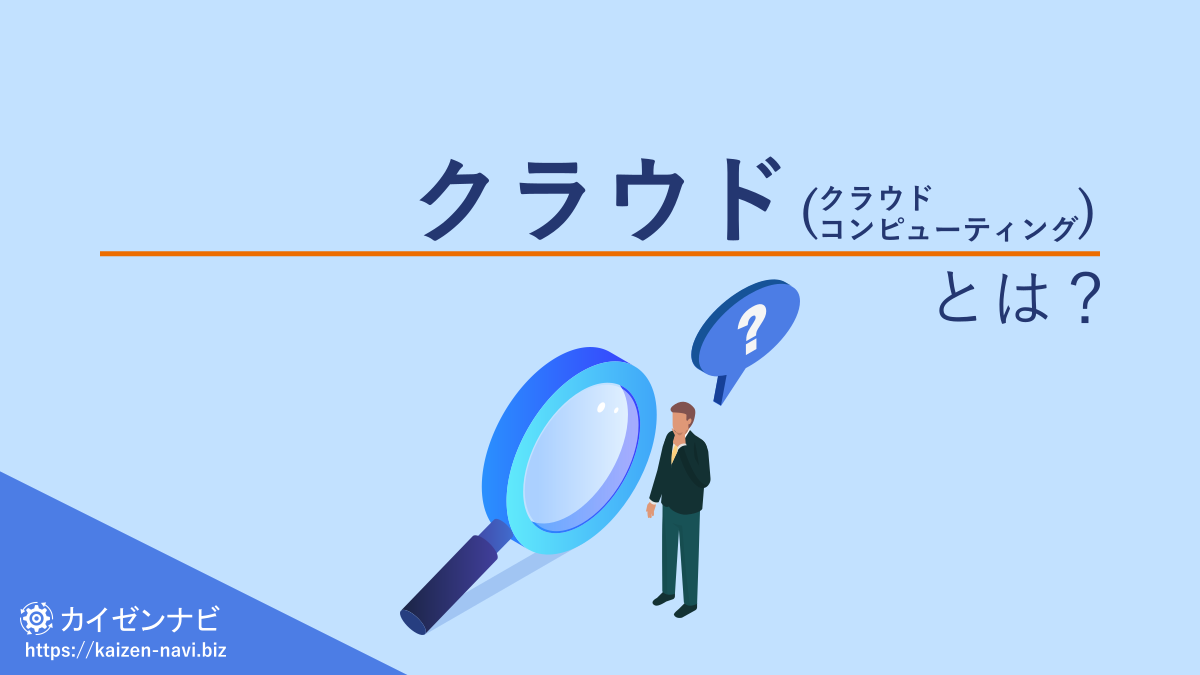
データを保存する際によく見かけるクラウドですが、クラウドとはどのようなものなのでしょうか?
クラウドの基本定義と背景
クラウド(クラウドコンピューティング)とは、データをインターネット上で保管する考え方のことです。パソコンやスマートフォンなどの電子端末からインターネットサーバーにアクセスすることで、データのやり取りを行ないます。
クラウドが開発された背景には、管理を楽にする考えがありました。今までは個別にサーバーを用意し保管していましたが、それだと管理に手間とコストがかかり、あまり効率的とはいえません。
そのことから、一元管理する方法としてクラウドが開発されます。そして、クラウドが開発されたことでデータ管理がしやすくなるほか、コスト削減や場所を問わず利用できるなどのメリットも得られるようになります。
また、便利であることは、クラウドを広める要素でもあります。場所を問わず利用できる、アプリケーションのインストール不要、保存はファイルを移動させるだけなど、利便性の良さから広まっていきます。
現在では、さまざまなネットワークサービスにクラウドが利用され、使わない日はないといっても過言ではありません。普及が広まって以来、とても身近にあるサービスといえるでしょう。
ちなみに、「クラウド」と呼ばれる理由は、ネットワークを図解した際、雲の絵が用いられていたからです。サービス先の相手がわからない様子が雲のようであり、そのままクラウド(雲)の名称で定着していきます。
オンプレミスとの違い
オンプレミスとは、サーバーを自社で管理する運用方式のことです。社内に専用のサーバーを用意し、そのサーバーにデータを保管して運用をします。
クラウドとの違いは、データの保管場所にあります。クラウドはインターネット上にあるデジタルサーバーに保存しますが、オンプレミスは社内にある物理的なサーバーに保存をします。大まかにまとめると、保存先が外部サーバーか内部サーバーかの違いといえるでしょう。
クラウドは利用コストが安く導入が容易、オンプレミスはセキュリティ性が高くカスタマイズしやすいといった特徴があります。どちらが優れているといったことはなく、目的に合わせて選ぶことが大切です。
クラウドの主な種類(SaaS / PaaS / IaaS)
クラウドには、「SaaS」「PaaS」「IaaS」と呼ばれる3つの利用形態があります。
SaaS(Software as a Service)は、インターネット経由でソフトウェアを利用できるサービスのことです。WebメールやWeb会議システムのように、ソフトウェアをインストールせずともインターネット経由で利用ができます。
PaaS(Platform as a Service)は、開発プラットフォームを利用できるサービスです。開発ツールが始めから用意されており、ツールを使って自由にアプリケーションなどの開発が行なえます。
IaaS(Infrastructure as a Service)は、インフラ基盤のみが用意されたサービスです。ネットワークがつながったサーバーが用意されていますが、基本的にそれだけです。開発プラットフォームなどもないため、すべて自分たちで作成します。
- SaaS:ソフトウェアが完成しており、そのまま利用できる
- PaaS:開発プラットフォームが用意されており、自分でアプリケーションを作る
- IaaS:サーバーのみが用意され、すべてを一から作る
細かな違いはありますが、主な違いは利便性と自由度の差です。SaaSは既に形ができているため誰でも簡単に利用できますが、完成されていることでカスタマイズの猶予があまりありません。用意されたサービスを、そのまま使う形となります。
逆に、IaaSはそのままではアプリケーションを利用できませんが、自分たちが使いやすいよう自由に作ることができます。知識がない人がIaaSを利用しても、サービスを持て余してしまうだけです。クラウドを利用する際は、自分たちの知識や技術に合わせて選ぶようにしてください。
私たちの生活にあるクラウドサービスの例
代表的なサービスといえば、「Gmail」や「Yahoo!メール」といったWebメールが挙げられます。
SaaSに分類するサービスであり、各運営会社が用意したサーバーを介してメールの送受信を行ないます。また、「Facebook」や「Instagram」といったSNSもクラウドを利用したサービスです。投稿した画像や動画は共有サーバーに保管され、サーバーにアクセスすることで閲覧やダウンロードができるようになります。
ほかにも、近年普及しつつあるWeb会議「Zoom」や、通販サイトで知られるAmazonが提供する「Amazon Web Services」などにも、クラウドが利用されています。DXへの推進に伴い、2018年に政府からクラウドファーストとなる方針が発表されました。クラウドは今後のデジタル社会の要となるサービスであり、情報システムを導入する際に優先的に活用を検討するよう指示がされています。
そのため、ネットワークを介したサービスには、ほぼクラウドが利用されているといって過言ではありません。意識していないだけで、毎日何かしらのクラウドサービスを利用しているのです。
「サブスク」とは何か?
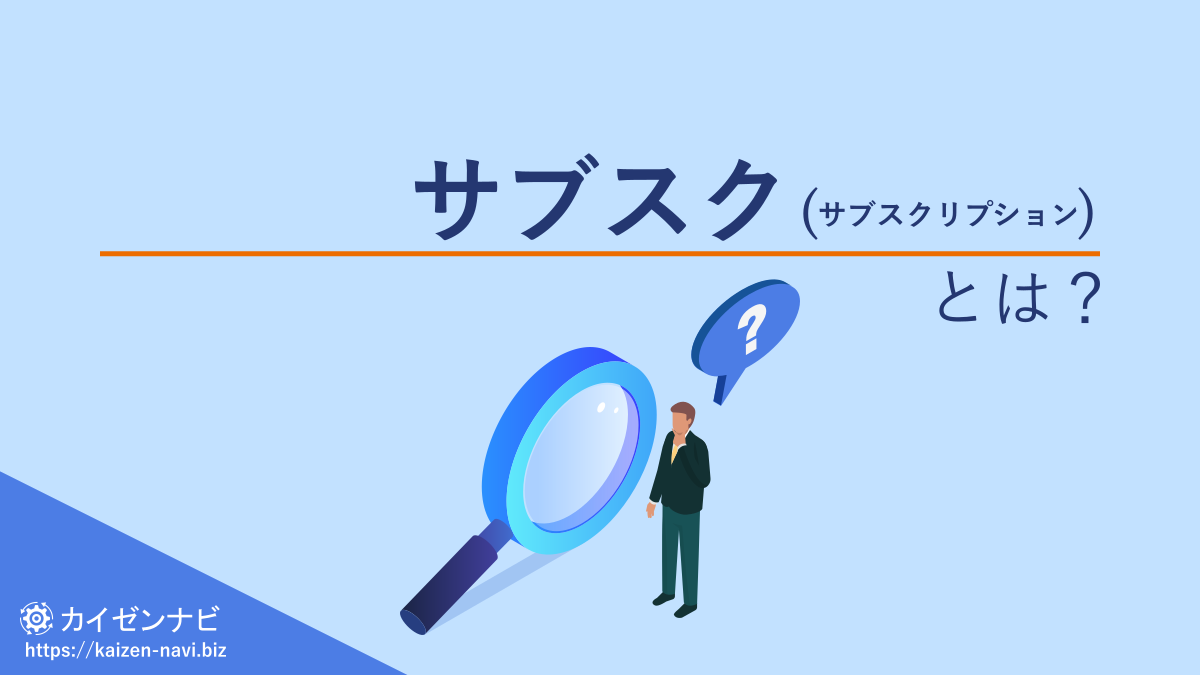
動画サイトを利用する際によく見かけるサブスクですが、サブスクとはどのようなものなのでしょうか?
サブスクの基本的な意味と考え方
サブスク(サブスクリプション)とは、サービスの定額制支払いのことです。和訳すると「定期購読」「定額制」といった意味となり、定額支払いをすることで、期間内なら提供されるサービスを自由に利用できます。
一般的な製品の売買とは異なり、サブスクは「サービスを利用する権利」に対して支払います。イメージとしては、遊園地などの入園料に近いです。そのため、プランの利用を止めるとサービスが利用できなくなります。
代表的なサービスとしては、「Amazonプライム」や「YouTube Premium」などが挙げられます。ほかにも、音楽サイトや書籍サイトなどでも採用されており、普段生活する中で見かけることが多い支払い方式となっています。
「所有」から「利用」へという価値観の変化
サブスクが普及した背景には、近年における価値観の変化が関係しています。近年は「物を購入して手元に置く」ことよりも「体験をして思い出に残す」ことが求められており、「所有から利用へ」変化したことで、サブスクを利用する人が増えているのです。
近年は、デジタル技術が発展したことで、さまざまなことがデジタル化しています。特に多いのが娯楽に関してであり、「インターネットがあれば娯楽に困らない」といわれるほどです。漫画、映画、ゲームなど、ほとんどの人がデジタルコンテンツに触れたことがあると思います。
ただ、デジタルコンテンツはデータからなるコンテンツであり、現物には残りません。そのことから、昔のように現物を必要とせず、体験を重視するようになります。
また、近年における物価高の影響も、サブスク利用が進む要因といえます。サブスクはコンテンツの量に対して料金が安く、とてもコストパフォーマンスの良い仕組みです。安くたくさん楽しもうとすることから、サブスクを利用する人が増えていきます。
現在では、サブスクの仕組みが一般的となり、娯楽以外でもサブスクの仕組みが使われています。今後もデジタルコンテンツが使われることで、サブスク利用が増えていくでしょう。
IT分野以外に広がるサブスクモデルの事例
IT分野以外だと、ジムやスクールの定額利用が挙げられます。月の始めか終わりに料金を支払っておくことで、後は時間が空いたタイミングで好きなようにスペースを利用できます。
また、最近では商品の定期購入も有名です。「毎月500円を支払うことで毎週卵が送られてくる」といったように、サブスクによる買い物も増えています。食品や日用品だけではなく、花や香水などもサブスク利用できるようになりました。
ほかに、車や家具のサブスクモデルもあります。定額制でレンタルができ、期間中は自由に使用可能です。もし商品が気に入った場合はそのまま購入もできるなど、サブスクで終わらせないサービスを提供しています。
サブスクといえばデジタルサービスが有名ですが、探してみれば、さまざまな分野でサブスクモデルを見ることができます。
「クラウド」と「サブスク」はどう違うのか?
クラウドとサブスクについて説明していきましたが、実際にはどのような違いがあるのでしょうか?
クラウド=提供形態、サブスク=支払い形態
クラウドとサブスクはセットで使われることが多いですが、それぞれの概念は全くの別物です。クラウドは、サービスを提供する仕組みのことです。運営が提供するサーバーやアプリケーションを、利用者が自由に使うことができます。
一方で、サブスクはサービスへの支払い方法です。定額支払いをすることで、サービスを利用者が自由に使うことができます。どちらも利用者が自由に使えるサービスですが、提供方法と支払い方法では意味が大きく異なります。
クラウドは提供の仕組み、サブスクは支払い方法と、意味が異なります。混同しないようにしましょう。
よくある誤解と実際の違い
よくある誤解として、クラウドとサブスクを混同してしまうことがあります。これは、クラウドとサブスクが一緒に使われるケースがとても多く、「クラウド=サブスクでの支払い」が定着してしまっているからです。クラウドとサブスクがセットになっていることから、一つの仕組みとして勘違いしてしまいます。
もちろん、買い切り型のクラウドサービスも存在しているため、必ずしも「クラウド=サブスクでの支払い」となるわけではありません。それでも、SaaSを利用したサービス(Netflixなど)のほとんどはサブスクで提供をしており、デジタル知識が低い人だと間違いやすいといえます。
両者が組み合わさるケースとそうでないケース
クラウドとサブスクは、「期間限定で利用する」ものに対して相性が良いサービスです。
例えば、車のサブスクについてです。「夏休みの間だけ必要」といったような場合だと、車を購入するより期間でレンタルした方が安く済みます。管理も不要なため、駐車場やメンテナンスなどの維持コストを安く済ませられるでしょう。
ほかにも、映画や漫画などは、一度見たら充分な人が多いです。そのような人は、すべて購入するよりもサブスクでレンタルした方が多くの作品を楽しむことができます。
逆に、「長く使い続ける」ものに対しては相性が良くありません。ゲームのように数か月や数年単位で同じものを使い続けるような場合は、レンタルよりも購入してしまう方が安く済みます。
クラウドとサブスクは相性の良い場面もありますが、すべてのケースに当てはまるわけではありません。サービス内容や用途に応じて適切に使い分けることが大切です。
「クラウド×サブスク」モデルの活用例とメリット
クラウドとサブスクは、セットでよく使われているように相性が良い仕組みです。クラウドとサブスクをセットで使っているサービスには、どのようなものがあるのでしょうか?
主なSaaSサービスに見る融合例
有名なサービスには、「Netflix」があります。Netflixとは映画やドラマなどをインターネット上で配信するサービスのことで、定額料金を支払うことにより、サーバーに保管された映像を自由に視聴できます。
また、「Adobe」や「Microsoft 365」といったサービスも、サブスクモデルが使われています。作成したデータはクラウドサーバーに保存され、次回利用する際にクラウドサーバーから読み込まれます。
ほかにも、「Chatwork」や「Zoom」も有名です。どちらも基本無料ですが、機能に制限が設けられており、サブスクを利用することで機能が解放されます。
このモデルのメリットと注意点
サブスクのメリットは、初期費用が抑えられる点です。サーバーやソフトウェアをレンタルできるため、購入するよりも安く済ませられます。
また、運営が用意したサーバーやソフトウェアをそのまま使えるため、準備の手間が少ないメリットもあります。利用を停止する際もプランを解約するだけと、気軽に利用をしやすいです。
いろいろなサービスやプランを試しやすく、自社に合ったサービスを低コストで探せるでしょう。
一方で、長期利用する場合は買い切りよりも高くなる可能性があります。いくら定額が安くても、長く続けば出費はかさんでいくからです。お得に利用するためにも、運用コストはしっかりと計算しておく必要があるでしょう。
ほかにも、運営側の都合でサービス内容が変わるリスクもあります。操作方法やデザインが変更されるだけではなく、場合によっては、料金の値上げもあり得るでしょう。
サブスクは、あくまでも利用できる権利を支払っているだけで、権利自体は運営側のものです。運営次第で内容が変わる点は注意が必要といえます。
サービス選定で気をつけるべきポイント
サービスを選ぶ際は、自社との相性を意識してください。クラウドは外部サーバーを利用するサービスですので、種類によっては他システムと連携できない場合があります。
もちろん、単独で利用するなら気にする必要はありませんが、データの送受信ができると業務効率が向上します。「クラウドを導入したところ、他のシステムが起動しなくなった」といったこともあり得ますので、相性は必ず確認をしておいてください。また、相性と合わせて利便性も意識するポイントです。必要な機能が備わっているのはもちろん、使いやすくわかりやすいデザインをしていると、利用者が理解しやすくなります。自社に合わせてカスタマイズもできるようなら、尚更使い勝手が良くなるでしょう。
運用コストも踏まえ、長期的に使っていくことを念頭に置くと利便性が判断しやすいです。
ほかにも、解約のしやすさやセキュリティ性も気にしてください。解約手続きが面倒なサービスだと、自由に利用が止められません。セキュリティレベルが低いと情報漏えいのリスクが高まるなど、トラブルの原因となってしまいます。
「使えればどれでも同じ」と思うかもしれませんが、どれも同じものではありません。長く使うことを踏まえ、しっかり吟味して選びましょう。
選ぶ際の見るべきポイント
- 自社システムとの相性
- 利用コスト
- 目的に合った機能
- 使いやすく分かりやすいデザイン
- 自社に合わせられるカスタマイズ性
- 解約のしやすさ
- サポート体制の充実さ
- セキュリティの高さ
クラウド・サブスク型サービスを選ぶときのチェックポイント
サービスを正しく利用するため、サービスの選び方についても知っておきましょう。
クラウドサービスを選ぶときの着眼点
クラウドサービスを選ぶ際は、利用できる機能について注目してみてください。SaaSとIaaSは、同じクラウドサービスでも利用できる内容が大きく異なります。たとえ同じSaaSのクラウドサービスでも、提供する企業が異なればサービス内容は異なるでしょう。
「なぜクラウドサービスを導入するのか」その理由を明確にし、必要な機能が備わっているサービスを選ぶことが大切といえます。また、外部サイトを利用することから、セキュリティ性能やサポート体制も重要なポイントです。セキュリティやサポートがしっかりしていれば、外部サイトであっても安心して利用ができます。使い方でわからないことがあっても、気軽に相談ができるでしょう。
コストや拡張性なども気になるポイントですが、「機能性」と「運営の信用性」の2点は、必ず確認するようにしてください。
サブスク契約で確認すべき条件
サブスク契約では、利用できるサービスの内容について確認してみてください。内容以外のことはできないため、必要な機能の記載がないと契約しても意味がありません。機能の有無はもちろん、利用回数や期限など、利用条件をしっかり確認しておきましょう。
また、解約条件も重要な確認要素です。解約方法がわからないサービスは、悪徳業者である可能性が高いといえます。解約したくても解約ができず、将来的にトラブルの原因となります。
ほかにも、自動更新の有無も気になるポイントです。自動更新は便利ですが、解約を忘れてしまうとムダに支払いが続いてしまいます。
買い切りではないからこそ、サービスの内容はよく確認する必要があります。無料でお試しができるサービスもありますので、無料版で使い勝手を試してから、サブスク契約をするのもいいでしょう。
まとめ
クラウドとサブスクは、それぞれ別のことを意味し、概念そのものが異なります。クラウドは提供形態、サブスクは支払い形態といった違いがありますので、間違えないよう注意してください。
買い切り型のクラウドサービスがあるように、クラウドとサブスクは必ずしもセットで使われるわけではありません。そのため、クラウドとサブスクをセットで覚えてしまうと、サービスの内容を正しく把握ができなくなります。
サービスに溢れる現代において、内容の把握はサービス選定における本質的な視点といえます。必要なサービスを正しく選ぶためにも、クラウドとサブスクの仕組みについてしっかり理解しておきましょう。